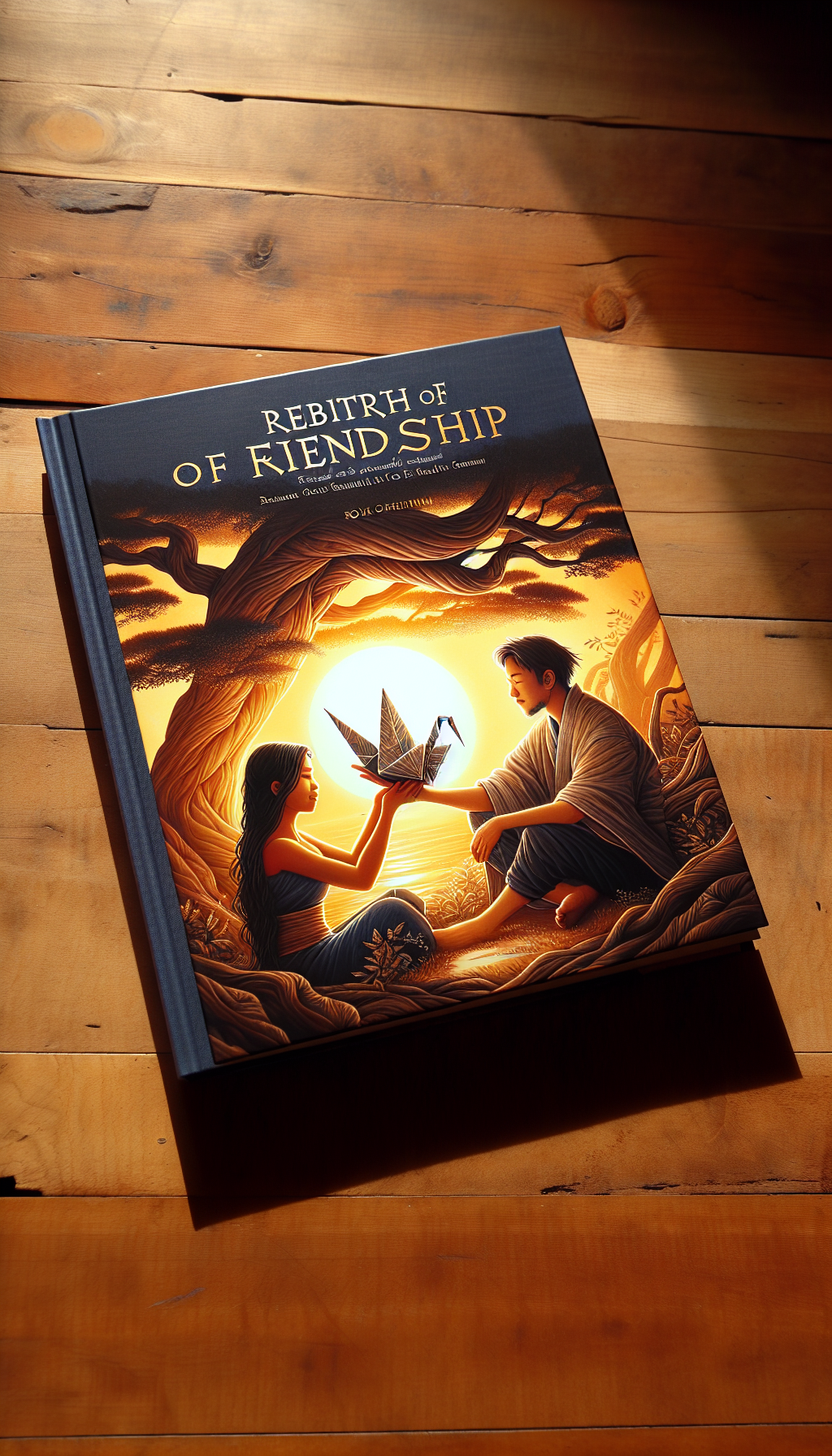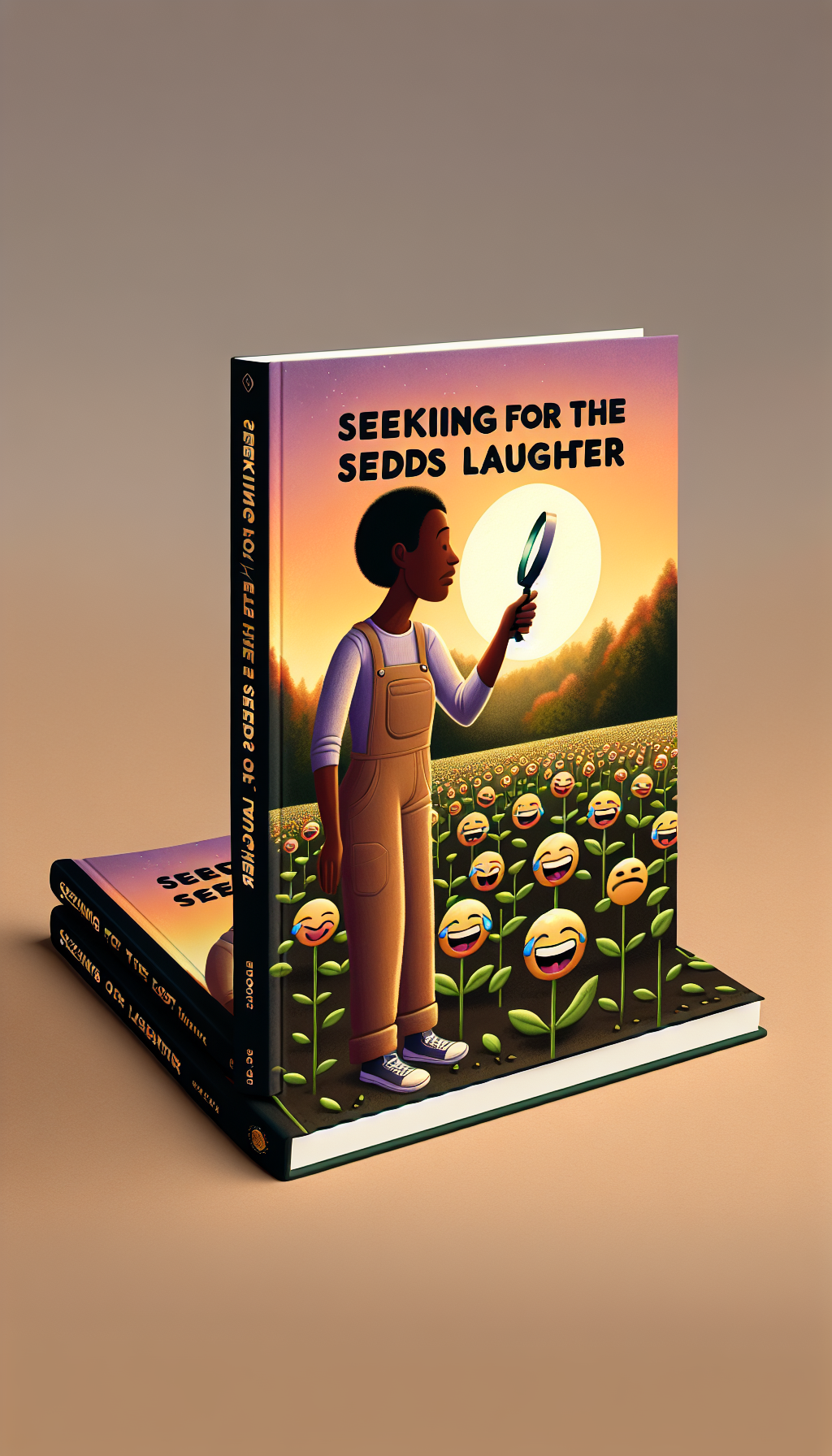心のメロディー
私たちには、姉妹というものがある。私と彼女、名は美和。10歳年上の彼女は、幼い頃から私の憧れだった。彼女の白い肌、ふわふわの黒髪、笑顔がいつも明るく、どんな時も私を包み込んでくれた。
私の記憶の中で、美和はいつも強い存在だった。私がちっぽけな心を持っていた頃、彼女は自分の夢を描いていた。彼女はピアニストになりたいと言った。私もその夢に憧れて、一緒にピアノを習い始めた。美和の指先から奏でられるメロディーは、まるで魔法のように私を魅了した。彼女は厳しくも優しく、私にたくさんのことを教えてくれた。
しかし、美和はいつしかその夢から遠のいてしまった。大学に入ってから、彼女は学業に追われ、ピアノを弾く時間は次第に減少していった。「忙しい」という言葉は、彼女の口癖になっていた。私はついに彼女が納得するようなピアニストになれずに苦しむ姿を見て、自分の夢を追い求めることができなくなった。姉の影に隠れたまま、小さな存在でいることに慣れてしまった。
それから数年後、美和は結婚して家族を持った。彼女が新しい生活を始めることに少し寂しさを覚えたが、彼女の幸せを心から応援した。彼女は子供を持ち、忙しい日々の中で自分の時間を持つことができなくなっていった。ピアノの音色は、もう彼女の部屋からは聞こえなくなっていた。
私が大学を卒業し、仕事を始めたころ、美和との距離はますます広がっていった。彼女は母親としての責任に追われ、私は社会人としてのプレッシャーに苦しんでいた。電話やLINEのやり取りも次第に少なくなり、私たちの関係はどこか希薄になっていった。姉の笑顔を思い返すと、心が締め付けられた。
そんなある日、家族で集まる機会があった。美和の家族と私の家族が一緒に過ごす時間、懐かしさとともに温かい気持ちが湧き上がってきた。子どもたちの笑い声が響く中、美和はふと笑顔を浮かべて、「昔は一緒にピアノを弾いていたよね」と言った。その言葉を聞いた瞬間、私は涙がこみ上げてきた。彼女のことを忘れたわけではない。むしろ、もっと彼女のことを知りたかったのだ。
「美和、またピアノを弾こうよ」と私は言った。その言葉に彼女は驚いた表情を浮かべたが、次第に頷いた。「うん、やってみようか」。
数週間後、美和の家に集まることにした。私はピアノを持ち込んだ。はじめはぎこちない指使いだったが、徐々に二人の心が通じ合う感覚が蘇ってきた。音楽の力は素晴らしい。私たち姉妹の距離が縮まっていくのが分かった。美和の笑顔は、かつての輝きを取り戻したかのようだった。
「私たち、もっと一緒に楽しいことをしよう」と彼女が言った時、心からの喜びが湧き上がった。彼女がかつての夢を再び見つけることができるかもしれない、そう思った。
美和と私は定期的に集まるようになった。ピアノを弾きながら、お互いの夢や生活の話をする。彼女の子供たちも巻き込んで、音楽の中で繋がる時間が増えていった。美和が少しずつ自分を取り戻していく姿を見て、私も彼女に背中を押されているように感じた。そして、いつしか私は自分の夢に向かって進み始めた。
姉妹の関係は、時に疎遠になりがちだ。しかし、心の奥底で繋がっていることを忘れないでいたい。私たちの物語は、また新たな章を迎えた。これからも、美和と共に色々なメロディーを奏でていこうと思う。心を通わせることの大切さを学んだ今、私たちの巻き戻しは、まだ始まったばかりなのだ。