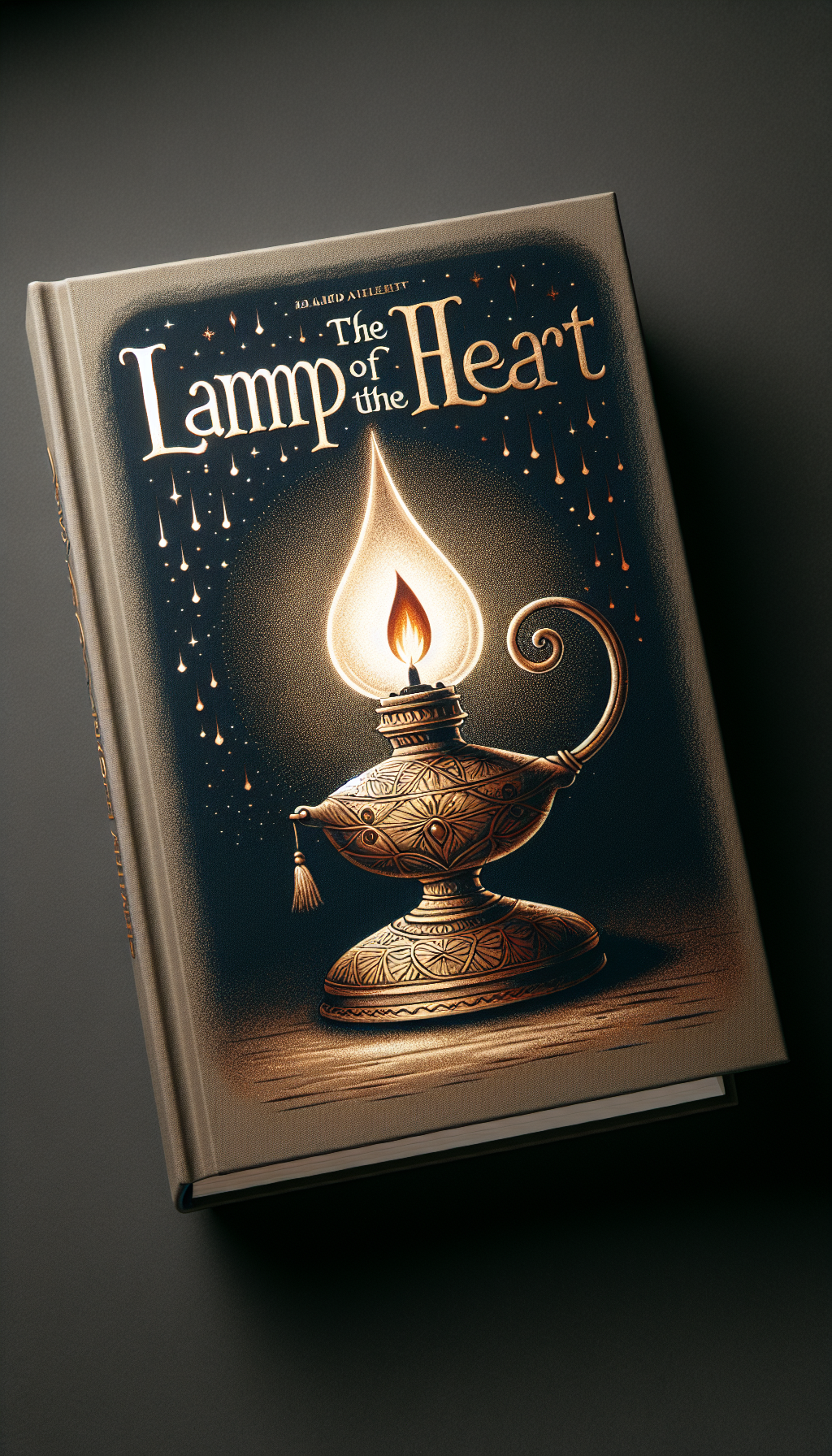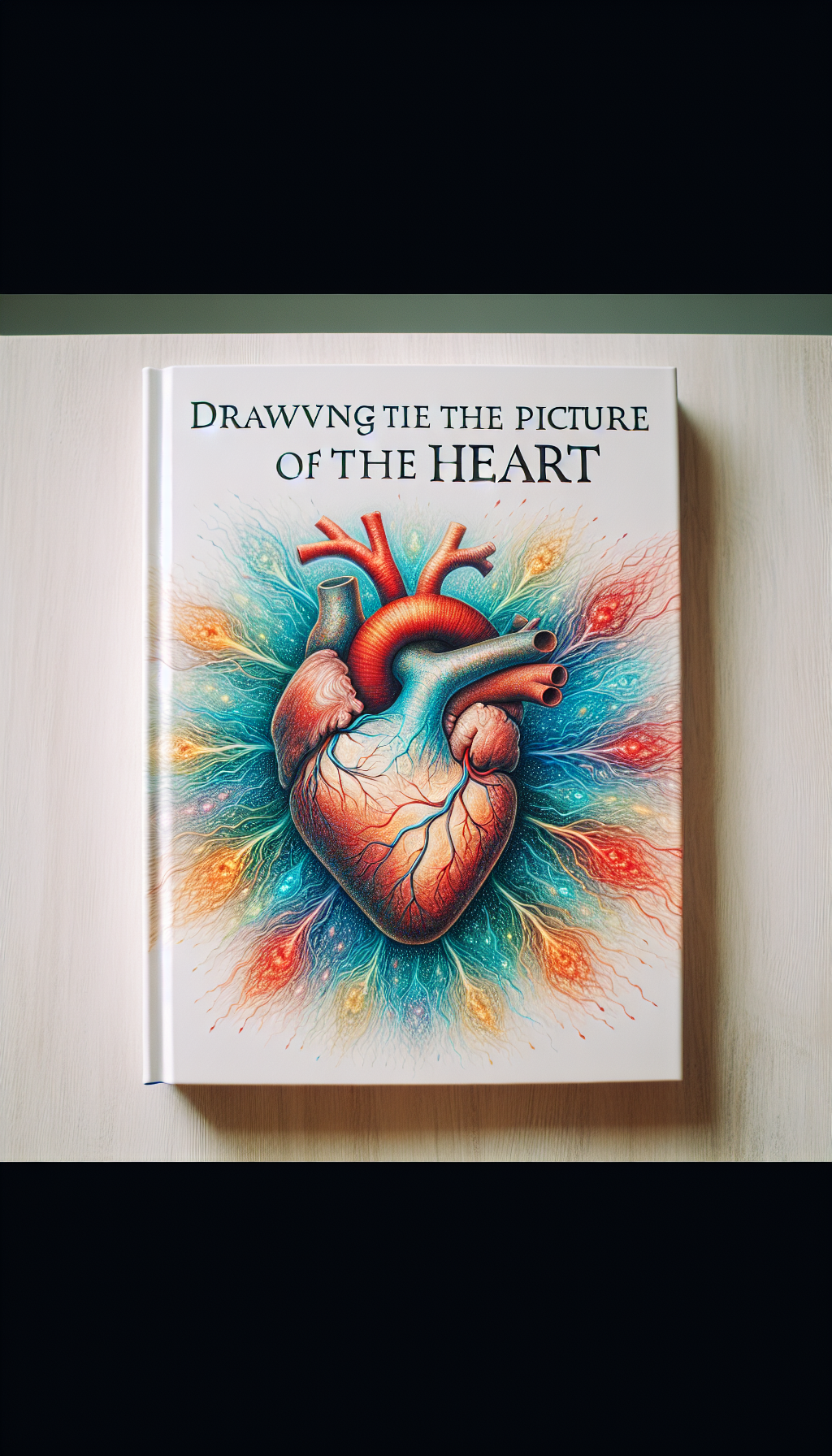日常の小さな光
朝の光がカーテンの隙間からこぼれ、薄明るい部屋を包み込む。田中明子は、まだ寝ぼけた頭を振りながら、ベッドから身を起こした。時計を見ると、もうすぐ7時。遅く起きると、朝食を用意できなくなる。急いで洗面所に向かい、顔を洗う。冷たい水が肌にあたると、少しずつ目が覚めてくる。
身支度を整え、リビングに降りると、キッチンでは母が朝食の準備をしていた。昨夜の残り物の味噌汁と、白ご飯、目玉焼き。お皿が並べられ、食卓はシンプルだが、心温まる光景だった。朝食を食べながら、明子はテレビのニュースに耳を傾けた。毎日のように流れる政治の話や経済の動向が、どんなに遠く感じられるか。そう思いながらも、どこかで自分の人生に影響を及ぼしているのだろうかと考える。
「明子、学校は大丈夫?」母が心配そうに声をかける。「うん、大丈夫」と明子は笑顔で返事をする。学校生活は表面的には順調だ。しかし、クラスには少し気まずい空気が漂っていた。友達のあいだで微妙な競争心が芽生え、些細なことでギスギスすることもあった。置いてきぼりになることが怖かった。明子は、そんな自分を感じながらも、平和な日常を守りたいと思っていた。
食後、学校に向かう途中、近所の猫が道の真ん中で日向ぼっこをしていた。明子は立ち止まり、猫を眺める。白くて小さな体が、気持ちよさそうに日光を浴びている姿は、なんとも愛らしい。猫は目を細め、明子の存在に気づくと、少しだけ動いて、また寝た。明子はその猫と目が合い、心が癒される感覚を覚えた。
学校に着くと、教室はすでに賑やかだった。友達と話しながら、自分の席に着く。だが、どこか心がざわついていた。気づけば、周りの会話が耳に入らず、自分だけが孤立しているような気がしてならなかった。授業が始まっても、その不安感は消えなかった。特に何かが起こるわけではないのに、胸が重く、思考が止まったままだった。
午前中の授業が終わり、昼休み。明子はいつも通り友達のグループに合流したが、会話が噛み合わず、浮ついた感じが続いた。友達が別の友達と楽しそうに笑い合う姿を見ると、あまりな気まずさに、自然と遠くを見つめてしまった。そんな自分に情けなくなる。まだ時間はある、そう自分に言い聞かせ、明子は教室の隅に目をやった。そこには、ずっと気になっていた一人の男子生徒がいた。
彼はいつも本を読んでいる。おそらく誰とも対話を必要としない一人の世界にいるのだろう。明子はその彼に話しかける勇気が出なかった。「彼とはどうやったら話せるんだろう」と想いを巡らせながら、彼に目を奪われていた。結局、その日の昼休みは何事もなく過ぎていった。
学校が終わり、明子は帰り道をゆっくり歩いた。青空が広がり、気持ちいい風が頬をなでる。日常の小さな幸せを感じながら、帰宅した。夕食の準備を手伝った後、明子は部屋に戻り、宿題を始める。しかし、どこか集中ができなかった。心の中のもやもやが、何かを阻んでいた。
その晩、明子は布団に入る前に、再度猫のことを思い出していた。あの猫のように、もっと自由に生きたいと思う自分がいて、気づけば涙がこぼれていた。「何をそんなに悩んでいるのだろう」と思いながら、明子は自分が抱える漠然とした不安にやがて向き直ることにした。
次の日、学校で思い切ってあの男子生徒に話しかけた。「本、好きなの?」と。彼は驚いたように顔をあげ、柔らかい笑みを浮かべた。「うん、特にミステリーが好きだよ」。その会話がきっかけで、明子の心は少し軽くなった。友達との距離感も次第に縮まっていき、日常の悩みも少しずつ和らいでいく。
日々の中で見つけた小さな幸せ、猫や友達との交流。そんな日常の小さな瞬間があって、自分自身を大切にすることを学んだ。明子は今、自分止まりの小さな世界ではなく、広い世界へと心を開いていく準備ができていた。日常の瞬間が、大きな一歩に変わることを信じながら。