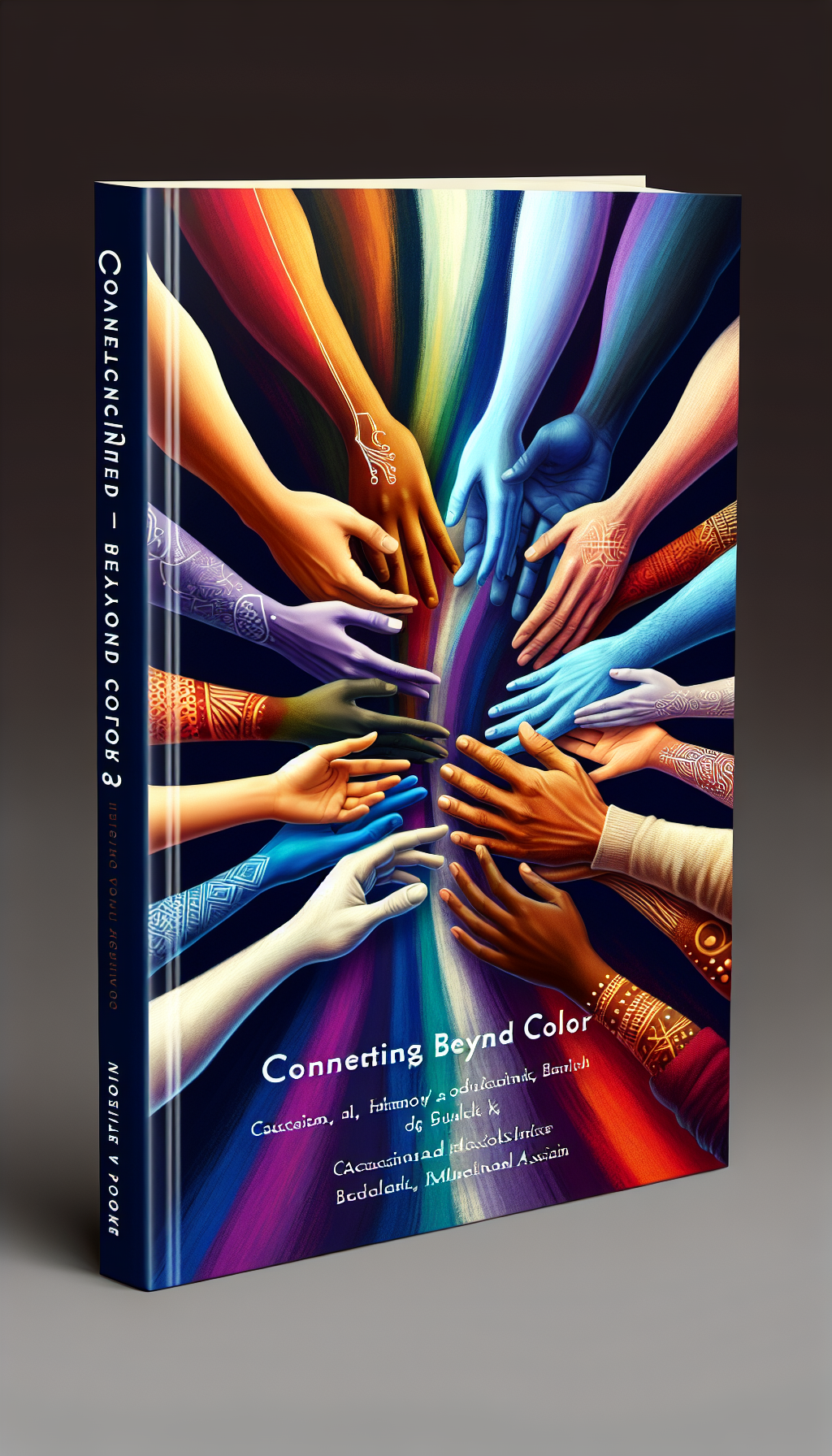川辺の約束
夏休みの終わりが近づくある日、17歳の拓海は、友人の健二と一緒に、地元の川辺でカヌーを漕ぐことに決めた。二人は幼少期からの親友で、毎年のようにこの川で遊んできた。この夏の思い出を作るために、特別な冒険をしようと考えていた。
朝早く、まだ肌寒い空気の中、二人はカヌーを引きずりながら川に向かった。カヌーに乗り込むと、健二は前に座り、拓海は後ろに構えて漕ぎ始めた。漕ぎ出すと、涼しい風が頬を撫で、心地よい緊張感が世界を包み込む。少しずつ流れが速くなり、二人は興奮しながら調子を合わせて漕ぎ続けた。
「今日はどこまで行く?」と健二が尋ねる。「あの小さな滝まで行こうぜ!それを越えたら、まだ誰も見たことのない場所に行けるかも!」拓海は地図を見ながら答える。健二は自信に満ちた笑顔を浮かべ、気持ちが高揚していくのを感じた。
小さな滝にたどり着くと、二人は一瞬躊躇した。滝の水は激しく流れ落ち、音が大きかった。だが、拓海は「行こう!」と叫び、健二もそれに続いて、二人は一体となってカヌーを滝に進ませた。水しぶきが周囲に舞い、心が弾むような瞬間だった。
カヌーは無事に滝を越えた。しかし、そこには彼らが予想もしなかった光景が広がっていた。幾重にも重なる緑の木々、澄んだ水の中を泳ぐ魚、そして小さな島にたたずむ古びた石の小屋。拓海は感動しながら、「わあ、すごい!」と声を上げた。
彼らはカヌーを岸に止め、島に上陸することにした。小屋の周りには、誰かが植えたのか色とりどりの花が咲き乱れていた。健二が「ここはまるで別世界だな」と呟いた。拓海はそれを聞いて、自分たちが今まさに青春の真っ只中にいることを実感した。
小屋の中に入ると、古びた家具が残っていた。本棚には埃をかぶった古い本が何冊か並び、周囲にはかつての住人の痕跡がちらほらと残っていた。二人はその空間を探索し、互いに思い出話をしながら、心の中にある不安を語り合った。
拓海は最近の悩みについて話し始めた。「進路のこと、すごく悩んでる。お父さんは医者になれって言うけど、実は絵を描くのが好きなんだ。」健二は彼の言葉を静かに聞き、しばらく考え込んだ。「俺も似たようなもんだよ。親には進学を期待されてるけど、本当はもっと自由にやりたいんだ。」
その瞬間、二人は共鳴するようにお互いの目を見つめ合った。彼らの心の内にある葛藤や希望が、青春のひとつの側面として凝縮されていた。拓海は「今、こうやってここにいることが大事だと思う。何があっても、友達と一緒にいることがさ。」と言った。
日が傾き始め、オレンジ色の光が川面を照らした。二人はしばらく小屋の中で過ごしながら、これからの未来について語り合い続ける。言葉にすることで少しずつ不安が和らいでいくのを感じていた。
夕暮れになり、帰る時間が迫っていた。二人はカヌーに戻り、漕ぎ始める。帰り道、流れに身を任せながら、心の中には新たな決意が芽生えていた。彼らは互いに理解し合うことで、自分たちの未来に希望を見出していた。
拓海はいつの間にか、「何があっても、俺たちなら乗り越えられる」と思うようになっていた。そして、健二とともに過ごしたこの一日は、二人の絆をさらに強める特別な思い出として、胸の中に刻まれていった。
帰り着く頃には、すっかり夕闇が迫っていたが、心の中には温かな明かりが灯っていた。彼らはそれぞれの未来に向けて、それでも一緒にいるという強い絆を持ち続けることを誓い合った。