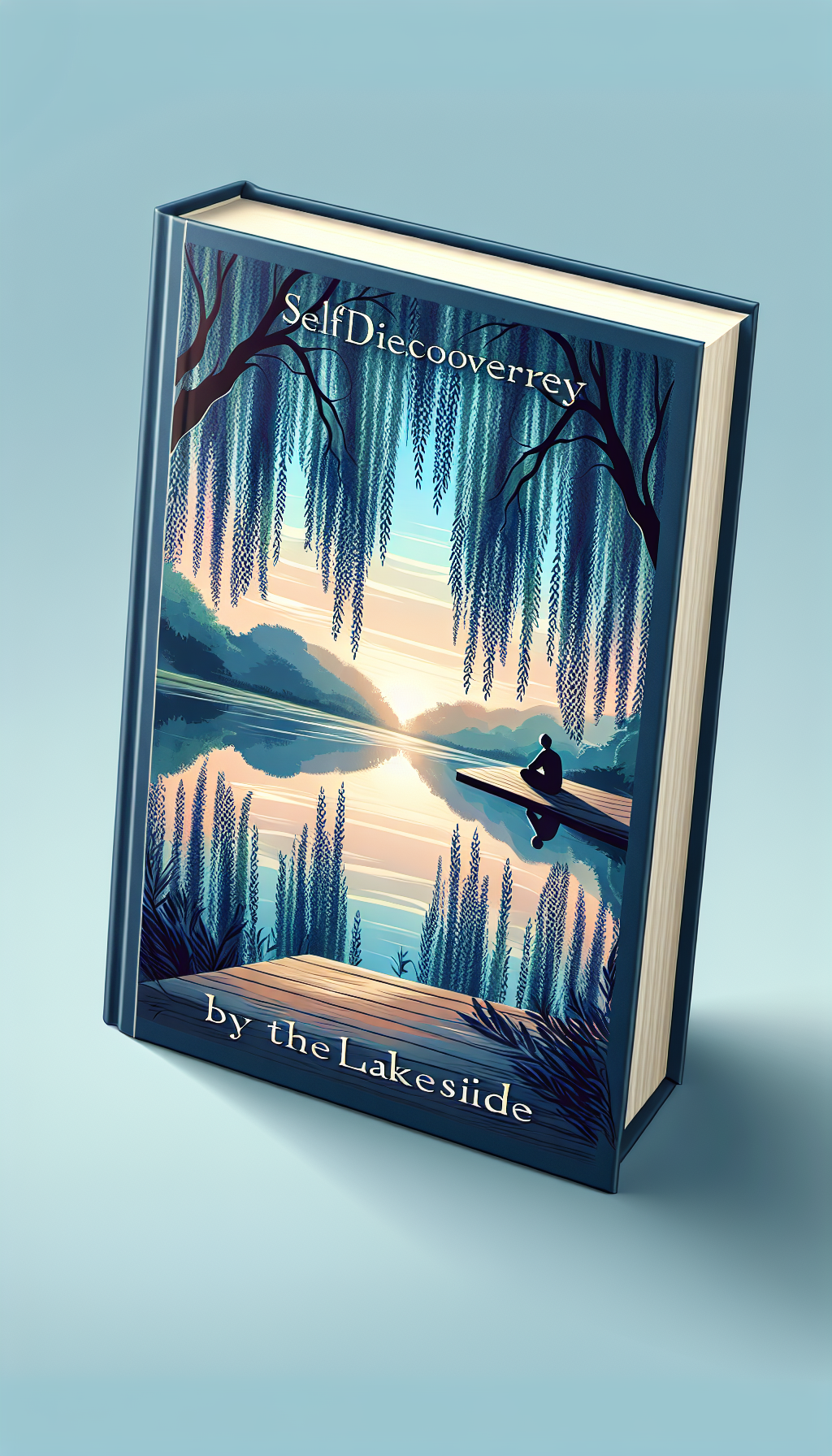絆の温もり
私の家族は、いつも賑やかだった。子供のころ、朝の食卓は笑い声と争い声で賑わっていた。父の大きな声で始まり、母の優しい声で締めくくられる日常。私は三人兄妹の末っ子で、兄たちと母の間を走り回る日々が続いた。
兄の一人、和彦は優秀な男子校に通っていた。彼は勉強熱心で、成績は常にトップクラス。ある日、彼が合格した大学の話を聞いたとき、私は素直に口に出せなかった。「羨ましい」と思う反面、そんな彼に振り向いてもらえない自分を感じていた。兄のプレッシャーのようなものが、私の心を重くしていたのだ。大人になったら、兄のように成績を残すという期待が、私にもかかっていた。
もう一人の兄、健二は反対に自由奔放だった。彼は夢を追いかけることが全てだと信じ、大学には進まなかった。彼はバンドを組んで、ライブハウスで演奏することが青春の全てだと思っていた。私は彼の情熱に魅了されたが、同時に心配でもあった。続けていくうちに、どうなるのだろう? そんな思いは、頭の片隅でいつもぐるぐる回っていた。
母はいつも私たちの間を取り持ち、時には私の行動に泣いて、時には兄たちに叱責をしていた。母の愛情は、私たちを一つにする強力な絆のようなもので、普段はそこには気づけなかったけれど、私たちが困難に直面すると、それがどれほど大切なものであったかを思い知らされた。
私が高校に進学したころ、穏やかな日常は徐々に変わり始めた。和彦が大学に進み、周囲の期待が彼にのしかかっていたのだ。いつもは明るい兄が、次第に暗い影を落としていくのを見て、私は心が痛んだ。健二は、自分のバンドが全然成功しないことに苛立ち、家での居心地が悪くなって、ますます出奔していった。
そんな中、私自身も高校生活のプレッシャーを感じ始めていた。自分が兄たちのようにできるのか、期待に応えられるのか、それともただ目立たない存在で終わってしまうのか。毎日が不安でいっぱいだった。
ある晩、私は家族のために夕ご飯を作ることに決めた。腕に自信はなかったが、母がいつも私たちのために頑張ってくれるのだから、私も何かできることはあるはずだと思った。買い物をして、レシピを見ながら普段の料理を模写するようにした。料理をしながら、昔の思い出が次々と浮かんできた。兄たちが小さかった頃、私たちが一緒に作ったお菓子、母との料理教室、父の笑顔が満ちた食卓。
夕飯の時間、和彦も健二も久しぶりに家に帰ってきた。互いに会話することもままならない空気が流れていたが、私の作った料理の香りがその空気を和らげた。思い切って、食卓に出した料理を食べてもらった。和彦が「美味しい」と一言つぶやいた瞬間、家の中に温かい空気が戻ってきた。健二も笑いながら「お前、やるな」と言ってくれた。
無言だった父も顔をほころばせて、皆でテーブルを囲むと、まるで時間が巻き戻されたかのように、笑い声が再び響いていた。和彦の成功や健二の自由、そんなものは一時的なもので、家族の絆は決して変わらないということを、私はその瞬間感じ取った。
時間は流れ、兄たちもそれぞれの道を進んでいった。ただ、あの晩の食卓の温もりがあったからこそ、私たちは今も家族としての絆を大切にしながら生きている。どんなに成績が良くても、どんなに夢を追いかけても、家族の笑顔を忘れずにいることが一番大切なことだと、今改めて思う。私たちの物語はこれからも続く。