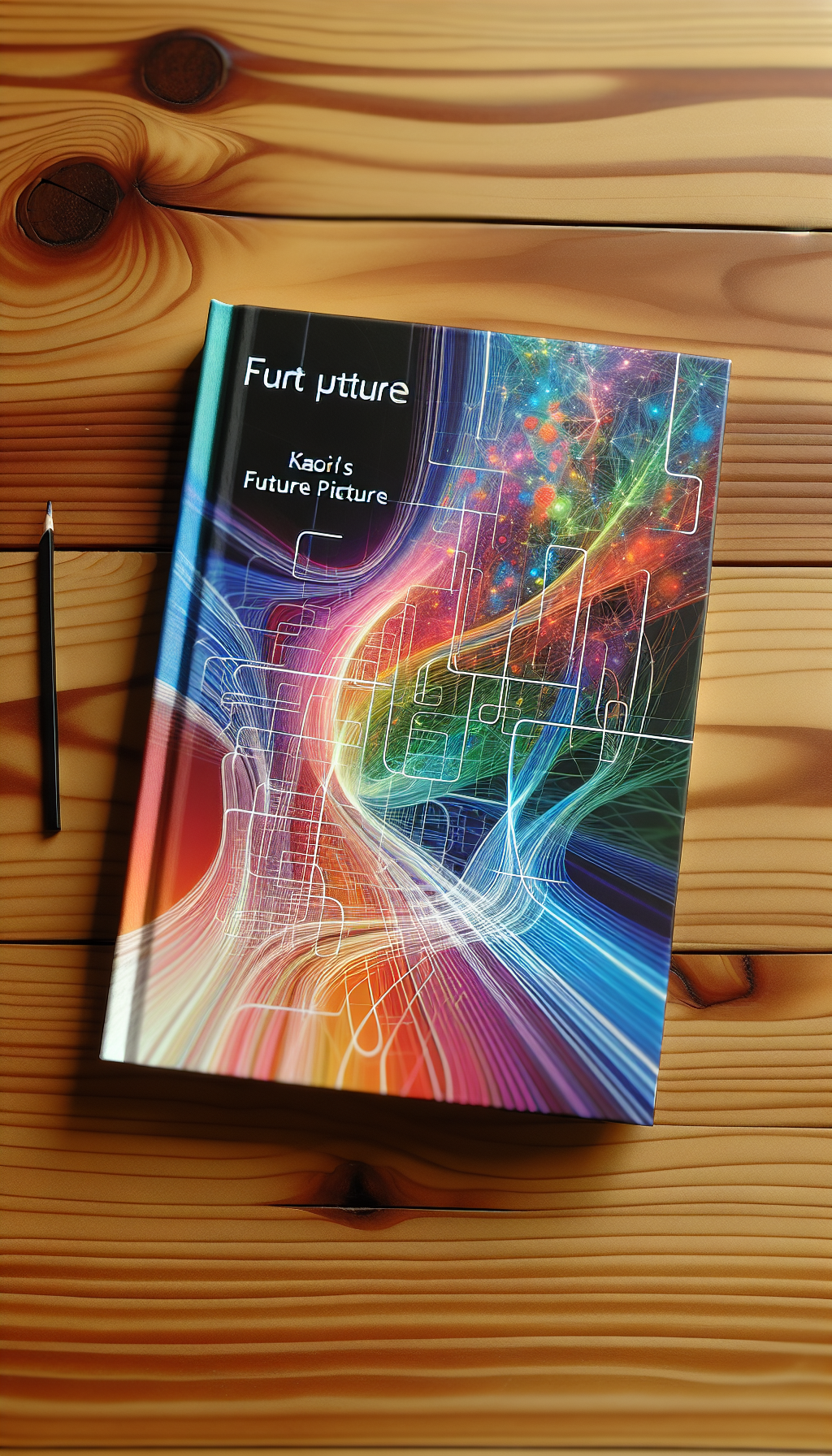秋の風に想い出
ある秋の日、葉の落ちる音が風に紛れる中、主人公の玲子は自宅近くの公園を散歩していた。公園のベンチに座り、一冊の古い本を開いた。これが彼女の日課であり、読者であることが玲子の日常を形作っていた。
玲子は30代半ばの独身女性で、出版社で編集者として働いている。毎日長時間をオフィスで過ごすが、その分、週末はゆっくりと自分の時間を楽しむのが彼女の息抜きであった。本を読むことはもちろん、散歩やカフェ巡りも好きだ。一日の疲れをリセットするため、公園のベンチに座る時間は特に大切にしていた。
その日も、彼女はゆっくりとページをめくり、秋の暖かな日差しを浴びながら文学の世界に浸っていた。ふと、何かが視界の端に映った。見上げると、公園の入り口に一人の中年男性が立っていた。その男はぼんやりと空を見上げており、手には古いカメラを持っていた。
男はいつしか玲子の方にゆっくりと近づいてきた。そして、静かにベンチの端に腰を下ろした。玲子は一瞬驚いたが、その男性がどこか物静かで親しみやすい雰囲気を纏っていることに気付いた。
「いい天気ですね。」男がつぶやいた。
玲子は本から顔を上げ、にこりと微笑んだ。「ええ、本当に。」
それから二人の会話が自然と始まった。彼の名前は健二、と話す中で彼は元新聞記者で、現在は写真家として活動していることを玲子に告げた。話が弾む中で、玲子はいつの間にか自分が少しずつ心を開いているのを感じた。
その後、玲子と健二は何度も公園で会うようになった。次の週末も、二人は公園のベンチで静かにお茶を飲みながら、互いの趣味や仕事の話をし合った。玲子は自分がこれほどに気軽に話せる相手を見つけたことに驚きつつも、心の中に小さな安堵感を感じていた。
ある日、健二は玲子に「写真を撮らせてもらってもいいですか?」と尋ねた。
玲子は少し驚いたが、彼の真剣な眼差しを見ると断る理由もなく、了承した。健二はカメラを構え、シャッターを切った。
「こんな風に、日常の一瞬を捉えるのが好きなんです。」健二は言った。
玲子は彼の言葉に共感を覚えた。彼女自身も、何気ない日常の中に美しさを感じる瞬間があると常々思っていたからだ。
秋も深まり、寒さが増す中、玲子と健二の友情はさらに深まっていった。玲子は毎日が少しだけ特別なものに変わったような気がしていた。健二と会話をするたびに、新しい発見や感動を感じることができたからだ。
しかし、ある日、健二は突然公園に来なくなった。玲子は心配し、次の日もその次の日も公園に足を運んだが、健二の姿はなかった。その不在が続く中、玲子は心の中にぽっかりと穴が開いたような感覚に襲われた。
一週間が過ぎたある日、玲子は意を決して健二の住む街を訪れることにした。健二の住所は以前の会話の中でうっかりと漏らしたことがあった。玲子はその手がかりを頼りに健二の家を見つけ、勇気を出してドアをノックした。
ドアを開けたのは健二の若い娘だった。玲子は健二のことを伝え、娘は驚いた表情を見せたが、すぐに心を開き、彼が今どうしているのかを教えてくれた。健二は体調を崩し、今は病院に入院しているとのことだった。
玲子はすぐに病院に向かった。そこには、以前の健二とは違って、病に侵され衰弱した姿の彼がいた。しかし、それでも彼の眼差しは温かく、玲子を見ると微笑んだ。
「すみません、心配かけましたね。」健二がかすかに言った。
玲子は涙をこぼしそうになりながら、そっと健二の手を握った。「大丈夫です。話に来ただけです。」
それから、玲子は毎日のように健二のもとを訪れ、二人の会話は再び続いた。健二の病状が改善することはなかったが、日常に戻った彼らの小さな幸せは、確かにそこにあった。
健二が旅立つ日が来ても、玲子は彼との思い出とともに日常を過ごし続けた。その思い出は、季節が巡るたびに色を増し、玲子の日々に新たな意味を与え続けた。
秋の風が再び葉を揺らす頃、玲子は公園のベンチに座り、あの日のように本を開いた。そして、空を見上げ、静かに微笑んだ。彼女の日常の中には、健二との出会いが永遠に刻まれていた。