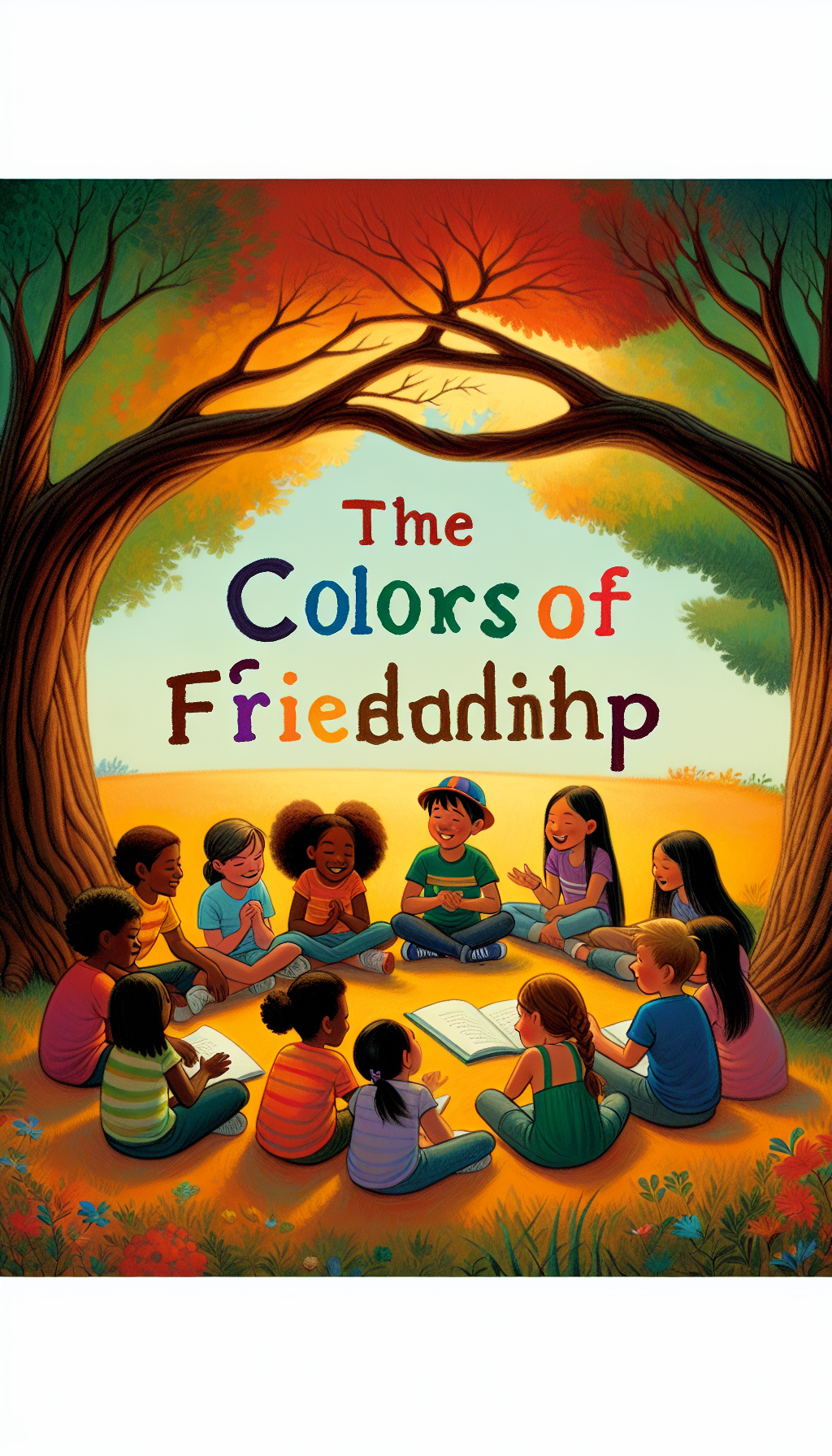姉との絆
私は初めて生を受ける瞬間から、姉とは特別な絆で結ばれていた。彼女は私より3歳年上で、私の初めての友達であり、人生の最初のガイドでもあった。私たちの家は山梨県の小さな町にあり、四方を自然に囲まれていた。父は地元の高校で教師をし、母は自宅で陶芸教室を開く芸術家だった。静かで穏やかな家庭の中で、私たち姉妹は育った。
小さい頃、私はいつも姉の後ろをついて回った。彼女はいつも私の手を引き、森の中や川辺へと連れて行ってくれた。姉は冒険好きで、私を引っ張って未知の世界に導いた。私はその時々の珍しい植物や昆虫を手に取り、姉の説明を聞くのが大好きだった。彼女は知識が豊富で、たとえそれが蝶の羽ばたき一つであっても、魅力的な物語に変えてしまった。
しかし、私は次第に姉という存在がどれほど大きいのかを理解し始めた。小学3年生のとき、姉は中学校に進学し、新しい友達や部活動に夢中になった。私はそれを見て、少し寂しさを感じたが、それ以上に誇らしい気持ちでいっぱいだった。彼女は私にとっての英雄だったのだから。
中学生になると、私も忙しくなり、姉との時間が少しずつ減っていった。それでも、家族の夕食時にはお互いの一日の出来事を共有したり、夜には姉の部屋で一緒に宿題をしたりしていた。その時々に姉が見せる笑顔や、触れ合う手のぬくもりが、私の心を安定させてくれた。
やがて、姉は高校生になり、さらに多忙な日々を送るようになった。彼女は文武両道の生徒で、成績は抜群、バスケットボール部のキャプテンとして毎日練習に明け暮れていた。それでも、私の悩みや心配事を聞いてくれる時間を見つけてくれた。思春期特有の不安定な感情や、友人関係のトラブルも、姉にだけは打ち明けることができた。その度に彼女は、私を励まし、適切なアドバイスをくれた。
高校を卒業して大学に進学するとき、姉は東京に引っ越した。離れ離れになるのが初めてだったため、私たち姉妹には大きな不安がつきまとった。しかし、毎晩の電話や、休日にお互い行き来することで、その距離を感じさせないように努めた。姉が社会人になり、私は高校生としての生活が始まると、ますますお互いの時間が取れなくなった。それでも、心の中ではいつも彼女の存在が大きく、共に成長している感覚を味わっていた。
大学に進学するとき、私は姉の影響を強く受け、彼女と同じ東京の大学に入学することを決めた。親近感と共に、都会の喧騒に飲み込まれないための安心感が欲しかった。再び同じ町、同じ空の下で生活する中で、私たちの絆はますます深まっていった。私は文学部に進学し、小説や詩の創作に打ち込んだ。姉は既に社会人としてバリバリ働いており、マンションも自分名義で持っていた。それでも、休日には一緒にカフェで時間を過ごし、お互いの夢や悩みを語り合った。
姉は私が創作活動に打ち込む姿を見ると、常に励ましの言葉をかけてくれた。彼女自身も仕事の中でクリエイティブな側面を活かす場面が多く、その経験から適切なアドバイスをくれるのだった。「何事も諦めずに続けることが大事だよ、ミホ」と、彼女はいつも言っていた。その言葉が私の心の中で大きな支えとなった。
しかし、私たちの絆が試される出来事が起きた。大学3年生の夏、突然の届け物である、家族全員が病院に呼ばれた。父の体調が急変し、余命が短いと知らされたのだ。私と姉は、父の最期の時間をどう過ごすかについて深く考え、議論した。悲しみに押しつぶされそうな中で、姉は冷静さを保ち、私を導いてくれた。
父の最期の瞬間、家族全員が集まり、手を握り合っていた。涙に濡れた瞳で見つめる中、彼の最後の言葉が胸に響いた。「お前たち二人、いつまでも仲良く支え合って生きていけよ」。その言葉を胸に、私たち姉妹は新たな一歩を踏み出した。
社会人としての生活が始まると、私たち姉妹の生活はますます忙しくなった。それでも、お互いの存在がどれほど貴重であるかを再確認する時間を大切にした。しばしば二人で旅行に出かけ、自然の中でリフレッシュすることもあった。その一方で、都会の喧騒から身を引いて、静かな時間を共有することもあった。
ある日、私が初めての小説を出版することが決まったとき、真っ先に姉に報告した。彼女は感動の涙を流し、「おめでとう、ミホ!これからもずっと応援するよ」と言ってくれた。その瞬間、私は姉が私の人生においてどれほど大切な存在かを再確認した。
私たち姉妹の物語は、ここで終わりではない。この先も互いに支え合い、新たな挑戦や困難を乗り越えていくだろう。そして、父の言葉を胸に、一歩ずつ前進し続けることを誓っている。どんなに時が経っても、私たちの絆は決して途切れることはない。