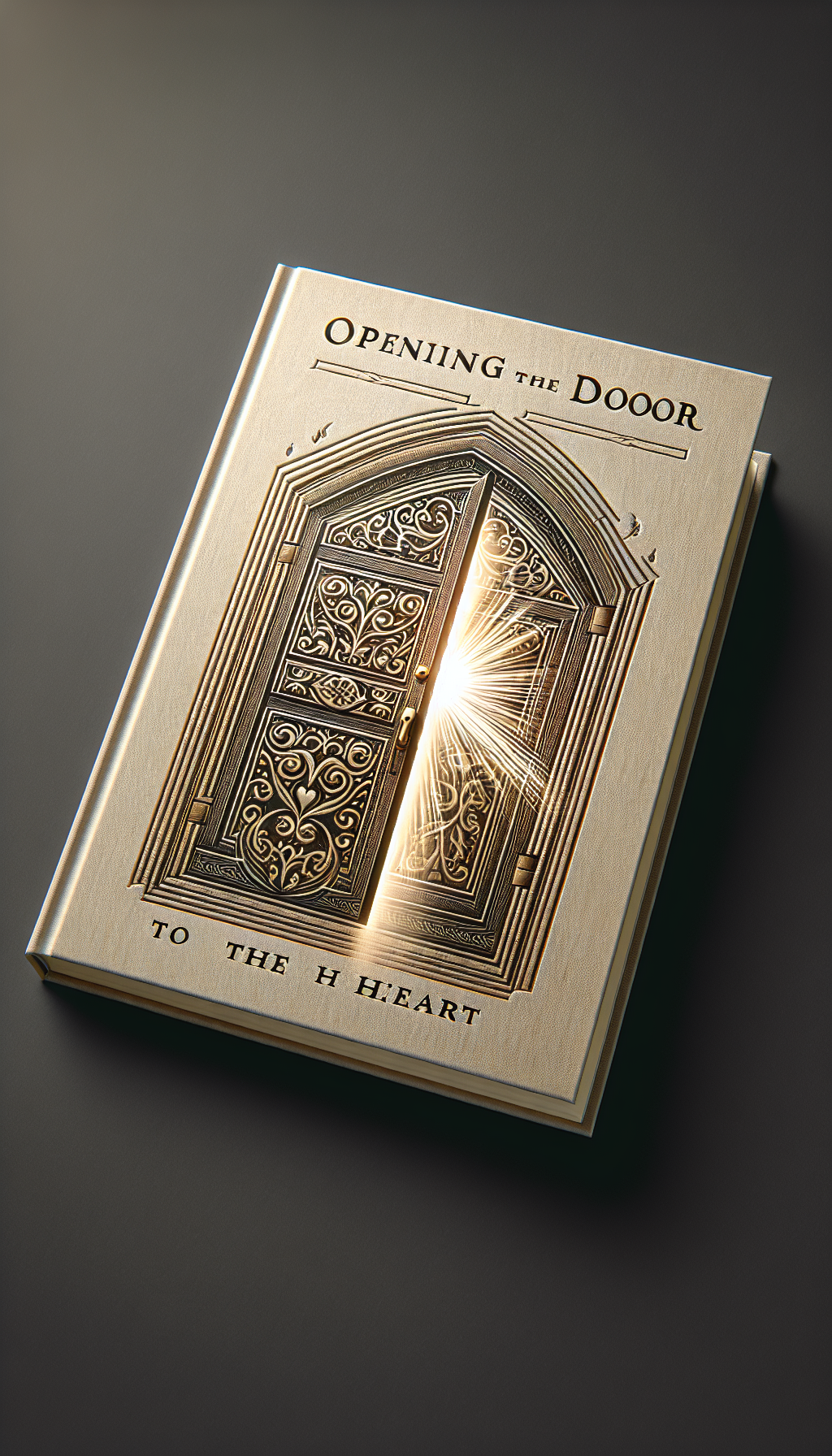幸せの糸
春の陽射しが窓から差し込む朝、久美子はキャベツを切る手を止めて、その光景にしばし見入った。正確に刻まれた光の線が、年季が入った木の床に踊る。彼女にはいつもその瞬間が特別に思えた。時間が静かに流れる瞬間、その刹那に感じる幸福感。子供たちはまだ眠っていて、夫の康夫は新聞に目を通しながら思索にふけっているだろう。
「パチン!」と音がして、久美子は気づいた。誠一が目覚め、顔を擦りながらやってきたのだ。彼は八歳だが、その顔には既に日々の重みが感じられる。学校生活が彼にとってはそれほど楽しいものではない。
「おはよう、ママ。」 誠一は少しぼんやりとした声で言った。久美子は息子の頭を撫でながら、にこりと微笑んだ。
「おはよう、誠一。早く朝ごはんを食べなさいね。今日も元気に学校に行ってね。」
久美子はキャベツを続きを切りながら、誠一のためにお米をよそい、サラダの盛り付けを始めた。彼女の手際よい動きには、家庭のために費やされた時間と努力が滲み出ている。一方で康夫は、毎朝の習慣を変わることなく続けていた。新聞の裏表を一通り読み、カップに注がれたコーヒーをゆっくりと味わう。その姿は、家族にとっても安心感を与えていた。
朝の光景が徐々に活気づいてくる。七歳の美咲が階段を駆け下りてくる音がして、誠一は妹の顔を見ると憂いが和らいだ。美咲は元気で明るく、その存在自体が家族全体に活力を与えている。
「おはよう、美咲ちゃん。今日はどんな夢見たの?」久美子は妹にも聞いてみた。
「えっとね、ママ!」美咲の瞳はキラキラと輝き、「大きな虹を見たの! おっきくて、七つの色が全部見えたの!」
「それは素敵ね。虹を見るのは幸運を運ぶんだよ。」久美子はそう言って、美咲にも朝食を用意した。
一家が揃って朝食を取る時、食卓には何とも言えない温かさが漂っていた。康夫はいつも黙々と食べ進みながら、実は家族一人一人の様子を察することができた。彼の観察力は、長年共にした妻と子供たちの成長を見守るためのものだった。
「さて、皆さん、今日も一日頑張ろうね。」久美子は締めくくるように言った。
その後、それぞれが忙しい日常に戻る。誠一と美咲はランドセルを背負い、元気よく家を出た。久美子は、家の片付けや買い物、パートの仕事へと向かう。康夫も直ぐに出勤の用意をするが、ふとその前に、ベランダから隣近所の風景を眺める。街は穏やかで、それぞれの暮らしが静かに流れている。
夕方、子供たちが帰宅すると家の中は再び賑わう。誠一が見せるしおれた顔に、美咲が無邪気な笑顔で元気付けようとする姿が微笑ましい。久美子は夕食の準備をしながら、その光景に目をやることが多かった。
「ねえ、ママ。今日学校でね、新しい友達ができたの。」誠一が珍しく話し始めると、久美子は耳を傾けた。
「それは良かったわ、誠一。どんな子?」久美子の問いかけに、誠一は少し照れたように答えた。
「すごく絵が上手な子で、僕に絵の描き方を教えてくれたんだ。」
その話に美咲も興味津々で耳を傾け、誠一は自分の小さな成長を家族に共有する喜びをかみしめていた。康夫も、疲れが見える顔に優しい笑みを浮かべ、息子の話を聞く。この小さな家庭の一瞬一瞬が、一日の中で最も価値ある時間と感じられるのだった。
夜が更け、子供たちが眠りについた頃、久美子は自分の寝室で康夫と少しの間会話を交わす。お互いの一日を振り返り、小さな喜びや悩みを共有する。この日常の積み重ねが、二人にとっての生きる原動力となっている。
静かな夜、久美子は窓の外に目を向ける。月明かりが再び床に影を落とし、その光景を見つめると心が安らぐ。これが彼女の日常、だがその中には無数の瞬間が輝いている。それは家族の温もり、子供たちの成長、夫との会話という小さな幸せだ。
片隅の光。それは、彼女がいつも追い求める存在であり、その一瞬一瞬が彼女の人生の絆となっている。家族との共感が、日常の中で最も大切な光を見出す鍵であることを、久美子は改めて感じたのだった。