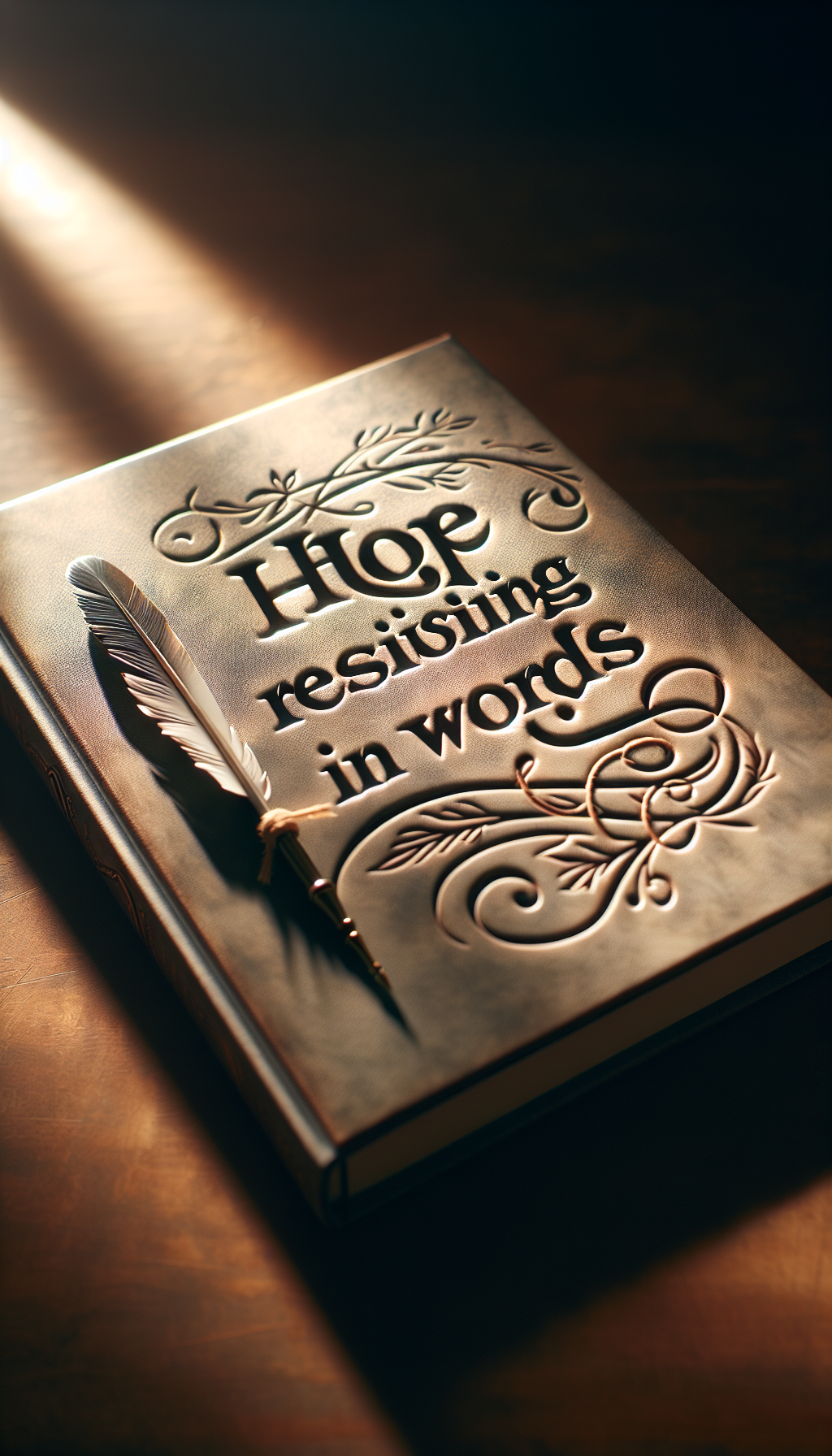秋風と約束
夏休みも終わりを迎え、学校が再開した。窓の外は青い空が広がり、秋の訪れを感じさせる雲がゆったりと漂っていた。高校2年生の智也は、新学期初日、何か特別なことが待っている予感を胸に抱きながら教室に足を踏み入れた。
クラスメイトたちの声が響く中、智也は席についてぼんやりと窓の外を眺めていた。ふと、視線が隣の席に移る。そこに座っているのは、幼馴染の芽衣だった。彼女は明るい笑顔を浮かべて、友達と楽しそうに話している。智也は少し自分が置いてけぼりにされている気分になり、内心モヤモヤした。
学校が始まってから数日が経ち、智也は芽衣と同じクラブ活動に参加することになった。文化祭の準備を進める放送部で、智也は音響担当、芽衣はスクリプト担当に割り当てられた。彼女の元気な声と明るい性格がチームの雰囲気を明るくしていた。しかし、智也はなぜか心のどこかに引っかかるものを感じていた。
文化祭の準備が進む中、智也は芽衣のことが気になって仕方がなかった。確かに幼馴染であり、互いに知っていることも多い。しかし、彼女が自分のことをどう思っているのか、特別な感情を抱いているのか、自信が持てなかった。ある晩、文化祭の練習が終わり、智也は芽衣を呼び止めた。
「芽衣、ちょっと話があるんだけど…」
芽衣は首をかしげて振り返った。「何?智也。」
「この文化祭が終わったら、少しだけど、どう思ってるか話し合わないか?」智也は緊張しながら言った。
「うん、いいよ!何か大事なことがあるの?」芽衣は目を輝かせて答えた。その表情に心が少しほぐれた。
文化祭は無事に終わり、大盛況のうちに幕を閉じた。その後、智也は芽衣を近くの公園に誘った。夕暮れ時の公園はほのかに温かい風が吹き、秋の気配が漂っていた。智也は気持ちを整理しながら、芽衣に話しかけた。
「芽衣、最近ずっと考えてたことがあるんだ。俺たち、幼馴染としてずっと一緒にいたけど、もしかして…もう少し近くにいたいって思うようになってきた。」
芽衣は驚いたように目を丸くしていた。「智也、私も同じことを考えてたの。でも、どうしてそう思うようになったの?」
智也は、自分の心の中にあった不安や期待をすべて吐き出すことに決めた。「だって、芽衣のことがどんどん好きになってるのに、それを言えなかった。もし、この関係が壊れたらどうしようって思うと、怖くて…」
芽衣は静かに智也の目を見つめた。「その気持ち、私も同じだよ。智也との時間がすごく大事で、その思いを伝えられなかった。私もやっぱり、智也のことが好きなの。」
その言葉を聞いた瞬間、智也の胸が高鳴った。彼は芽衣の手を優しく握りしめた。「これからもっと、お互いのことを知っていこう。少しずつ、距離を縮めていけたらいいな。」
芽衣も力強く頷いた。その瞬間、彼らの心の距離が一気に縮まった気がした。夕焼けが公園を赤く染める中、智也と芽衣はそのまましばらく何も言わず、手を繋いでいた。
その後も二人は、お互いに支え合いながら高校生活を過ごしていった。文化祭の思い出や友達との楽しい時間を共有し、少しずつ成長していく中で、お互いの絆は強固なものになっていった。
数年後、大人になった彼らは、互いの思い出を振り返りながら確かな未来を見据えていた。青春の日々は常に変わっていくけれど、あの公園で交わした約束は、彼らの心の中で永遠に輝いているのだった。