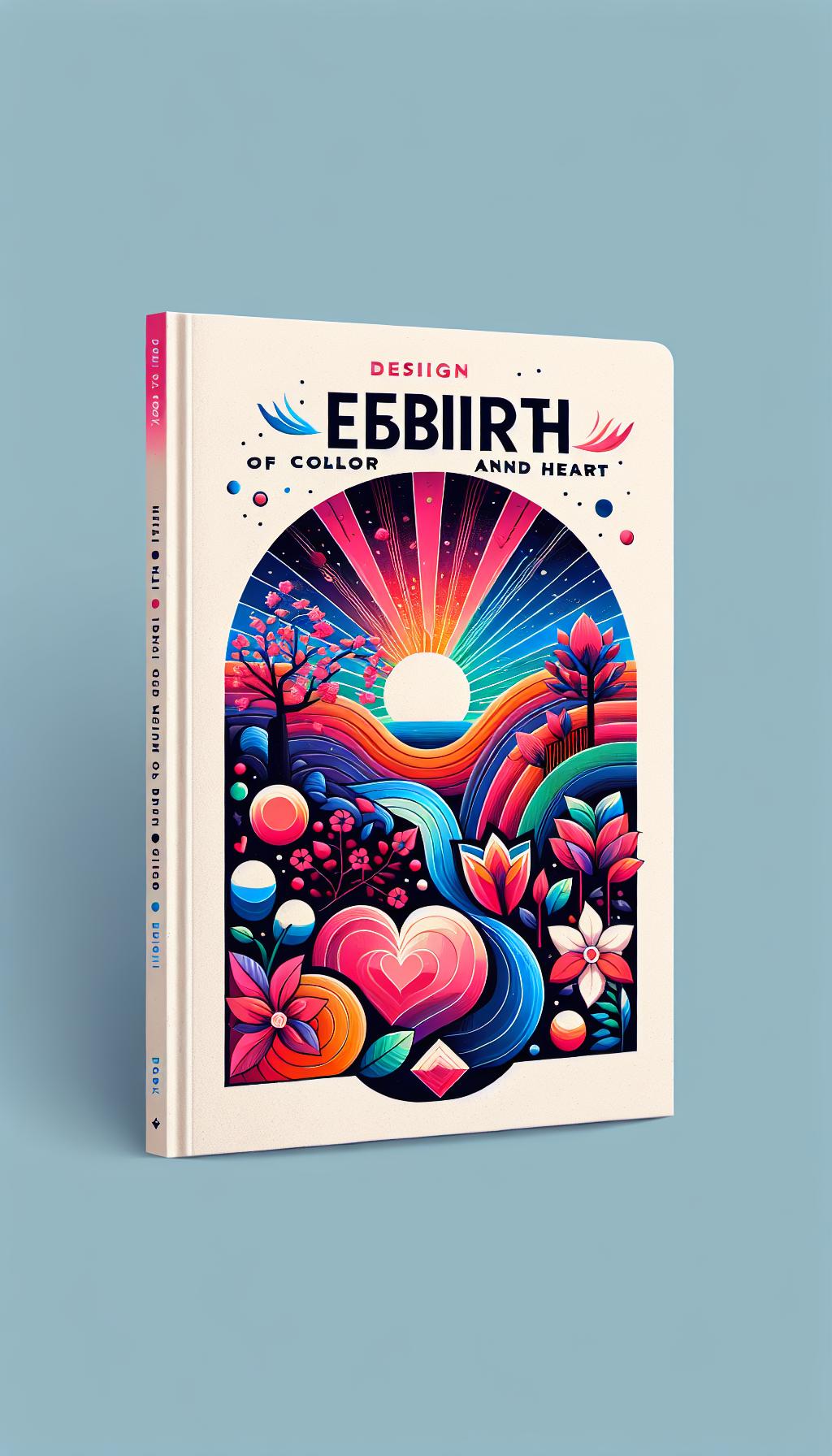美しさを共有したい
晴れた休日の午後、私は塩田美術館の小さな展示室に立っていた。色とりどりの絵画が並ぶ中、一際目を引く一枚の絵があった。それは、パリのモンマルトルに佇むカフェの情景を描いた、水彩画だった。淡いピンクやブルーで描かれたその風景は、異国の地にいるような気分にさせてくれる。
この絵の隣には、アーティストの名前と簡単な紹介が書かれていた。目を通すと、女性画家で、その名は中野麗華(なかのれいか)だという。彼女は戦後の混乱期に生まれ、日本の美術界で無名のまま亡くなったという。展示されている絵画は生前の作品で、彼女の兄・中野健一という人物によって大事に保管されていたらしい。
その隣に、「中野麗華展」と書かれたタイトルボードがあり、少ないながらも彼女の作品が並んでいる。春の草原、冬の夜空、そして雨に濡れた街角など、いずれもどこか懐かしさを感じさせる作品ばかりだ。だが、その中でも一際異彩を放つのが、私が目を奪われたカフェの情景画だった。
展示室を見渡すと、ひとりの白髪混じりの中年男性が立っていた。展示されている絵の一枚一枚を眺めながら、時折深いため息をつく。彼の目はどこか放心しているようにも見える。
「もしかして、この絵に何か特別な思い入れがあるんですか?」
私はその男性に声をかけてみた。彼は驚いた表情で私に振り返ると、ゆっくりと頷いた。
「ええ、この絵を描いたのは僕の妹なんです」
そう言って彼はカフェの絵に向き直り、遠い目をしながら続けた。
「麗華は、僕の人生そのものと言っても過言じゃないんです。彼女は僕より五歳下で、僕にとってはいつだって小さな妹でした。でも、絵の才能は僕なんか到底及ばないほど、素晴らしかった」
彼は麗華が描いた作品のいくつかを指差した。どれもふんわりとした色遣いと、温かみのあるタッチで描かれている。それらの絵からは、彼女の優しい性格が伝わってくるようだった。
「戦後の混乱期、家族を支えるために彼女は絵をあまり描かなくなった。それでも、僕たちは二人で支え合って生きてきたんです。僕が就職してしばらくしてから、やっと彼女もまた絵を描き始めました」
中野健一さんは、麗華の人生について話し続けた。彼女は描くことが大好きだったが、売れない画家として苦労した。その挫折感と戦いながらも、創作する喜びをいつも大切にしていたという。
「麗華がパリに行ったのは、1972年のことでした。当時、彼女は日常の中で見つけた美しさを描くことに情熱を注いでいました。特にモンマルトルは彼女のお気に入りの場所で、そこで多くの絵を描きました」
彼の話を聞きながら、私はその時代の麗華さんの姿を想像してみた。活気に満ちたモンマルトルの街角で、スケッチブックを手に取り、路傍のカフェで柔らかな笑みを浮かべながら描く彼女。そんな彼女の姿が、まるで目の前に浮かんできた。
「でも、パリから帰国してしばらくして、麗華は病に倒れてしまったんです。脳腫瘍でした。治療を受けましたが、回復の見込みはありませんでした。それでも最後まで、彼女は絵を描き続けたんです」
中野さんの声は震えていた。私はその痛みと悲しみを感じ、胸が締め付けられる思いだった。
「最後の方は、手がうまく動かなくなってしまってね。それでも、麗華は筆を握り続けました。このカフェの絵、実は彼女が最後に完成させた作品なんです。病床で、死ぬ間際に描いたんですよ」
その絵が持つ淡い色彩とやわらかなタッチは、そんな彼女の最期の思いが込められていると思うと、胸にこみ上げてくるものがあった。
「その後、彼女の絵をこの美術館に寄贈しました。彼女のことをもっと多くの人に知ってほしかったからです。もしかしたら、彼女の絵が誰かにとって特別なものになるかもしれない。そんな希望を持って」
結局、私はそのカフェの情景画の前で時間を忘れるほど立ち尽くしていた。中野さんの話を聞いてから、絵の一つ一つがより深く心に刺さるようになった。絵は、ただ視覚的な美しさだけでない。その背後には描き手の思いや人生が込められているということを改めて感じさせられたのだ。
絵画は、描いた人の「美しさを共有したい」という気持ちが詰まったものだ。その気持ちは、時代を超えて人々の心に届く。中野麗華さんの描いたこのカフェの情景は、私にとっても大切な一枚になった。彼女の思いが、この絵を通じて、誰かの心に触れることができる。それが絵画の持つ本当の力なのだと、私は思った。