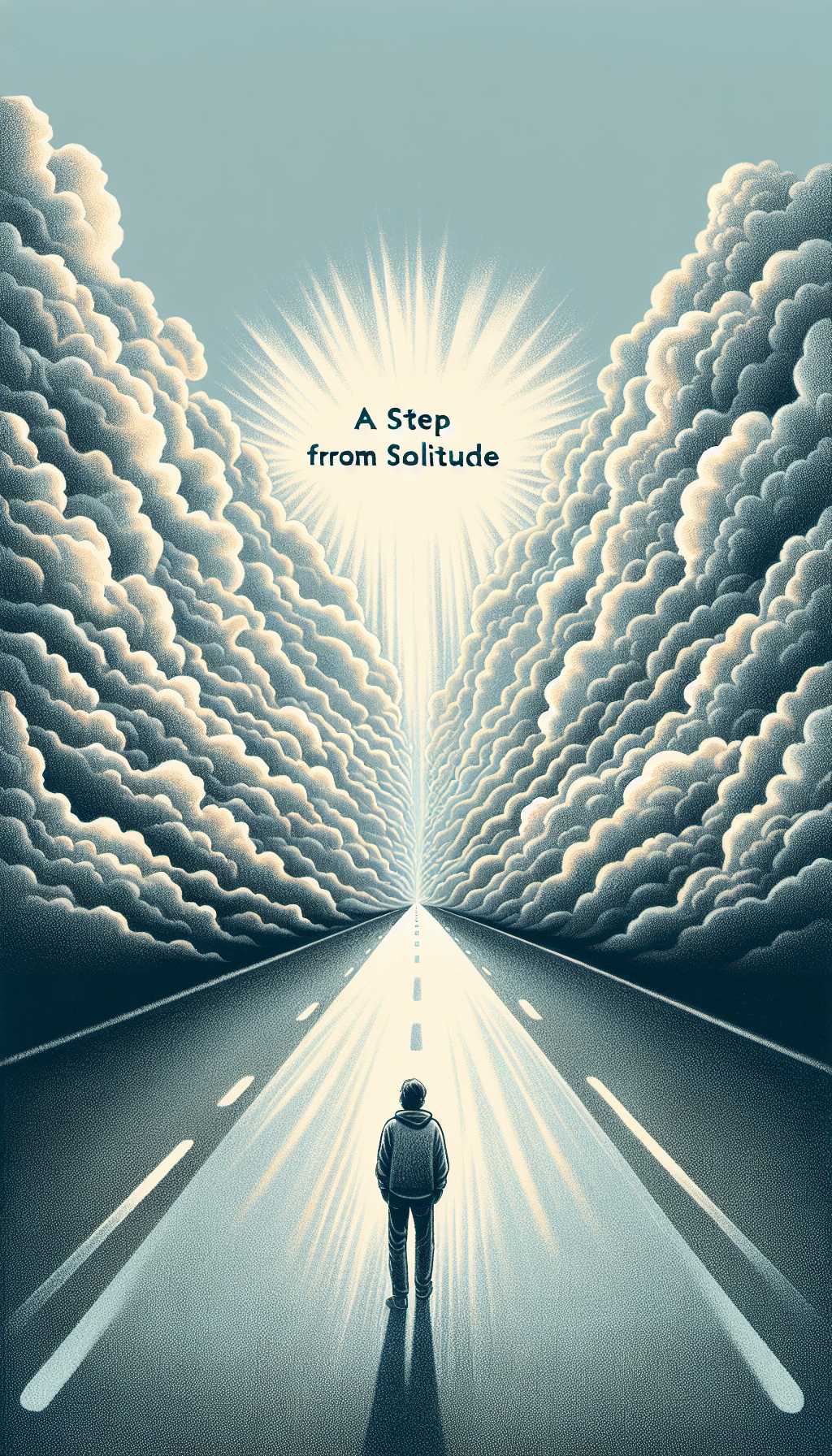風と死の対話
風の強い秋の午後、福田は大学から自宅へ戻る途中、駅近くの公園に立ち寄った。冷たい風が吹き抜け、木々の葉がカサカサと音を立てて揺れていた。どこかで見かけたような顔が、公園のベンチに座っているのに気づいた。歳の頃は五十代半ば、顔には深い皺が刻まれ、疲労が見えた。彼の隣には一冊の本が置かれている。
福田はその場を通り過ぎようとしたが、なんとなく目が離せず、足を止めた。目の前の男は、福田の大学時代の教授であり、故・長谷川だった。彼は以前、福田に特別な興味を持ち、彼の将来に期待を寄せていた。
「教授、久しぶりですね」と福田が声をかけると、長谷川は驚いたように顔を上げた。少し驚いたように目を細め、「おお、福田君か。もう随分経ったな。」と笑顔を見せた。
彼の顔には、死の影が忍び寄っているように見えた。ベンチのそばには、彼の愛用の本が開かれたままに置いてあった。間違いなく、彼はそこで過ごすことを選んでいたのだろう。福田は何かしらの気持ちを抱えながら、長谷川の隣に腰掛けた。
「何を読んでいるんですか?」と尋ねると、長谷川は少しの間、考え込むように目を閉じた後、つぶやいた。「これか。『死にゆく者のための詩』という本だ。」
福田は、そのタイトルに興味を持った。死とは何か、そしてそれを受け入れることがどれほど難しいのかを、長谷川は今、真剣に考えているのだ。彼の眼差しに、何かしらの深い悲しみと安らぎを感じた。
「教授は、死のことをどう思いますか?」福田が尋ねると、長谷川は少し笑った。「死は、甘くも苦いものだ。人生のすべての経験が、最後には消えてしまうと思うと、やり残したことが多いなと感じる。」
彼の言葉には重みがあった。それに続く沈黙が、彼の心の奥深くに潜む思いを映し出しているようだった。
「私の母は、数年前に亡くなった。彼女の最後の日々は辛かった」と福田は言った。「でも、彼女はその瞬間まで生きることを楽しんでいた。死の直前で、少しだけ笑っていたのを覚えている。」
長谷川は黙って頷き、その時の福田の気持ちを理解したように思えた。時間が経つにつれて、彼の顔に浮かぶ微笑みは少しずつ消え、何かを思い悩む表情へと変わっていく。
「私も、いろんな患者を看取ったなぁ」と彼は感慨深く語り始めた。「彼らの最後を見届けるのは、とても大変なことだった。しかし、彼らが最後の瞬間に見せる表情には、何かしらの安らぎがあったのだ。」
「どんなふうに安らぎなんでしょうか?」胸が締め付けられる思いで福田は聞いた。
「生死についての理解や、受け入れることができたときに訪れる一瞬の静けさだ。彼らは、自分の人生を振り返り、終わりを見据えているのだと思う。それは、その人自身のあり方を象徴している。この世界から消えることに、感謝の気持ちがあったとも言える。」
長谷川の言葉は、福田の心に深く響いた。彼自身も、死を意識しなければならない時がやがて来るだろう。それを考えると、恐れや不安が湧き上がる一方で、穏やかな気持ちも生まれてきた。
「教授、もし残された時間を知っていたら、何をしますか?」と福田は問う。
長谷川は長い間考え、静かに言った。「もっと多くの人と、深い会話をしてみたかった。大切な思い出を作り、残したいものを見つけることができれは、その人の生がどれだけ大切かがわかるから。」
福田は、教授の言葉を通じて彼がいかに人生を真剣に生きてきたかを感じた。彼自身も、そのような生き方を模索している途中だった。
「死は終わりではない、ただの変化だと思う。受け入れれば、前に進めるものだ」と長谷川は続け、彼の目には涙が浮かんでいた。
福田はその言葉を噛み締めるように感じ、長谷川がどのように生き、そしてどのように死を迎えようとしているのか、何か特別な思いを抱えながらそこにいるのを感じた。
一時的な沈黙を破り、福田は「今日のこの時間、無駄ではなかったですね」と笑顔を見せると、長谷川も穏やかに微笑み返した。その瞬間、風が再び吹き抜け、枯れ葉が舞い上がった。
それは、彼らの心に新たな気持ちを運んでくるような、さわやかな風だった。