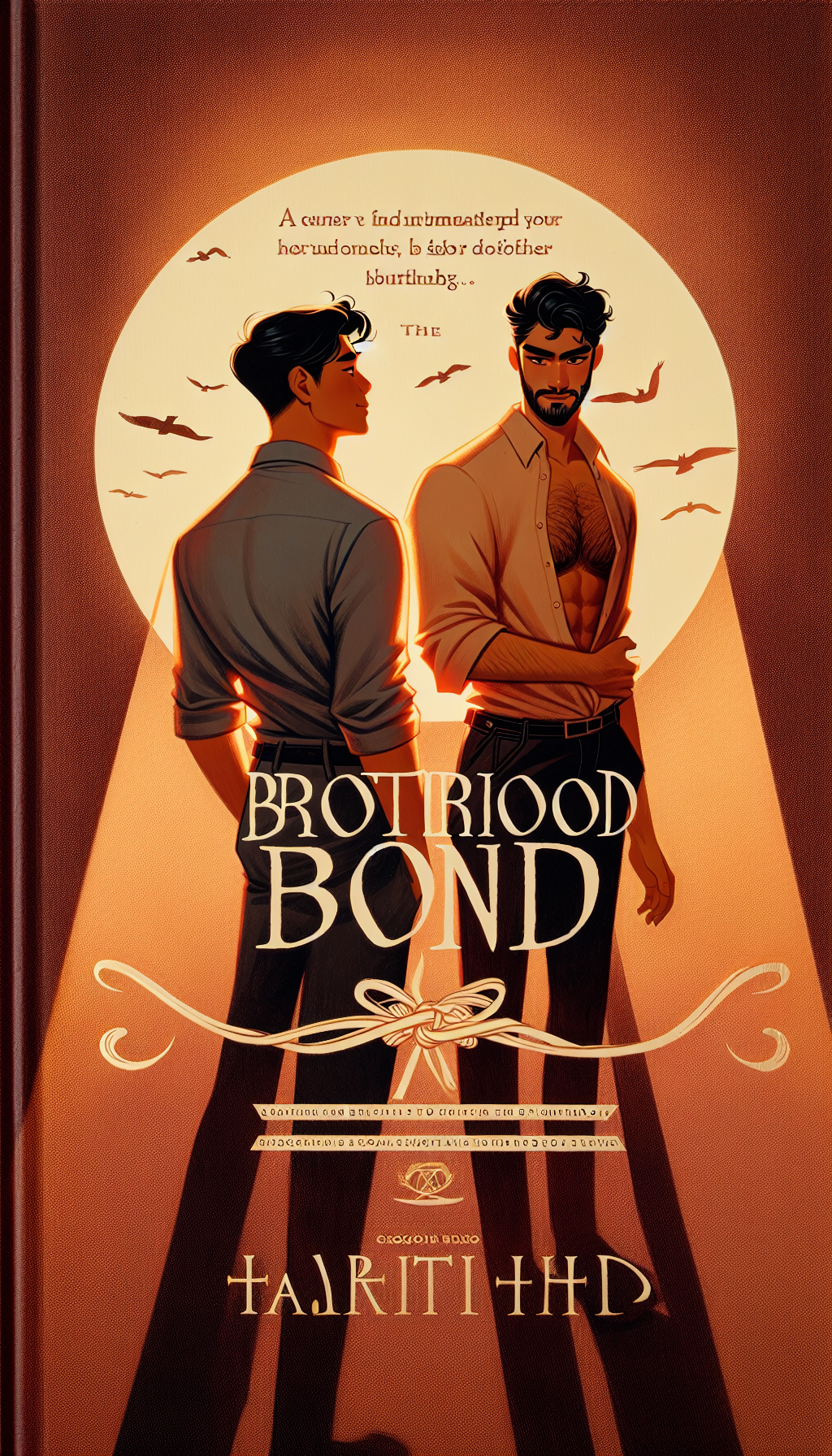愛の瞬間を切り取る
煌びやかなネオンが散りばめられた都市の中心で、彼女、ミキは深夜のカフェに腰を下ろしていた。外は雨がしとしと降り、路面が濡れ光を反射していた。ここは彼女が毎晩通う場所であり、心の底から安らぎを感じる数少ない場所だった。賑やかな会話とは裏腹に、彼女の頭の中ではさまざまな思考が交錯していた。
最近、SNSでの自分の存在感に少し疲れていた。毎日更新することが期待される時代、フォロワー数が彼女にとっての自己価値を測る一つの基準となっていた。しかし、いくら写真を編集し、キャプションに気を遣い、褒め合うコメントを返しても、心の奥にある虚無感は消えなかった。
一杯のコーヒーを前にして、ミキはスマートフォンを手に取り、思わずアプリを開いた。最新のフォロワー数を確認する。少し減っていた。彼女は心の中で数え上げた。失ったのは二人。何がいけなかったのか。この問いは彼女の心を締め付け、がんじがらめにした。
周囲には友人たちが楽しそうに集まっている。恋愛話や仕事の愚痴、次の旅行の計画など、明るい声が飛び交う中で、ミキはその声の波間に漂う孤独を感じた。彼女は自分の話ができない。自分が本当に求めるもの、大事なものを見失ってしまったと感じていた。
その瞬間、ふと彼女の視線が奥のテーブルに目を向けた。そこには一人の青年、名はカズト。彼もまた、スマートフォンを手にしている。しかし彼の表情は何か違った。画面に映る世界を眺めながら、どこか遠くを見つめる目をしていた。確かに、周りの客は彼に気づいていないが、彼女はその眼差しの奥に隠された悩みを感じとった。
勇気を出して、ミキはカズトのテーブルへ近づいた。「ごめん、いい?一緒にいても?」カズトは驚いたように顔を上げ、小さく頷いた。「もちろん。」
コーヒーを頼んだミキは、カズトに話しかけた。「何を見ているの?ずっとスマホを見てるけど。」
「これ、写真を撮ってるんだ。街の風景をさ。」カズトは画面をミキに見せた。美しい夜景と雨に濡れた街路。彼は何気なくシャッターを切っていたのだという。
「すごい、素敵。でも、そんな時代じゃないよねみんな、SNSのためにポーズを取るばかりで。自分を演出することに疲れない?」ミキは思っていたことを吐き出した。
カズトは少し考えた後、穏やかな声で答えた。「うん、確かにそうかもしれない。でも、僕はただその瞬間を切り取ることが好きなんだ。その時の雰囲気や光、雨が作る反射。誰にも見せないフォルダにそれを保存しておくんだ。」
彼の言葉に、ミキは心を打たれた。彼は自分のために写真を撮っているのだ。自分を見せることを目的とするのではなく、ただ「美しい瞬間」を楽しむために。ミキは自分がどれだけその瞬間を見落としていたかを実感した。
「じゃあ、今度一緒に撮影しようよ。私もそれを楽しみたい。」カズトの目が少し輝く。「もちろん、いいよ。」
それ以来、二人は会うたびに街の中を歩き回り、思い思いの写真を撮ることにした。何かを見かけてはカズトがカメラを構え、ミキもそれを真似してみる。時にはお互いの写真を見せ合い笑い、時には静かに沈黙し、ただその瞬間を共有した。
しばらく経って、ミキは自分のSNSにその写真を投稿するのをやめた。ただ二人だけの世界に浸り、隣で笑っているカズトとの時間を大切にした。美しい瞬間を重ねていくことで、彼女の心の中にあった虚無感は少しずつ薄れていった。
ある日、雨上がりの夕方にふと二人で出会ったカフェの窓から、街の灯りが浮かび上がる景色を一緒に見つめた。ミキは心の底から感じる充実感を噛みしめた。「この瞬間を、どんな言葉で表せばいいのか分からないけど、とても幸せ。」
カズトは微笑み、彼女の手をやさしく握った。「それは、言葉にしなくてもいいんじゃないかな。僕たちはここにいるんだから。」
二人は言葉を超えた理解の中で、ただその時を楽しむことを選んだ。彼女は心の中で、あの煌びやかなネオンとは異なる、温かい光を見つけたのだった。