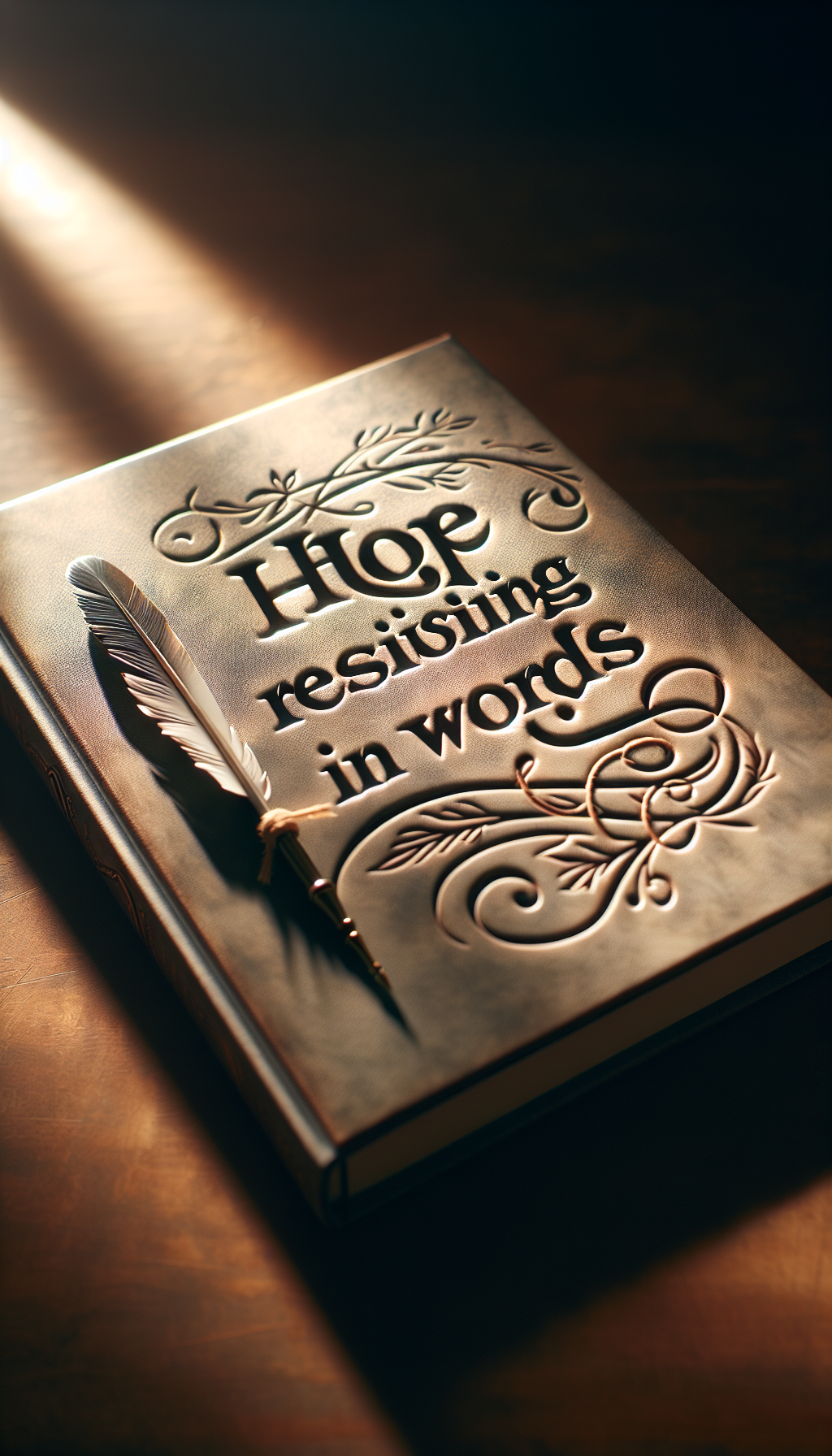夏の終わりの約束
夕暮れ時、街の片隅にある古びたカフェのテラス席に、涼しい風が吹き抜けた。高校三年生の沙奈は、最後の夏休みを迎えた自分の心のうちを整理するため、友人の美咲と二人でこのカフェに来ていた。彼女たちの目の前にはアイスコーヒーが置かれ、さやかに緑の葉が揺れている。
「本当に、もうすぐ終わっちゃうんだね、高校生活」と、美咲が言った。彼女の指は、コーヒーのストローを小さくくるくると回している。
「うん、信じられない。でも、なんかあっという間だったな」と沙奈も返した。ふと、壁にかけられた古い時計を見る。針は六時を指しているが、彼女の心の中ではもう時間が止まっているようだった。
「卒業したら、みんなそれぞれの道に進んじゃうんだよね。淋しいな」と、美咲が溜息をついた。沙奈は、二人の間に流れる沈黙の中で、友人との別れを漠然と感じていた。
「私たち、こんなに長い間一緒にいたのに、どうしてもっと一緒にいなかったんだろうね」と沙奈がぽつりと言った。美咲は大きく目を見開き、何かを考えるように天井を見上げた。
「私もそう思う。でも、過去は戻らないし、これからだってどうなるかわからないよ。今のこの瞬間を大切にしよう」と美咲が力強く言った。その言葉に沙奈は心を打たれた。彼女は思わず美咲の目を見つめ返した。
二人は、そのまましばらく黙ってアイスコーヒーをすすっていた。夕焼けがオレンジ色に空を染め、人々がカフェの周りを行き交う。彼女たちは、この瞬間が終わることを恐れているようにすら見えた。
翌日、沙奈はバイト先の書店の帰りにふと思い立って、公園に寄ってみた。そこには、子供たちが遊び、大人たちがゴザを広げている姿があった。何か懐かしい気持ちが湧き上がり、思わずその光景を見守った。思い出したのは、初めて美咲と出会った日のことだった。小学校の入学式で二人は同じクラスになり、一緒に遊ぶ約束をしたのだった。
「沙奈、見て」と後ろから美咲の声が聞こえた。振り返ると、美咲が満面の笑みを浮かべて立っていた。
「どうしたの?」と沙奈が尋ねると、美咲は小さな手に何かを持っている。「これ、みんなでやってみない?」
美咲が持っていたのは、カラフルな風船とビニールの的だった。二人はそれを広げ、公園の一角で友人たちを誘った。数分後、男の子たちが集まり、風船を一斉に飛ばした。公園は笑い声で満ちた。
その時、沙奈はすべての刹那を大事に思った。彼女は美咲に、「大好き!」と叫びたい衝動を感じたが、それを口にする勇気がなかった。
それから数ヶ月が過ぎ、学校の卒業式の日がやってきた。体育館に響く卒業生たちのスピーチや感謝の言葉が、沙奈の心に重みを持たせる。
「皆さん、私たちはこれからそれぞれの道を歩んで行きます。でも、過ごした日々は必ず心の中に残ります」と校長先生が語ると、沙奈はじわりと涙をこぼした。美咲の顔を目で探すと、彼女と目が合い、少し微笑んだ。
式が終わり、友人たちとの別れの挨拶が始まった。その中でも、美咲とは特に時間をかけて、お互いの思い出を語り合った。沙奈は心の底から感謝の言葉を伝えた。
「また、いつでも会おうね!学校が違っても、友達だから」と美咲が言う。この瞬間が永遠であるかのように、二人は何度もその言葉を繰り返した。
別れの時が迫り、沙奈は思い切って言った。「私も美咲のこと、大好きだよ!」その言葉は、心からの思いがこもったもので、ふたりの絆をさらに深めるものとなった。
これからの未来がどうであれ、沙奈は今この瞬間が一生忘れられない宝物だと感じた。別れは確かに淋しいけれど、新しい出会いや経験が待っていることを信じて、彼女は次の一歩を踏み出す決意を固めた。彼女たちの青春は、今ここに、確かに生きている。