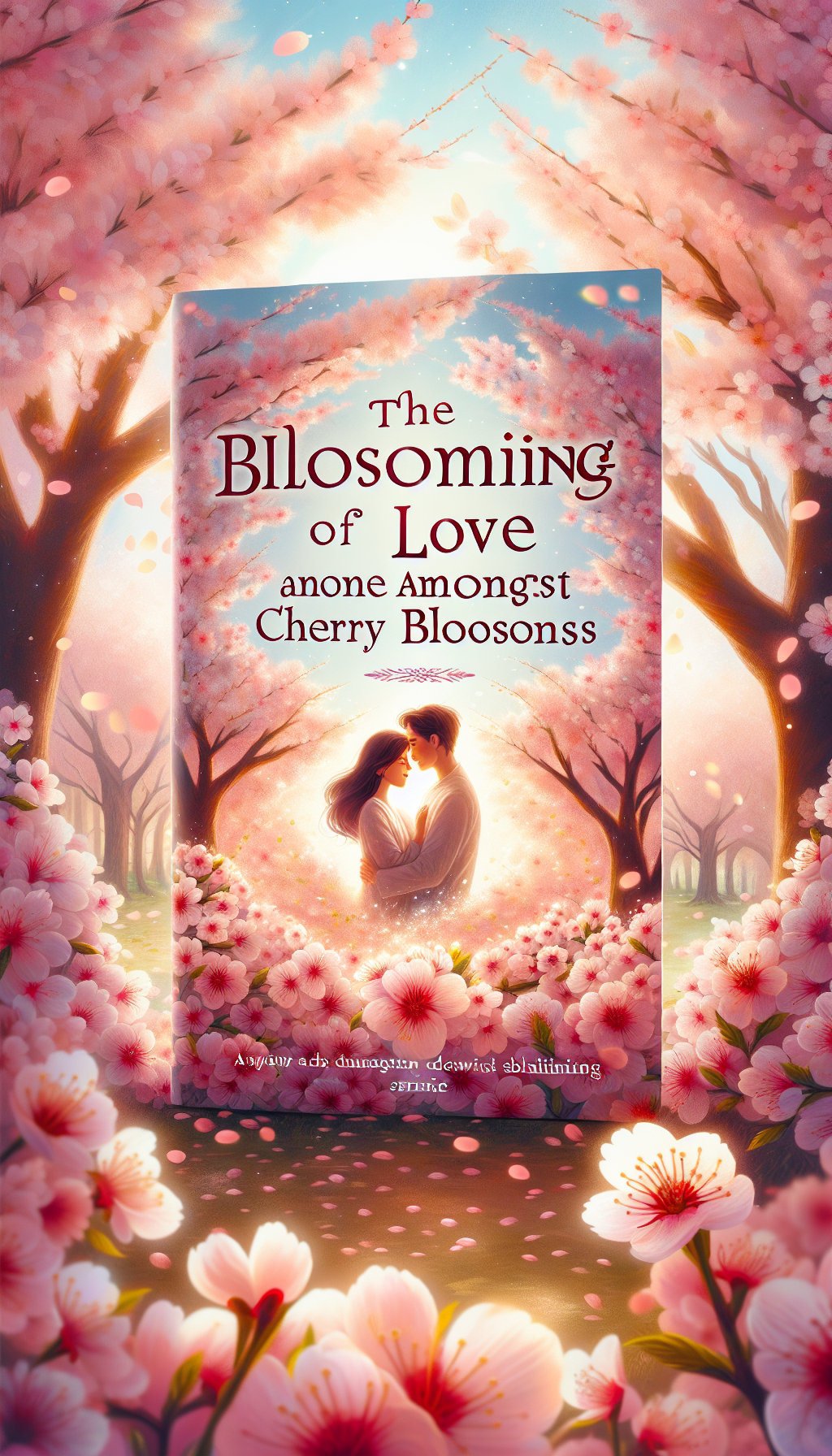夏の終わりの約束
ある夏の終わり、東京都心の小さなカフェで、私は首藤美咲という名の女性に出会った。彼女は毎朝、同じ時間にやって来て、窓際の席に座り、熱いカフェラテを注文した。彼女の髪は長く、柔らかな波がかかっていて、笑顔は太陽の光のように周りを明るく照らしていた。
最初のうちは、彼女の存在に気づかないふりをしていたが、次第に彼女の仕草や表情が目に入るようになった。美咲は本を読むことが好きで、常に異なるジャンルの小説を持ち歩いていた。時折、本を読む手を止め、外を眺める姿が印象的で、その瞬間の彼女の表情に心を掴まれてしまった。
ある日、勇気を振り絞って声をかけてみた。
「こんにちは、毎朝ここでお見かけしますね。」
驚いた様子で美咲は顔を上げ、ふんわりとした笑顔を返してくれた。「ええ、ここが好きなんです。あなたも?」
その日をきっかけに、私たちはお互いの生活を少しずつ知るようになった。美咲は大学生で、文学を専攻していると語った。彼女は夢があって、将来は自身の小説を出版することを目指しているという。話をするたびに彼女の想いの深さや作品にかける情熱を感じ、それと同時に惹かれていった。
カフェでの会話が続く中で、次第に親密さが増していった。美咲は私のことも知りたがり、ささいな趣味や家族のこと、将来の夢についても聞いてくれた。少しずつ彼女と共有する時間が増え、心の距離も縮まっていった。
ある土曜日の午後、美咲は特別な提案をしてくれた。「私の好きな本を一緒に読んでみない?」と。彼女が選んだのは、村上春樹の短編集だった。私たちは公園のベンチに座り、交互にページをめくりながら作品の感想を交わした。彼女の声が優しく響き、心地よい風の中で、時間があっという間に過ぎていった。
それからさらに数回、二人で公園に行ったり、映画を観たりするうちに、お互いの心の奥底に存在するものが次第に形を持ち始めていることに気づいた。友情が愛情に変わりつつあるのを感じ、私は胸が高鳴ると同時に、どう接するべきか悩んでいた。
ある日の夕暮れ、美咲と一緒にカフェの外で過ごしていた時、思わず彼女の手を握った。「美咲、君のことが好きだ」と言葉が自然と口をついて出た。彼女は私の目をじっと見つめ、しばらく沈黙が流れた。その瞬間、私は不安と期待が入り混じった感情を抱えた。
やがて彼女はゆっくりと微笑み、「私も」と返してくれた。喜びで心が満たされると同時に、彼女が手を引き寄せてくれた。その瞬間、私たちの距離が確かに縮まったことを実感した。
それからの数ヶ月は、まるで甘美な夢のようだった。私たちは一緒に過ごす時間を増やし、お互いのことを少しずつ深く知っていった。恋人同士になっても、美咲の文学に対する情熱は変わらず、私も彼女を支える存在になりたいと願った。
しかし、時が経つにつれ、美咲が卒業後に大きな選択を迫られることになる。彼女には海外留学の夢があったのだ。私との関係を続けながら、その夢を追うのが本当に可能なのか、美咲は悩んでいた。そして、別れの予感が彼女の心を締め付けているのを感じた。
ある晩、私たちは再び公園のベンチに座り、彼女はぽつりとつぶやいた。「私、行かなくちゃいけないかもしれない」と。その言葉は、私にとって耐えがたい痛みとなった。美咲は続けて、「でも、私たちの出会いは無駄じゃなかったと思う。これからも、あなたのことを大切に思う」と告げた。
涙が頬を伝いそうになったが、私は彼女の手を強く握り、「君の夢を追うことを応援するよ。自分の道を進むことが、一番大事なことだと思うから」と言った。美咲は涙を浮かべながらも微笑み、私たちは互いに抱きしめ合った。
それから数ヶ月後、美咲は夢を追い求めて旅立った。彼女との思い出は心に強く残り、私は彼女の選択を尊重することを決意した。時折カフェに行くと、彼女と過ごした日々が心を温かくした。
愛情とは、単に一緒にいることだけではなく、相手の幸せを願い、支えること。それが私たちが育んだ絆だった。別れが訪れたとしても、その愛情は永遠であり、私の心の中に美咲が生き続けることを信じていた。