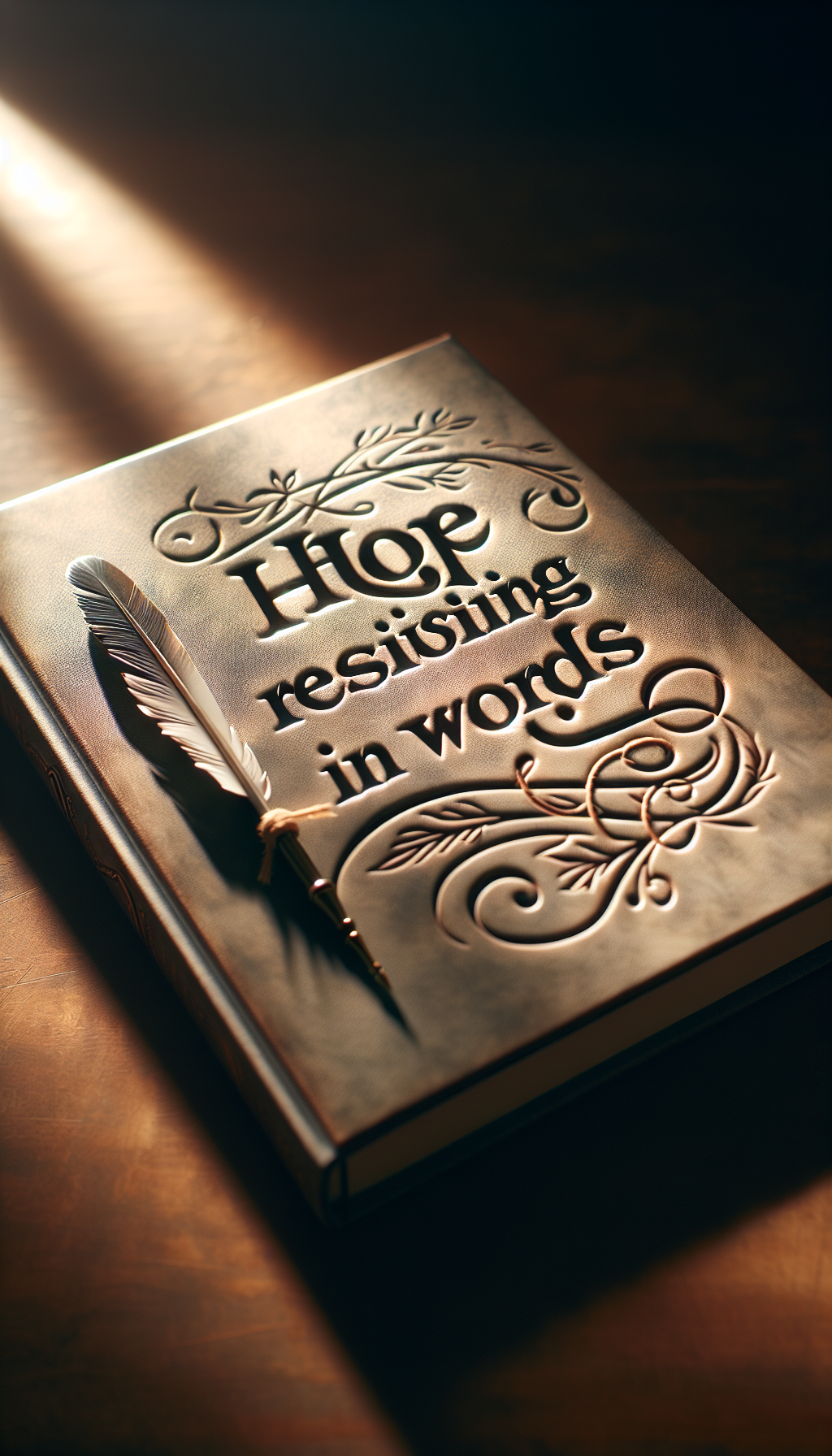桜の再会
空は青く、ふわりとした雲が流れ、桜の花びらが舞い落ちる季節だった。僕たちは高校最後の春休みを迎え、桜が咲き誇る公園で集まっていた。四郎、琴子、翔太、そして僕—優斗。幼馴染の僕たちは、ずっと一緒だった。進学や就職、夢追いなどそれぞれの道を歩み始める前の最後の春休み、僕たちは思い出作りに熱中していた。
「もうすぐ別々の道に進むんだな」と四郎がポツリと言った。その言葉に琴子はふくれっ面をした。「そんな寂しいこと言わないでよ、今は楽しまなくちゃ」という琴子の言葉に僕は同意し、翔太も「ま、琴子の言う通りだな」と笑った。
その日は終わってしまうことを恐れずに、僕たちは毎日一緒に過ごした。キャンプに行ったり、夜遅くまで星を見たり、大好きな映画を見返したり。時間が止まればいいのにと何度も思った。
ある夜、僕たちは秘密の場所、川沿いの廃工場に集まった。元々は工場だったが、僕たちにとっては秘密基地だ。入り口には錆び付いた柵があり、その柵は今では草木に覆われ、まるで自然に飲み込まれている。だが、そこは僕たちだけの隠れ家だった。
「この場所も、もうすぐお別れか…」と詩的なことを言ったのは翔太だ。「誰もいなくなっちゃうからね」と琴子も寂しそうに足元を見つめた。
「でもさ、ここで約束しようよ」と僕が言った。四郎が何も言わずに僕を見つめ、「どんな?」と聞いた。その時、僕は心に決めていた。
「将来、またみんなここで集まろう」と。四郎と翔太が一瞬目を見合わせ、琴子が「いいね、それ」と笑顔を見せた。「じゃあ、再会の約束」と僕たちは手を重ねた。
桜が散り、夏が来て、僕たちはそれぞれの新しい生活を始めた。連絡は途絶えなかったが、時間が経つにつれてお互いに忙しさに追われ、頻度が減っていった。それでも「また集まろうね」という言葉はくじけることなく、お互いの心に残っていた。
そんなある日、翔太からの一通の手紙が届いた。彼は医学部に進学し、将来的には医者になることを目指していた。その彼が突然、「しばらく連絡が取れなくなる」と告げる手紙だった。理由は書かれていなかったが、その一通が僕たちの結びつきをさらに強くした気がした。
数年が経ち、それぞれが忙しい生活を送っていたが、僕たちは再会の約束を忘れずに生きていた。そして十年後の桜が満開の頃、僕たち四人は再び川沿いの廃工場に集まった。
「優斗、お前もすっかり大人になったな」と笑いながら四郎が言った。彼は会社の管理職となり、家庭を持っていた。琴子は美術教師となり、夢であった芸術に携わる仕事をしていた。
翔太も、数年前に連絡が途絶えた理由を話した。彼は医学部での過労と精神的なストレスで一時期休養が必要となっていたのだ。しかし、今では立ち直り、立派な医者として働いていた。
「みんな、よく頑張ったな」と翔太が言った。その言葉には、十年前の僕たちが誓った青春の日々がこもっていた。そして僕たちは再び廃工場で手を重ね、今の自分たちを確認し合った。
「これからも、それぞれの道を歩んで行こう。でも、いつでもここで再会しよう」と僕は微笑みながら言った。四郎、琴子、翔太も頷き、手を重ねた。
「じゃあ、また十年後?」と琴子が笑顔で言った。四郎が「そうだな、次も無事に再会できるように」と僕たちの手をぎゅっと握りしめた。
桜の花びらが舞う中、僕たちは再び歩き始めた。それぞれの人生という荒波の中でも、いつでも戻れる場所がある。そう思うだけで、未来への不安は少しだけ和らいだ。
青春の日々はもう戻らないかもしれないが、僕たちの心にはずっとあの日々が刻まれている。あの時約束した通り、僕たちは再び青春時代の仲間と共に、新たな歩みを始める。そうして、僕たちの物語は続いていくのだ。