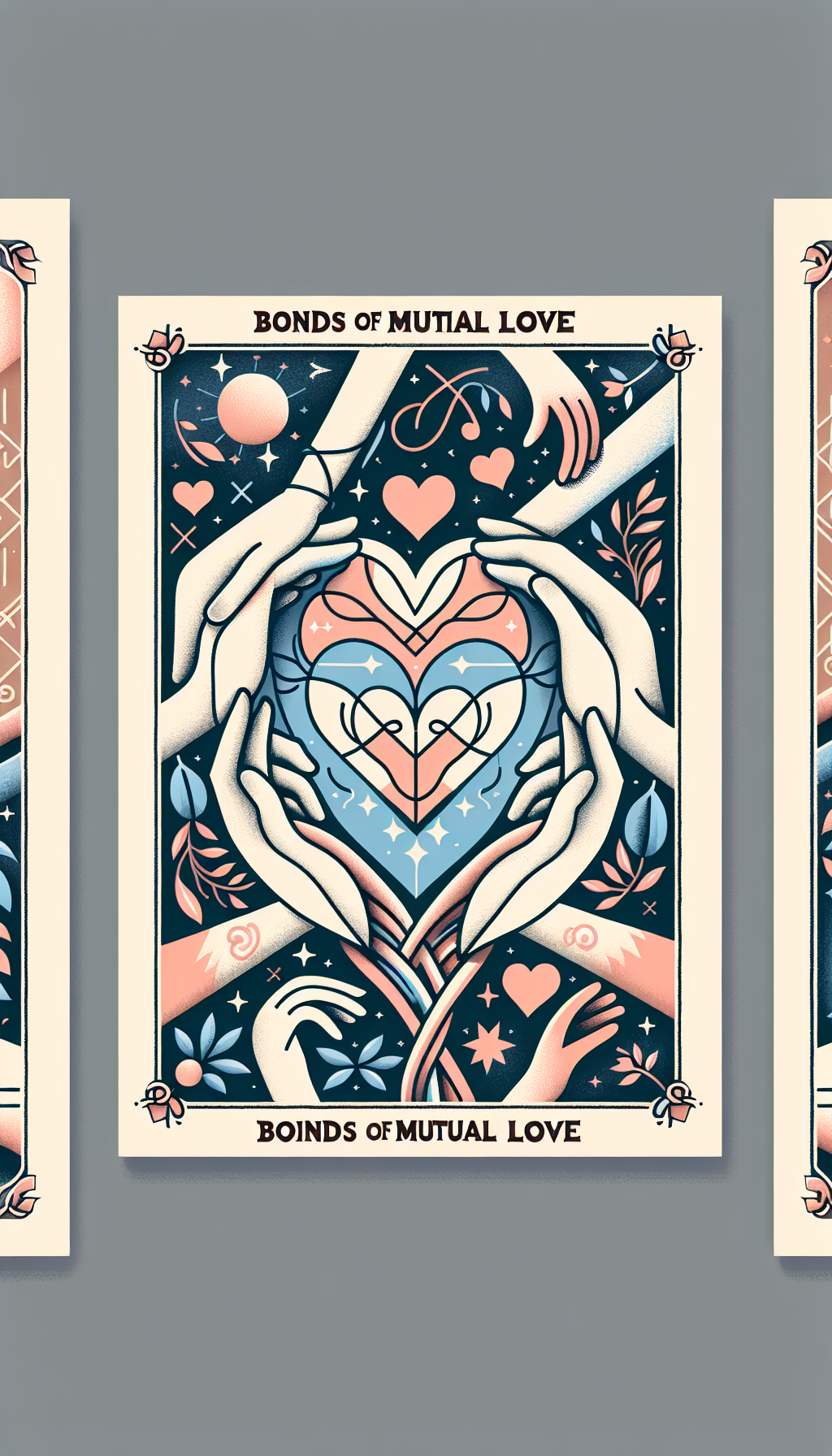家族の絆
佑介は33歳。東京都内の小さな広告代理店で働いていた。成功とは言い難いキャリアの中で、毎日を淡々と過ごしていた。既婚者だが、妻の美佳とは最近すれ違いが続き、家に帰るのがどこか億劫になっていた。そんな折、佑介の母からの電話がかかってきた。
「佑介、実家に帰って来ない?」母の声は少し疲れていた。父が病気になり、余命が短いかもしれないという知らせだった。佑介は茫然とした。両親のことは気にかけていたが、あまりにも遠い存在になっていた。迎えに来るという母に何とか返事をし、数日後に実家へ向かうことにした。
実家に着くと、懐かしい風景が目に入った。しかし、家の中は静まり返り、父の姿が見当たらない。母が台所で動いていることに気づいた佑介は、声をかけた。「お母さん、父さんは?」母は一瞬手を止めて、悲しそうな目で佑介を見上げた。「もう車椅子になってしまっているの。」
食卓の周りには数日分の食べ物が並べられたままだった。佑介は母が一人で全てを抱えているのだと感じた。しばらく沈黙が続いた後、佑介は覚悟を決めて言った。「手伝うから、何でも言って。」
こうして、実家での日々が始まった。朝、父を起こし、食事を手伝い、薬を飲ませる。佑介が自分の家庭のことを考える余裕もなく、ただ日常が流れていった。時折、父が昔の話を始めると、佑介はその話を聞くことで少しでも父との距離を縮めようとした。父の大好きだったウィスキーの話や、若い頃の夢。話すうちに、佑介の心に封印されていた思い出がよみがえり、父との絆を再確認する瞬間があった。
そんなある日の晩、佑介は父から思わぬ話を聞いた。「佑介、お父さんは自分が喜んでいたことを、あんたにも知ってほしい。」父は少し言葉を選んで続けた。「あんたの方が成長して、やっとわかったことが、若い頃の自分にはできなかった、ということだ。」
佑介はこの言葉を聞いて、胸が締め付けられる思いがした。父は自身の青春を、佑介の成長について語ることで、自分が手に入れられなかった夢を叶えようとしているのかもしれないと感じた。その瞬間、佑介は自分の家庭を懸命に守ろうと努力していなかったことに気がついた。
しかし、佑介は自分ばかりが抱える問題を考え、どこか気持ちを割り切れないでいた。帰りを待つ美佳のこと、仕事のこと。自分の人生に埋もれて、家族の大切さを忘れかけていた。母の疲れた顔、弱っていく父の姿を目の当たりにすることで、彼は自分の無関心に気づかざるを得なかった。
ある日、佑介は家族全員を集めて話をした。「本当に大変な時期だけど、みんなで助け合おう。俺もできることがあれば、言ってくれ。」その時、母は泣きながら頷き、少しずつ笑顔を見せた。父はベッドの上で、微かに目を細め、彼らの会話を見守るようにしていた。
時間が経つにつれ、病状は進行していった。それでも彼らは少しずつ前向きになり、支え合いながら過ごした。特に佑介は、仕事と家庭の両立を再考し、実家での役割を誇りに思うようになった。家族のためにできる限りの努力をするという選択が、彼の心を軽くした。
そして、父が静かに息を引き取った夜、佑介はその瞬間に立ち会った。父の手を握りしめられることができ、少しだけ心が和む感覚を覚えた。父の愛情が、家族の中に生き続けていることを今は実感していた。
その後、佑介は実家を出てからも家族との絆を大切にすることを決意した。美佳と共に、また家族を築いていくための道を模索し始めた。彼にとって、家族の大切さは何よりも重い意味を持つものであり、受け継がれる愛情が新しい形で花開くことを願った。
家族が互いに支え合い、繋がっていくことが、最後には全てを癒すのだと、佑介は心から感じていた。