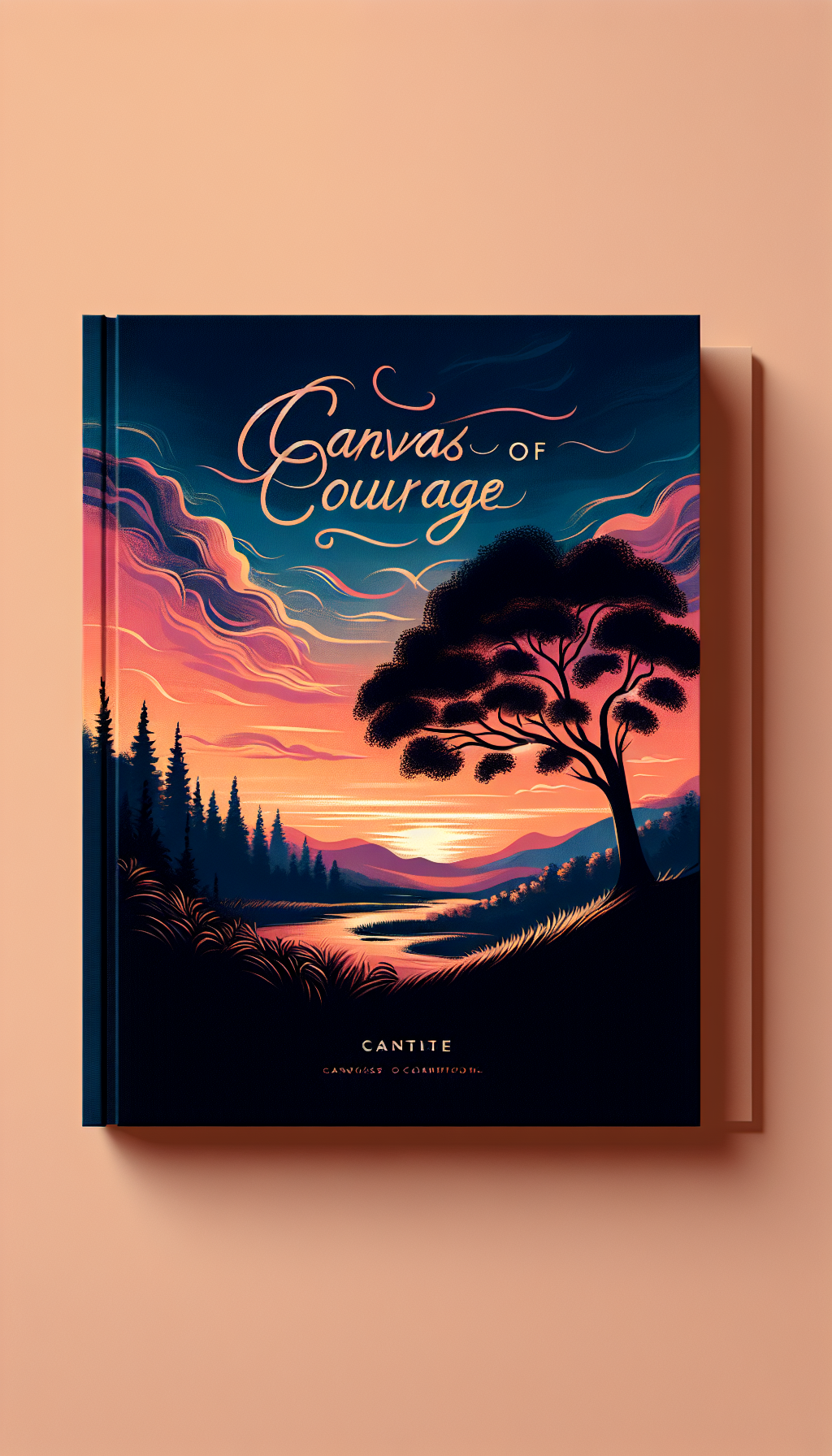未完の絵の続き
冷たい雨が降りしきる中、由美は古びた傘を傾けながら、ある小さな画廊の前で足を止めた。絵画に強い興味を持つわけではなかったが、その窓越しに見える一枚の絵が彼女の心を捉えたのだ。
中に入ると、画廊の独特な香りと落ち着いた雰囲気が広がり、外の喧騒が一瞬で消え去った。壁に掛けられた絵を一枚一枚眺めていると、画廊の奥からひとりの老人がゆっくりと出てきた。
「いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください。」と、柔らかな声で迎えられた。
由美の目が再び窓越しに見た絵に留まった。色とりどりの花が溢れるフィールドを、少女が軽やかに舞うように描かれた一枚の絵だ。彼女はその光景に心を奪われていた。
「美しい絵ですね。」由美が何気なく口にした。
「そうですね。あれは私の娘が描いたものです。」老画家は微笑んで答えた。
娘の話を聞こうとしたが、不意に壁の端にもう一つ目立たぬ絵があることに気付いた。暗い色調で描かれた風景画で、ほとんど人の目に留まることはないのだろう。それでも、由美はその絵に何故か惹かれた。
「こちらの絵も気になります。」と由美が言うと、老画家は少し困ったような笑みを浮かべた。
「あの絵は未完成なんです。娘が描きかけたまま手を止めた作品でして。」
由美は驚いた。その絵は、たとえ未完成であっても十分に力強い印象を彼女に与えている。
「どうして未完成のままなのでしょうか?」と、由美は切り出した。老画家は一瞬黙り、高揚した様子で続けた。
「彼女は病気で筆を握ることができなくなったのです。彼女は今病院のベッドの上にいます。この画廊は、彼女の絵を展示するために借りました。」
由美はその言葉に深い感銘を受けた。この画廊が、一人の画家の未完の夢を他の手で完成させるために存在する場所なのだということがわかったのだ。
「その絵を見ていると、何かを補足したくなるんです。」と由美は声に出して言った。「まるで、続きを見たいような気がして。」
老画家は優しい眼差しでうなずき、「それが娘の望みでもありました。全ての作品が完結することなくとも、見る人それぞれが完成を感じ取れるようにと。」
由美は感触に突き動かされ、絵を購入することを決意した。その夜、自宅のリビングに絵を飾り、しばらくその前に座って時が過ぎていくのを感じていた。
翌日から由美は、久々に絵筆を持ち出して自分の作品を描き始めた。子供の頃から絵を描くのが好きだったが、忙しさにかまけて長い間絵を止めていたのだ。その繊細なタッチを再び思い出しながら、彼女は新たな作品に取り組むことにした。
数ヶ月後、由美は自分の作品を老画家に見せに行くことにした。あの画廊の前に立った時、彼女は胸の高鳴りを感じた。老画家は彼女の作品を優しく手に取り、一つ一つの細部を丁寧に見てくれた。
「素晴らしいですね。あなたの絵に生き生きとした生命が感じられます。」彼は心からの賛辞を送った。
由美は微笑み、静かに一言、「あなたの娘さんの絵が私に新しい命をくれました。感謝しています。」
その後、彼女は老画家の娘とも面会する機会を得た。病院のベッドで横たわる彼女に、由美は自分の物語と、新たに描き始めた絵のことを話した。彼女の目が輝き、感動の涙がこぼれた。
「お父さんが私の未完成の絵を見せながら、誰かが続きを感じ取ってくれることを願っていたと聞きました。あなたがその続きを教えてくれました。」
由美の描く絵は次第に地元で評判を集め始め、いつしか個展を開くまでになった。そして、その会場の一角には、彼女が初めて買った老画家の娘の未完の絵も一緒に飾られていた。
その展示会場には、絵を愛する人々が多く訪れ、彼女の描く世界が広がっていった。由美にとって、絵画はただの趣味ではなく、人生そのものを変える力強い媒介となったのだ。そのすべては、ある小さな画廊で運命の出会いが扉を開けた瞬間から始まったものだった。
雨の音が再び聞こえるある季節の夕暮れ、由美はふと、あの未完成の絵に目を向けた。そしてその先にいる見知らぬ誰かの夢の続きを想い、また新たな一筆を加えるのであった。