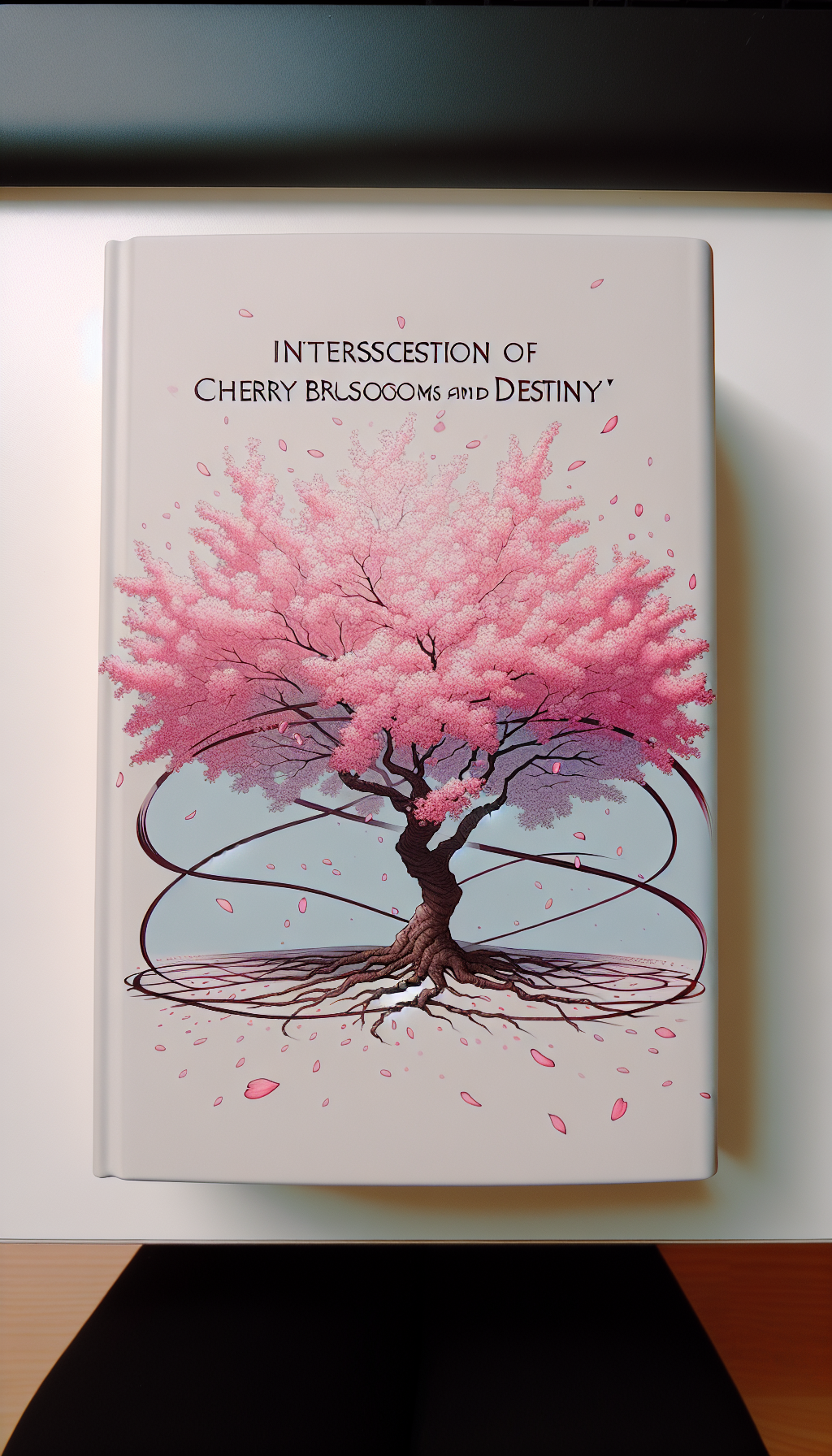波間の亡霊
薄曇りの早朝、港町の小さなカフェに一人の男が座っていた。彼の名は坂本敏夫。長年港の漁師として生計を立ててきたが、今は魚を捕ることをやめ、毎朝このカフェでコーヒーを飲むのが日課になっていた。敏夫は、人生の潮が引くのを待っているような、そんな静かな日々を送っていた。
だが、今日の敏夫の心はざわめいていた。数日前、近くの港で漁師たちが見つけた死体のことが、町中で噂になっていた。遺体は海に浮かんでいたが、警察の捜査によれば、どうやら他殺だったらしい。その漁師は町でも評判の悪い男、田島だった。彼は年齢は三十代後半で、酒と女に溺れる日々を送っていたが、特に危険な男というわけでもなかった。だが、敏夫は田島をよく知っていた。昔、田島がトラブルを起こしたとき、敏夫が助けたことがあったのだ。
その日の午後、敏夫はカフェを出て、港へ向かった。心のどこかで、田島の死に何らかの関わりがあるのではないかと感じていたからだ。港に着くと、岸壁には複数の若い漁師たちが集まっており、田島の話をしていた。
「田島は、最近変わったんだ。前よりも不気味だった」と、若い漁師の一人が言った。もう一人は「腹立たしいことに、彼はいつも酒と暴力で周囲を脅していたから、誰が犯人かなんて分からないよ」と続けた。
敏夫はその様子を見ながら、田島との過去を思い出していた。ある酒場で、敏夫が田島を助けた時、彼は「お前には恩義がある。俺はお前に何かあったら助けるからな」と言っていた。敏夫は、その言葉に何か特別な思いを抱いていたが、それが今、田島の死との関連を示しているのではないかと考えた。
次の日、敏夫は独自に田島の家を訪れた。そこはひんやりとした古い家で、田島の父親が亡くなった後、彼が一人で住んでいた。ドアをノックすると、応答はなかった。敏夫は戸を開けて中に入り、薄暗い部屋を覗き見た。
部屋には散らかったゴミや、酒瓶、テーブルの上には田島の顔写真が大量に貼られた掲示があった。それは、おそらく田島が狙われていたことを示唆している。敏夫は、何かを感じ取り、写真を一枚手に取った。それは、彼が戦っている様子を捉えたものだった。
その表情には、恨みや恐怖が交錯していた。田島は何かに追われていたのだ。敏夫は不安になり、周囲を探ることにした。すると、近くの酒場で一人の女が田島と親しそうに話していた姿を目撃した。彼女の名前は美咲。酒場で田島と一緒にいる姿は、周囲にどう見えていたのかが気になった。
翌朝、美咲に会いに酒場を訪れた。彼女は酔っ払った様子ではなく、冷静に敏夫を見つめていた。敏夫は田島の死について質問し、彼女が知っていることを探った。
「田島のこと?彼は私を脅していた。でも、彼を助けようと思ったの。だって、彼は本当は根っから悪い人じゃないと思ったから」と美咲は言った。
敏夫は胸が痛む思いだった。田島が他人を脅すようなことをしていたとはいえ、彼なりに闇を抱えていたのだ。美咲は続けた。「実は、田島の周りには彼を狙う人たちがいた。彼が酒に溺れていたことで、何かを掴めずにいたの。」
敏夫はその言葉から何かをひらめき、半信半疑だったが美咲を連れて田島の家に戻った。二人は部屋の中を調べているうちに、古びた引き出しの中から一枚のメモを見つけた。それは、脅迫状だった。「お前の悪行はもう終わりだ。次はお前の番だ。」と書かれていた。
二人はそれを警察に持って行くことにした。このメモが田島の死の手がかりになるかもしれなかったからだ。警察はすぐに捜査に取りかかり、その結果、田島の死に関与した犯人を特定することができた。彼は田島の依存症を利用して犯罪に巻き込もうとしていた男だった。
敏夫は心の中で少しだけ救われる思いがした。田島の死は悲劇だったが、その背後には複雑な人間関係と闇があった。敏夫は、田島の亡霊に敬意を払い、彼のことを忘れないことを心に誓った。
これからの港町の潮流は、彼にとって少しずつ変わっていくのだろう。田島のことを忘れずに、彼のことを語り継ぐことが、自分の新たな生き方の一つになると信じて。