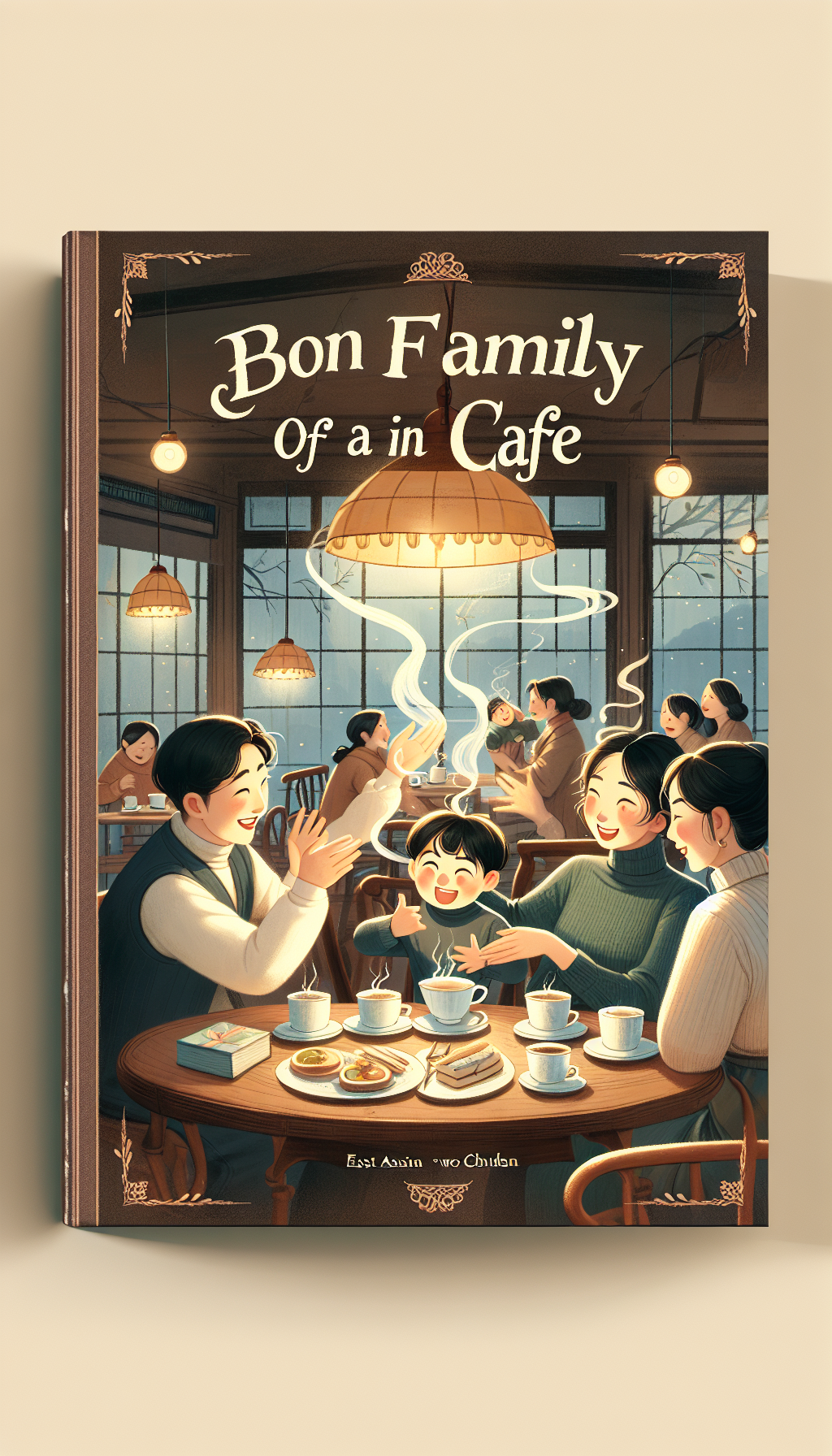兄弟の絆、恋の芽生え
夏の終わり、太陽がやや低くなり始めた頃、兄の大輔は友人の結婚式のために従兄弟と一緒に帰省することにした。東京で働く大輔は、忙しい毎日の中で家族に会う時間をなかなか取れず、久しぶりに実家の空気を吸うのを楽しみにしていた。
実家に着くと、すでに弟の健二が待っていた。健二は大学を卒業したばかりで、上京する準備を進めていたが、長い間帰省するのは久しぶりだった。兄弟の再会は久しぶりのせいか、少しぎこちない。互いにどう過ごしていたのかを話し始めるものの、そこにいたのは昔の兄弟のような無邪気さではなく、大人としての互いの立場だった。
夕方、実家の居間で母が用意した夕食が並ぶ。焼き魚、煮物、味噌汁。懐かしい味に、二人は自然と笑顔になる。家族が揃う温かさに、二人の心も少しずつ解けていく。しかし、話は健二の就職活動や新しい街での生活についてのものが多く、大輔は自分がどれだけ健二を日常で支えられなかったかを痛感する。
「兄ちゃん、結婚式には誰か連れて行くの?」健二が問いかける。
「いや、一人で行くつもりだよ。仕事忙しいし、婚活も進んでないしね。」大輔は少し気まずそうに笑った。
「ふぅん、一人か。ちょっともったいないな。兄ちゃん、いつもカッコいいって言われてるんだから、誰か誘ったらどう?」健二は軽い冗談交じりに言ったが、その真意がどこにあるかを大輔は察していた。健二は自分の結婚への期待を重ねていたのだ。
その夜、二人は久しぶりに兄弟としての親しさを再発見する時間を持った。健二が東京での生活について熱く語る中、大輔は昔の彼を思い出していた。学生時代、よく一緒に映画を見に行ったり、ゲームをしたりしていたこと。そんな思い出が、今、兄弟の絆に新たな色を添えている。
数日後、結婚式当日。大輔はスーツを着て鏡の前で自分の姿を確認していた。しかし、ふとした瞬間、健二と二人で選んだスーツを着ている自分を思い出す。兄弟の絆があったからこそ、カッコ良く見せることができたのだ。
式場に着くと、きらびやかな装飾と幸せな雰囲気に包まれた。新郎新婦を祝う声が響く中、大輔の気持ちは複雑だった。友人たちの笑顔を見ながら、自分だけが一人でいることに少しの孤独を感じてしまう。
披露宴が始まると、周囲のカップルや家族を見て、胸が締め付けられるような思いが募る。しかし、その時、目の前の席に座る女性が目に留まった。彼女は新婦の高校時代の友人で、名前は由美。笑顔が魅力的で、周りを明るくするオーラを放っている。
席が前後になったことで話しかける機会があった大輔は、互いに軽い会話を交わし、彼女の魅力に少しずつ惹かれていく。しかし、なかなか次のステップに進む勇気が出ない。
そんなとき、健二がやってきた。「兄ちゃん、相手に話しかけるなら、今がチャンスだよ。」背中を押されて、大輔は思い切って由美に声をかける。
「ねえ、由美さん。プロフィールタイムの後、少しお話しませんか?」
それに対して彼女はニコリと微笑み、素直に返事をしてくれた。それから二人は自然と会話が弾んだ。映画や趣味の話で盛り上がり、気がつけば周囲の喧騒が耳に入らなくなっていた。
披露宴の後、大輔は由美と連絡先を交換し、もっと話したい意思を伝えることができた。満足感を感じながら式場を後にする大輔の目には、健二が誇らしげに微笑んでいる姿が映った。
数日後、東京に戻った大輔は、由美と何度かデートを重ねることで彼女との距離を縮めていった。その中で、自然と自分自身の感情も整理され、健二との再会の恩恵を感じるようになった。弾けるような笑顔の彼女と過ごす時間によって、大輔は自分の世界が広がるのを感じていた。
ある日、由美とのデート中、大輔は真剣な顔で言った。「君に出会えたのは、実家へ帰ったからなんだ。あの結婚式で、兄弟の絆を再認識できたおかげだと思う。」
由美は、優しい目で大輔を見つめながら、少し驚いたように笑った。「それは素敵な話ね。私も、兄弟の大切さを感じているの。」
この言葉に、大輔はくすぐったい思いを抱えながら、彼女との未来を考え始めた。兄弟の絆が深まったことで、恋愛も深まる。一度は孤独だと感じていた心が、今は温かい光で満たされていることを知っていた。
再び家族のもとへ帰る日が待ち遠しい。大輔は、小さな奇跡が自分の人生を変えたことを実感し、次に会う時には健二に感謝の気持ちを伝えようと心に決めた。兄弟の絆が、彼の人生に新しい道を開いてくれたのである。