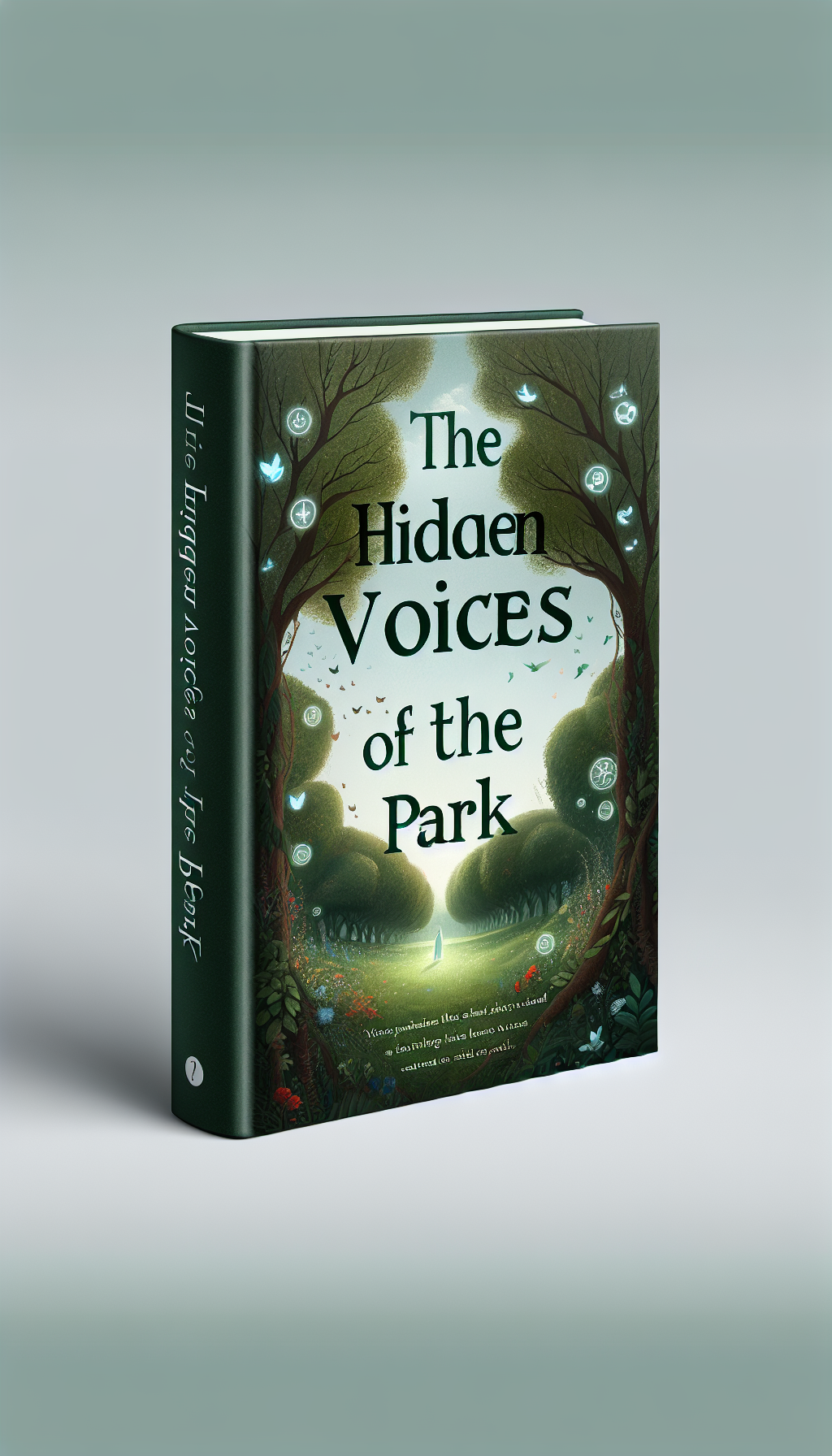深淵の中の真実
鈴木多香子は、その夜も眠れないでいた。不眠症はもう何年もの付き合いだ。彼女は毎晩、夫の大介が隣で穏やかに眠る姿を見つめることが日課となっていた。その間、頭の中には今日の出来事や、これからの予定、そしてふとした妄想が次々と現れ、混沌とした海のように押し寄せる。ある時は過去のトラウマに苛まれ、またある時は未来への不安に襲われるのだ。
その夜、彼女はリビングルームに降りていき、コーヒーを淹れた。カップから立ち上る湯気を見つめながら、彼女は何かが変わりつつあることを感じていた。誰も気付かないだろうが、彼女にはそれが分かる。まるで空気が重くなり、沈黙が痛みを伴うかのようだった。
翌朝、彼女はほとんど寝ていなかったにもかかわらず、夫にいつも通りの朝食を用意した。トースト、ベーコン、サラダ、スクランブルエッグ。それぞれの素材が美しく配置された皿を、優雅にテーブルに置く。大介は新聞を読みながら、片手でコーヒーを飲んでいた。多香子はその姿を見るたび、心が温まるような気がしていた。
しかし、その朝は何かが違った。大介の顔に浮かぶ微かな不安の影が、多香子の心理に深く刻みこまれたのだ。何が彼をそうさせたのか、多香子にはわからなかったし、聞く勇気もなかった。いや、もしかしたら、自分自身が怖かったのかもしれない。変化はいつも恐ろしいものだ。
その日の午後、多香子は少し街を歩いて気分転換を図ることにした。彼女は小さな書店に立ち寄り、本を手に取る。心理学のコーナーで足を止め、本の背表紙を指でなぞった。長年、心理学に関心を持っていた多香子だが、その知識は表面的なものに過ぎない。彼女はある本に手を止めた。「人間の心の闇」というタイトルが書かれたその本は、彼女の興味をそそった。
夜が訪れると、彼女の悪夢は再びやってきた。暗闇の中、彼女は陸と海の間の無限の境界線を彷徨っているかのような錯覚に陥った。大介の気配がない。彼女は目を覚ますと、隣のベッドが冷たくなっていることに気付いた。大介はその夜、突然姿を消してしまったのだ。
彼女はすぐに警察に通報し、友人たちにも連絡を取ったが、大介の行方は分からなかった。日が経つにつれて、彼女の不安と疑念は増していった。彼は自分を捨てたのか?それとも何か他の事情があったのか?答えは不明のまま、時間だけが過ぎていく。
そんなある日、彼女の元に一通の手紙が届いた。差出人は不明で、中にはただ一言「信じるな」という言葉だけが記されていた。彼女はその言葉をどう解釈すればいいのか、全くわからなかった。しかし、その言葉が彼女の心に深く刺さったことは確かだった。
それから数日後、彼女の家の前に黒い車が停まっているのに気付いた。車には誰も乗っていなかったが、その存在が異様で恐ろしかった。彼女は恐怖に駆られながらも、意を決して車の周りを調べ始めた。そして、車の中で見つけたものは彼女の心を凍りつかせた。大介の財布とスマートフォンがあったのだ。
警察は再び調査を開始し、多香子も自ら探ることを決意した。彼女は大介のスマートフォンを解析し、メッセージや通話履歴を調べ始めた。そこに現れたのは、彼が知らないうちに何者かと接触していた証拠だった。不審なメッセージのやり取りや、深夜の通話履歴が浮かび上がってきた。
あるメッセージには「計画は進行中です」という言葉があり、そのメッセージから、彼女はその正体不明の人物が彼女の心理の中に潜り込み、操っていたのではないかという恐怖を抱いた。そして、彼女はそのメッセージが指し示す場所にたどり着く。
それは荒れ果てた廃工場で、彼女は恐る恐るその中に足を踏み入れた。闇の中、彼女は大介を見つけた。縛られた彼の姿は衝撃的で、彼女はその瞬間、自分の心理が打ち砕かれる感覚を味わった。しかし、彼は意識があり、彼女に近寄らないように叫んだ。
「多香子、逃げろ!これ以上深入りするな!」
その叫び声と共に、彼女は再び手紙の「信じるな」という言葉を思い出し、震えながら家に戻った。再び訪れた静寂の中、多香子は一つの結論に至った。それは、大介を信じることではなく、自分の直感を信じることだ。
数日後、警察は廃工場での捜索を行い、大介を救出した。その背後には、組織犯罪が隠れていたことが判明し、多香子は夫を奪還できたが、心には深い傷が残った。闇の中で彼女が考えたのは、自分の心の中にもまた、一つの謎が潜んでいるということだった。先日、手に取った心理学の本を再び開いた彼女は、これからも解き明かされることのない、終わりなき謎を追い続ける決意を新たにした。