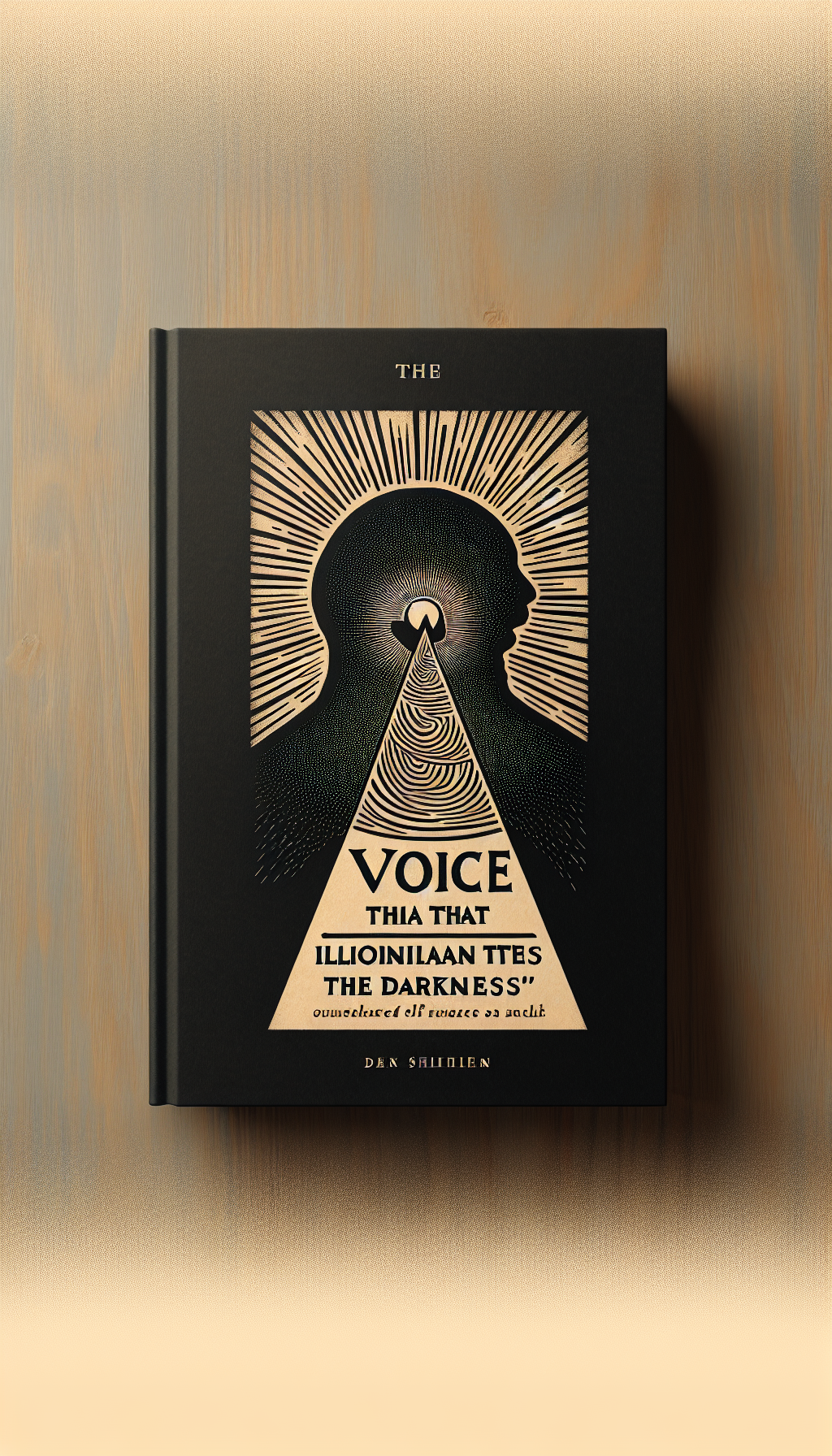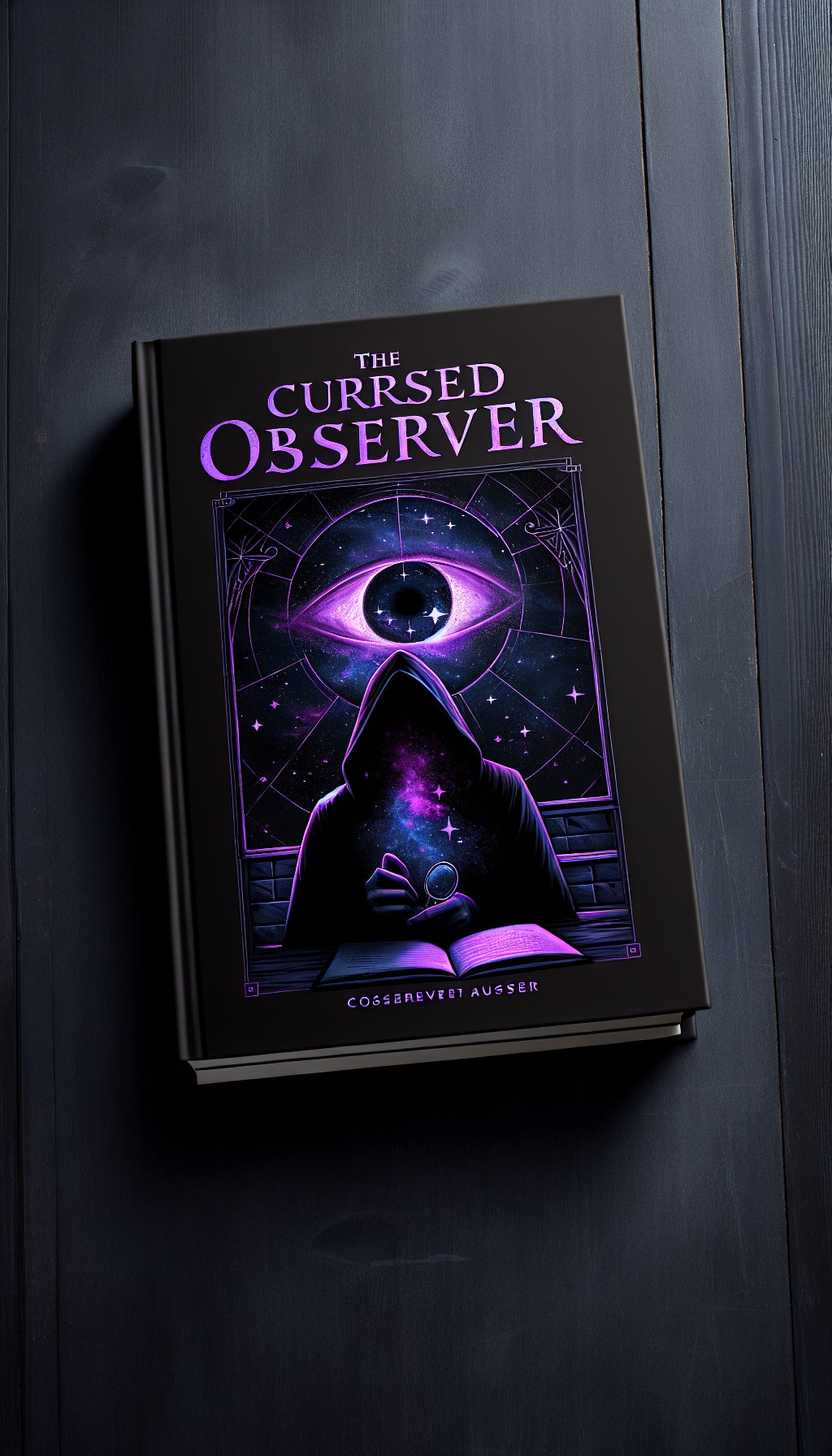時を越える旅
駅のホームに降りた瞬間、私は奇妙な感覚に包まれた。ここは昭和の中期、1953年の東京である。来訪者に過ぎない私が、霧のように現れたのは、タイムトラベルが可能となった未来の技術によるものである。
「何かを変えてはいけない。ただ、見届けるだけだ。」
科学者たちが口を揃えて警告する。だから、私は手袋の中に指を隠し、短い旅路を始めることにした。
この物語は、それが始まった日から数日前の出来事を元にしている。私は黒いスーツをまとい、灰色の帽子を深くかぶって、昭和の町並みに溶け込もうとした。
「あのう…お兄さん。」
突然、か細い声が耳に入ってきた。振り向くと、そこには小さな男の子が立っていた。7歳くらいだろうか。緩やかな笑顔を浮かべ、髪の毛はきちんと七三分けにされている。
「どうしたんだい、坊や?」
「お兄さん、あの時計を見たことがありますか?」
彼が指し示す先には、巨大な時計塔がそびえ立っていた。その時計は、午前中であるにもかかわらず12時を指していた。奇妙だったが、私はどうせ未来人だ。それより眼前の少年の表情に気を取られた。
「いや、初めて見るが。何か特別なことでも?」
少年はうなずき、さらに言葉を続けた。
「あの時計、動いているはずないんです。でも、見てください、動いてますよ?」
確かに、時計は動いているようだった。ただし、秒針が一瞬ごとに跳ねているのではなく、じわじわと進んでいる。それに気づいた瞬間、何かがおかしいと感じざるを得なかった。
「どうしてこの街に来たんですか、お兄さん?」
突然の質問に一瞬戸惑ったが、笑顔で答えた。
「ただの旅行者さ。少しこの時代の空気を味わいたくてね。」
少年はニヤリと微笑んだ。「時代の空気かあ。僕もそれが好きなんですよ。」
彼の大人びた返事に、私は何か不穏なものを感じ始めていた。少年に何か秘密があるのかもしれない。
「ねえ、お兄さん、僕のお父さんを探してくれませんか?」
予期せぬ申し出だったが、その頼りない声に無視することはできなかった。
「いいよ、坊や。でも、お父さんはどこにいるか知ってるんだろ?」
少年は首を横に振った。
「いいえ。最後に見たのは、あの本屋さんの前です。でも、それから既に三日経ってる。」
彼が指し示した本屋は、1950年代の象徴的な建物の一つで、少し薄暗く、たくさんの書籍が並んでいた。
一緒に本屋の前にたどり着いたが、中に入る前に男の子が私の腕を引いた。
「お兄さん、気をつけてください。中には不思議なことがいっぱいあるから。」
小さな手に握られた腕がどこか冷たく感じたが、私はその言葉を心に留めておいた。
本屋の中に入ると、古い本の香りが漂い、近くの棚には埃が積もっていた。店主らしき老人がカウンターに座っていた。
「何かお探しですか?」
低い声で尋ねられると、私は少年のことを話し出した。彼も無言で老人を見つめている。
「この坊やのお父さんを探してるんだけど、ここで見かけたことないかな?」
老人はしばらく考え込んでから静かに答えた。
「その少年…君は、時を越えてきたのかね?」
その言葉に私は驚きを隠せなかった。未来の技術がどこまで知れ渡っているのかと思いながら、老人の顔をじっと見つめた。
「はい、そうです」と少年は静かに答えた。「でも、お父さんがいなくなってしまったんです。」
予想外の展開に私はさらに混乱したが、老人は手を伸ばして一冊の古びた本を取り出した。
「この本を読みなさい。きっと道を示してくれる。」
本を受け取ると、その中から一枚の紙切れが滑り出てきた。そこには一つの住所が書かれていた。
「感謝します」と言って本屋を後にし、その住所に向かって歩き出した。少年も私の後を追った。
住所にたどり着くと、そこは崩れかけた小屋だった。それでも勇気を振り絞り、中に入ると、古びた家具と埃っぽい空気が漂っていた。その一角には一人の男性が、机に向かって埋もれて倒れていた。
「お父さん!」少年は叫びながら走り寄った。しかし、目の前の光景に息を呑んだ。
その男性の顔は、驚くほど少年と似ていた。しかし、歳を重ねたその顔には深い皺があり、目には何か悲しげな光が宿っていた。
「坊や…君は、時を越えてきたことを覚えていたのか?」
男性は静かに問いかけた。少年は首を縦に振り、涙を堪えながら答えた。
「お父さん、僕はずっとあなたを探していたんだ。」
その瞬間、彼の体から薄い光が放たれ、それは次第に薄れていった。
私はその瞬間を見逃すことなく目に焼き付けた。不思議な時の巡りに立ち会った私は、すべてが一瞬の出来事であるかのように感じた。
旅の終わりを告げる笛の音が遠くから聞こえ、私は再び未来へ戻るための準備を始めた。
時代を越えて巡り合う人々の物語。その一端に触れたことで、私は新たな謎とともに未来へと帰ることを決意した。