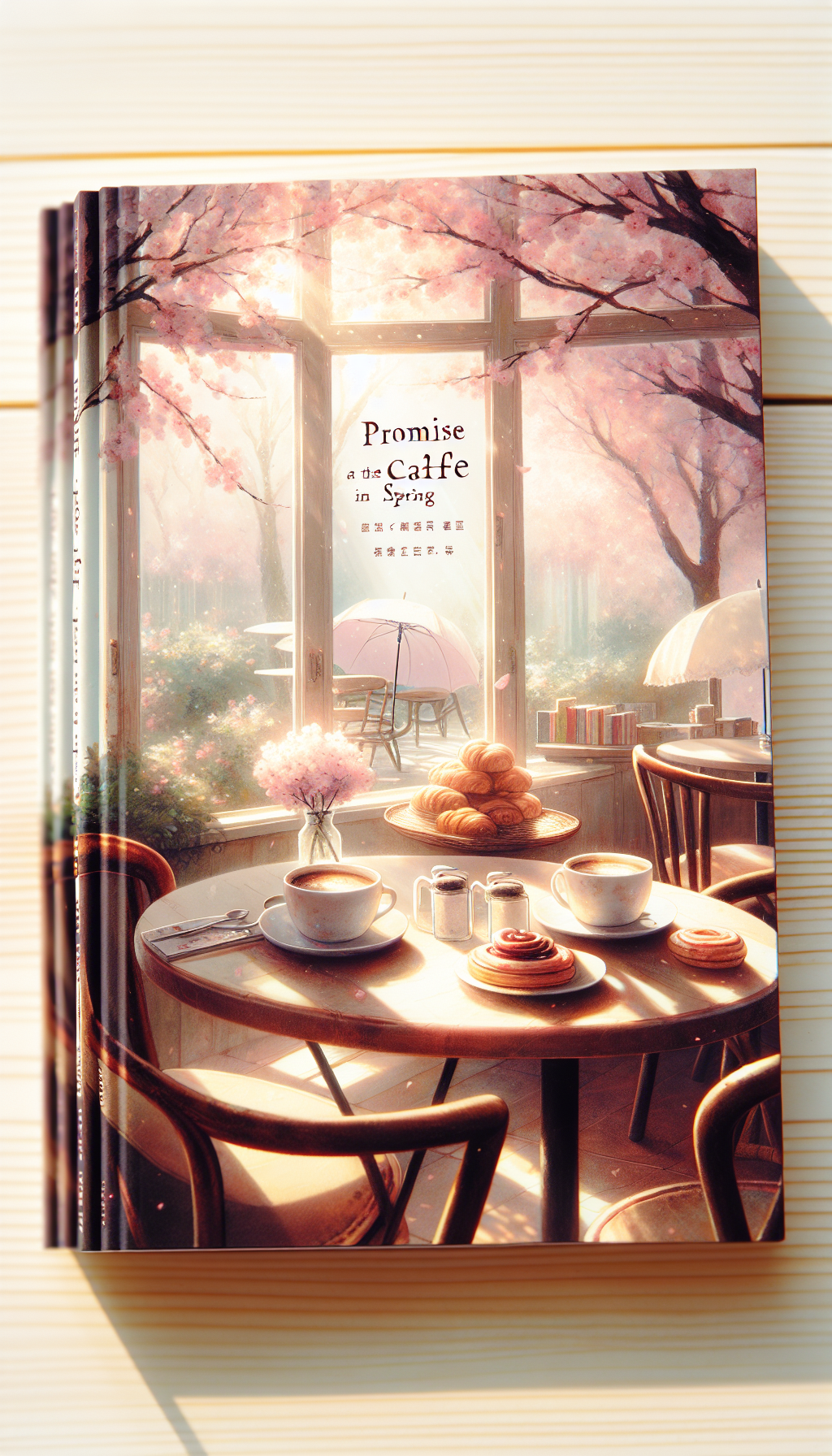桜舞う春の恋
陽気な春の日、桜が舞い散る公園で、美術大学に通う若い女の子、由紀はベンチに腰掛けていた。彼女の手にはスケッチブックがあり、満開の桜の木を描いている。周囲は花見を楽しむ人々で賑わっているが、由紀は一人静かに自分の世界に浸っていた。
そんなとき、彼女の視界に一人の男が入ってきた。彼は派手なチェックのシャツを着て、にこやかに周囲を見回しながら、仲間たちの中に混じっていた。彼の名前は大樹、大学の同級生で、サッカー部のエース。由紀は彼にあまり関心を持っていなかったが、その明るい表情に何か惹かれるものを感じた。
次の日、由紀は大学のキャンパスでまた大樹に出会った。彼は仲間たちと楽しそうに話していたが、由紀の目に入った瞬間、ふっと視線が交わった。心臓がドキッとする。由紀はすぐに目をそらし、急いでその場を離れた。彼女はあまり人間関係に得意ではなく、特にモテる男に接近する勇気はなかった。
そんなある日、大学の授業中に由紀は大樹に声をかけられる。彼は彼女のスケッチに興味を示し、「良い絵だね。これから展示会に出さないの?」と聞いてきた。由紀は驚きながらも、少し照れくさくなりながら「まだまだ未熟だから」と答えた。
大樹は笑顔を崩さず、「自信を持てよ。友達のサッカーの試合を応援するみたいに、由紀の絵も応援するよ」と言った。由紀は思わずほころび、少しだけ彼に心を開くことにした。
それから数週間、二人の距離は徐々に縮まっていった。授業後には一緒に話したり、時には大学のカフェでコーヒーを飲んだりするようになった。大樹は由紀の絵に対する情熱や努力を理解し、彼女自身の内面に興味を持ってくれる存在だった。
ある日、大樹が由紀に提案した。「今度一緒にサッカーを観に行かないか。応援してくれると嬉しいんだ」。由紀は内心ドキドキしながらも、彼の誘いを受け入れた。サッカーはそれほど得意ではなかったが、彼と過ごす時間がもっと増えるなら、と思ったからだ。
試合の日、由紀は大樹の応援席に陣取った。周囲は熱気に溢れ、選手たちのプレーに歓声が響き渡る。大樹はフィールドに出てプレーする姿に真剣な表情を浮かべていた。彼の活躍を見守る中、由紀は心の中で応援を送る。
試合が終わった後、大樹が由紀のところに駆け寄ってきた。「見た?あのゴール!」と叫ぶ彼の顔には満足感が溢れていた。由紀は微笑み、「すごかったよ、大樹!あなたが得点した瞬間、驚いた!」と返した。
その後、二人は更に仲良くなり、休日を共に過ごすことが日常になっていった。大樹といると、由紀は自然に笑顔になり、リラックスできる自分を感じていた。
ある晩、公園を散歩しながら、由紀はふと素直な気持ちを言葉にした。「最初は、サッカーとか全然興味なかったけど、大樹と一緒だと楽しくなった。ありがとう」と言った。大樹は少し照れくさそうに、でも嬉しそうに笑って返した。「由紀といると、サッカー以上に楽しいよ。」
その夜の帰り道、二人は星空を見上げていた。大樹がポケットから小さなスケッチブックを取り出し、由紀に見せる。「これ、由紀のサッカー応援の絵だよ。勝手に描いてみたんだ。気に入るかな?」由紀は驚きに目を大きくし、それを受け取った。大樹の素朴な絵は彼女の幸せな日々を見事に映し出していた。
その瞬間、由紀は彼の存在がどれほど大切かを再認識した。それでも、まだ告白する勇気はない。二人の関係がこのままでいることを恐れていたからだ。
時間は流れ、由紀は春の展示会に向けて一生懸命絵を仕上げた。大樹も友達と一緒に応援に来ると約束してくれた。展示会の日、由紀は緊張しながら自作品を見つめた。それが彼女の情熱の結晶であり、彼女のすべてだった。
その日、展示会場に大樹が現れる。由紀は彼の元へ駆け寄って、「見に来てくれてありがとう!この絵、私の気持ちが詰まってるの」と嬉しそうに言った。大樹は真剣な表情でのぞき込み、「素晴らしいよ、由紀。これは本当に君らしい」と静かに言った。
展示会が終わり、人々が去った後、由紀は一人ベンチに座り込む。大樹も隣に座り、「一緒に帰る?」と声をかけた。由紀は「うん、帰ろう」と言いつつ、心の中で勇気を振り絞り、「大樹、私、あなたのことが好き」と言った。
瞬間、時が止まったように感じた。大樹は目をぱちくりさせ、驚いた表情を浮かべた。しかし、彼はすぐに微笑んで、「それ、僕もだよ」と答えた。由紀は自分の言葉が現実であることを信じられなかったが、同時に安心感に包まれた。
春の夜、二人は星の下で、新たな一歩を踏み出すことになる。絵とサッカー、異なる世界で結びついた二人が、共に歩む日常が始まったのだった。