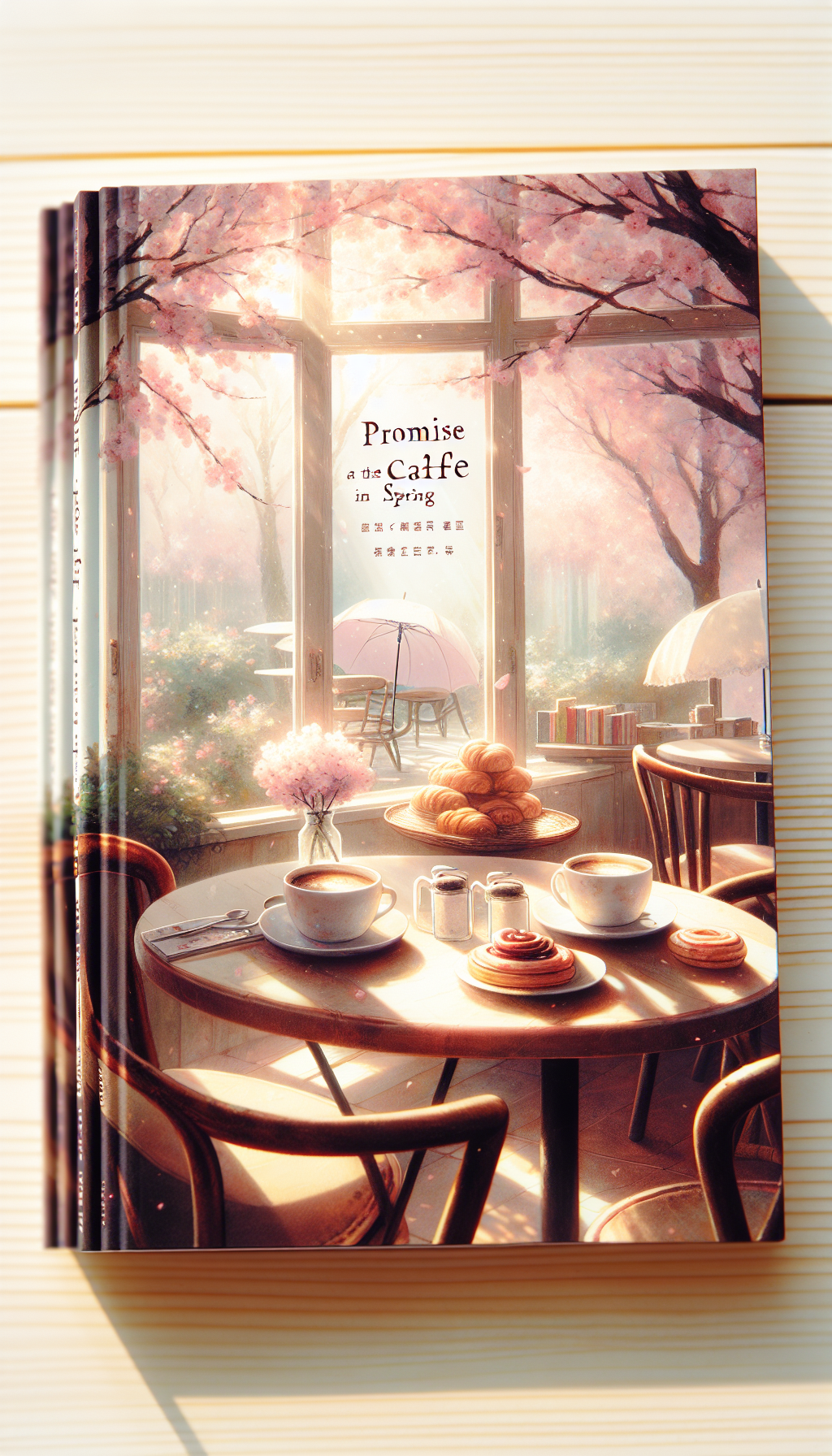支え合う三人
夏の終わりが近づく、静かな町の小さなカフェ。友人たちが集う場所であるそのカフェには、長年の友情を育んできた三人組、リナ、ユウキ、そしてミキがいた。この三人は、互いに支え合い、笑い合い、時にはケンカをしながらも、いつも一緒にいた。
ある日、リナがカフェに現れると、二人が何やら楽しそうに話をしているのを見つけた。彼らは、来週の週末に開かれる町の秋祭りの準備について話しているようだった。その祭りには、近隣の町からも多くの人が集まるため、特別なイベントがあるという話だった。
「ねえ、私たちも何か出店しない?」リナが言った。ユウキは目を輝かせた。「それいいね!何を売る?」ミキは微笑んで考え込み、「私たちの特製スイーツはどうかな?」と言った。
リナは目を大きく開いて、「それいい!私たちのケーキをもっと多くの人に食べてもらおう!」と乗り気になった。こうして、三人は秋祭りに向けてスイーツの出店を決定した。
だが、祭りの準備が進む中で、リナはあることに気づく。ユウキが最近、異様に忙しそうで、無理をしている様子が続いていたのだ。彼は自分の仕事に加えて、祭りの準備も任されているようだった。リナは心配になり、ユウキに声をかけることにした。
「ユウキ、無理してない?」と尋ねると、ユウキは少し驚いた顔をして、「大丈夫だよ、僕はこれくらいのことで挫けるような男じゃないから」と笑顔を見せた。リナはその返事が本心でないことを感じ取ったが、彼を追い詰めるのは良くないと思い、しばらく様子を見ることにした。
祭りの準備が進む中、ユウキはますます忙しくなってしまった。最後の週末は、彼が全くカフェに来ることもなくなり、リナとミキは彼を心配する日々が続いた。そして祭り当日、ユウキはついにカフェに姿を現した。
「ごめん、遅れた!」と彼は明るく言ったが、その表情には疲労がにじんでいた。ミキとリナは、ユウキにスイーツを作る手伝いをしながら、彼の様子を気にかけた。
「今日は俺たちの出店が一番人気になるといいな!」とユウキは元気に言ったが、その言葉には少し無理があるように感じられた。リナは思い切って言った。「ユウキ、無理しないで。本当に大丈夫?」彼は一瞬驚いた後、「本当に大丈夫だってば。気にしないで」と言って笑った。
しかし、その笑顔がどこかギクシャクしているのをリナは見逃さなかった。そして、出店の準備が整い、いよいよ祭りが始まった。カフェの前には、多くの人々が行き交い始め、リナたちはスイーツの値札を掲げて呼び込みをする。
「美味しいケーキ、種類豊富です!」リナが大声で叫ぶと、数人が足を止めてくれた。「一ついただきます!」とお客が言うと、ユウキは笑顔でケーキを手渡したが、その瞬間、彼の表情がパッと暗くなった。
「ユウキ、大丈夫?」リナは心配になり、ユウキに近寄った。「本当に大丈夫!ただ、ちょっと疲れただけ!」と彼は言ったが、その声には元気が感じられない。
祭りが進む中、リナとミキはユウキを支えるために、できる限り手伝いを行った。たくさんのお客が来て、楽しい雰囲気が漂う中、ユウキの様子はますます疲れていくように見えた。そんな中、ふと、リナは出店の裏でユウキが一人で休んでいるのを見つけた。
「ユウキ、大丈夫?」と声をかけると、彼はふと顔を上げた。「ごめん、ちょっと一息ついてた」と呟く。リナは彼の横に座り、「あなたが頑張りすぎてるから、心配なんだ。何かあったらちゃんと教えて」と優しく言った。
するとユウキは、少し沈黙の後に口を開いた。「実は、最近仕事のことで悩んでて。本当は、こんなこと言えないと思ってたけど、やっぱりリナとミキには頼りたかった」と言った。リナは彼の手を握り、「いつでも言って。私たちは友達なんだから、助け合おうよ」と返した。
その瞬間、ユウキの表情が少し穏やかになり、「ありがとう、リナ。本当に助かる。気づかせてくれてありがとう」と微笑んだ。リナは心が温かくなるのを感じた。
秋祭りは進み、三人の出店も大盛況を迎えた。周囲の人々と笑い合い、スイーツを作り、心の中の重荷も少し軽くなった。祭りが終わり、帰り道を歩きながら、リナはふと立ち止まった。「これからも、こうして互いに支え合っていこうね」と言った。
ミキとユウキは「もちろん!」と返事をし、三人は一緒に大きな笑顔で町の夜空を見上げた。新たな友情の深まりと、これからも続く日々の中で、彼らはもっと強く結びついていくのだろう。