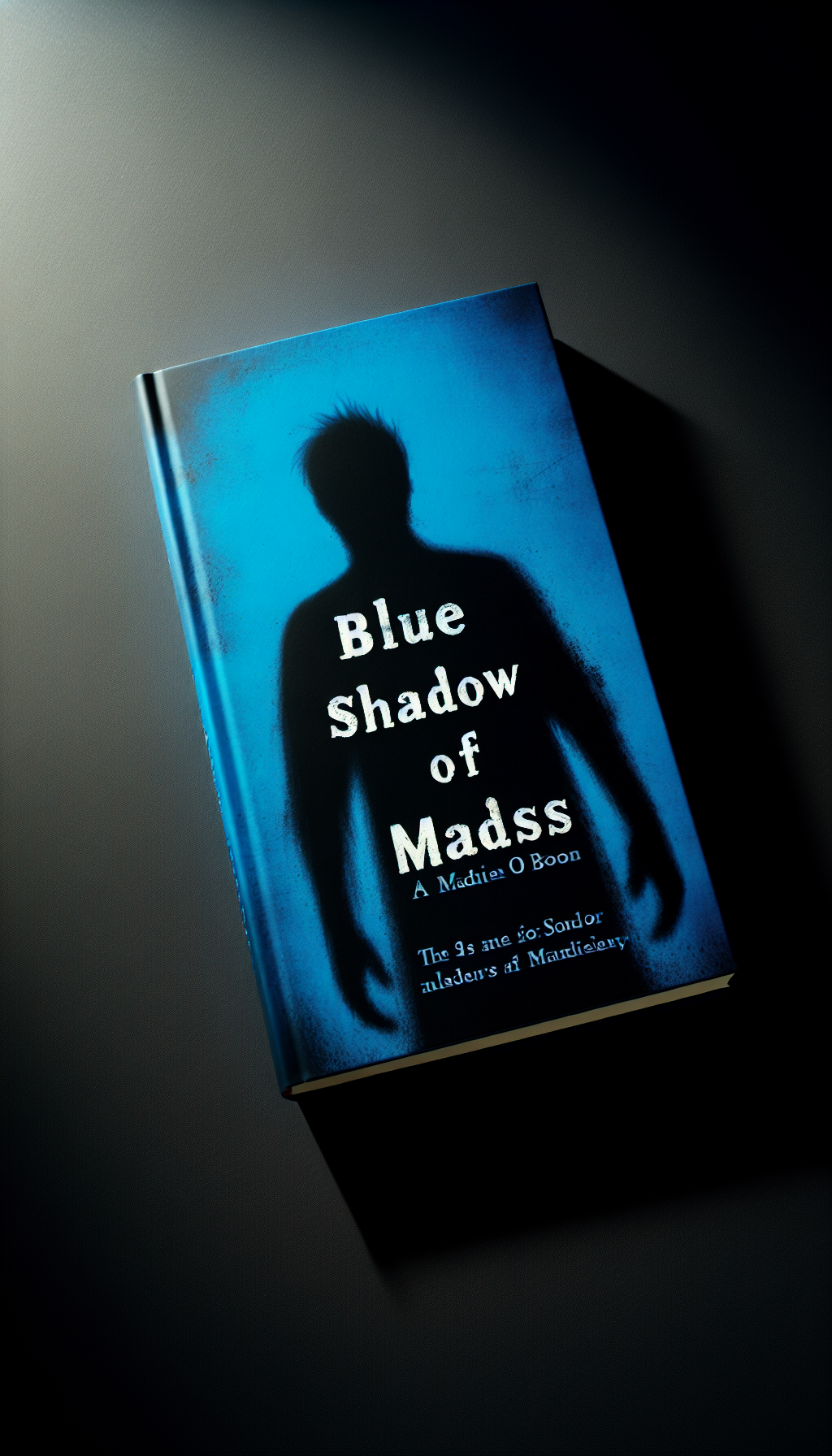影の呪縛
夜が訪れ、静まり返った街の片隅にある古びた洋館。昔の栄光を思わせる重厚な扉が音も無く開き、入る者を拒むかのように冷たい風が吹き抜けた。ひとりの若い女性、佐藤明美は、その屋敷の前に立っていた。彼女は大学の心霊研究会に所属しており、遺跡に関するレポートを作成するため、町に伝わる怖い話の検証をすることになったのだ。
この洋館には、長い間使われていないという噂と共に、住人が突然失踪したという怪談があった。興味をそそられた明美は、友人たちに頼んで一緒に来る予定だったが、皆の都合が合わず、一人で屋敷に足を踏み入れることになった。心の中で不安が広がるが、何か大きな成果を求めていた彼女は、自分を励ました。
館内は薄暗く、塵と蜘蛛の巣が絡まりついていた。時間が止まったかのような静寂の中、明美は懐中電灯を持ちながら、ゆっくりと足を進めていく。リビングには年代物のソファやテーブルが残されており、どこか悲しげな雰囲気が漂っていた。彼女はその場所に何かが住み着いている気配を感じたが、それが何であるかを考えぬようにした。
ふと、階段の上からかすかな音が聞こえた。明美は耳を澄ませながら、音のする方へと向かう。階段の一段一段を踏みしめるたびに、軋む音が響き渡り、彼女の心臓は高鳴った。上に辿り着くと、薄暗い廊下が広がっていた。ドアが数枚並ぶ中、一番奥の部屋から、かすかに光が漏れていた。
気を引き締めてそのドアを開けると、小さな書斎があった。古い本が所狭しと並び、机の上には一冊のJournalが置かれていた。明美は興味をそそられ、そのページをめくった。内容は、かつてここに住んでいた男性が家族を失い、その悲しみと恐怖を綴ったものだった。彼の家族は、ある日突然、消えてしまったのだと。最後のページには、「彼らは私の中にいる、逃げられない」という言葉が書かれていた。
その瞬間、明美の背筋を凍るような冷たい空気が走り抜けた。彼女は直感的に、この家には彼の家族の魂が何かしらの形で存在しているのだと思った。明美は急いで部屋を出ようとしたが、突然、ドアが音を立てて閉じてしまった。パニックに陥り、ドアを叩くが、全く反応が無い。
背筋に冷たい汗を感じ、彼女は一瞬立ち尽くした。そこに何か影が見えた。薄暗い隅から、かすかな笑い声が響いてくる。明美は恐れを抱きつつ、懐中電灯を向けるが、何も見えなかった。しかし、その笑い声は彼女の耳から離れず、どんどん大きくなっていく。彼女は感覚が麻痺していくのを感じた。
突然、目の前に子どもの影が現れた。驚きと恐怖が入り混じり、明美は後ずさりした。子どもは、悲しげな目で彼女を見つめていた。家族を失った悲しみが、彼から伝わってくる。明美は彼に何か言おうとしたが言葉が出なかった。
その時、部屋中が揺れ動く感覚がした。明美は、突然の地震かと錯覚したが、影はどんどん増えていき、他の家族も現れた。彼らは一見無邪気に見えたが、その目には絶望と憎しみが宿っていた。周囲は暗くなる一方で、彼女は混乱し、釘付けになってしまった。
「助けて…私たちと一緒にいて…」
その声が明美の耳に響いた。彼女は逃げ出したい気持ちと、子どもたちの悲しみに引き寄せられる気持ちの間で激しく揺れ動いた。彼女が一歩踏み出すと、驚くほどの力で彼女の腕が引き寄せられる。明美は必死に抵抗しようとしたが、影たちは彼女の心の奥深くに囁きかけ、脱出する道を封じた。
恐怖に耐えられず、明美は意を決して叫んだ。「私は帰る!あなたたちを助けられない!」
その瞬間、全ての影が一斉に消えた。彼女はドアが開かれ、自分を飲み込むような暗闇から解放された。驚いて振り返ると、子どもたちの悲しみの目が遠くで彼女を見ていた。その顔は、今もなお彼女の心に焼き付いている。
明美は何とか屋敷を抜け出し、外に出ると息を切らして立ち尽くした。彼女はもはやこの場所を受け入れることはできなかった。何かが、彼女の中に残った。街の灯りを見ながら思った。「私はもう一度訪れることはないだろう」と。屋敷が待っていることを知りつつ、彼女は足早にその場を立ち去った。