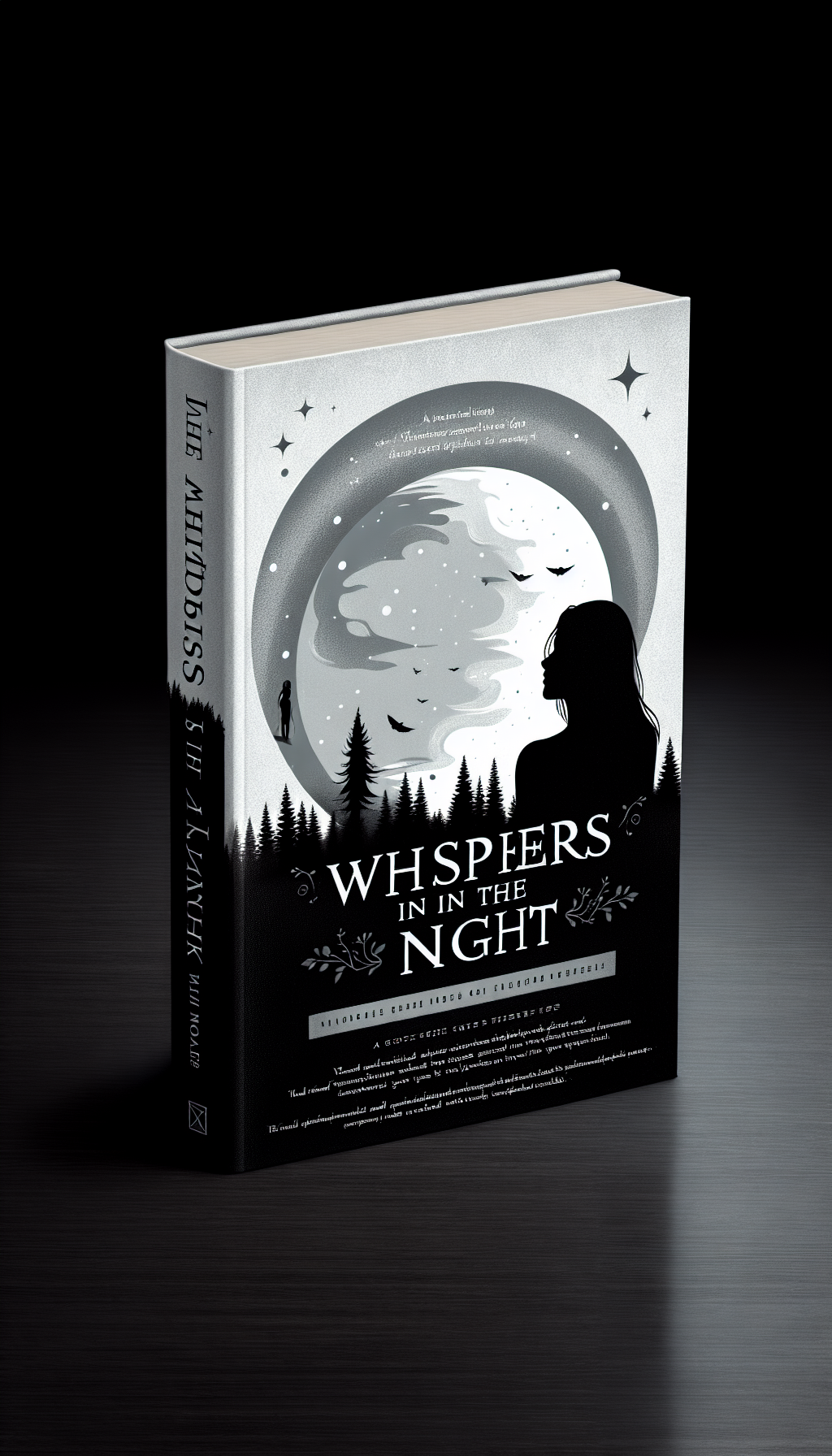魂の迷宮
霧の立ち込める夕暮れ、森の奥にひっそりと佇む古びた館がある。この館は村人たちの間で「不思議の館」と呼ばれており、誰も近寄らない。理由は、この館に入った者が二度と戻らないという伝説があるからだ。
その伝説に挑むべく、若い探検家のカンナは一人で館を訪れた。彼女は好奇心旺盛な性格で、未知のものに対する恐怖よりも興奮を感じるタイプだった。手には懐中電灯とカメラを持ち、重たい木製の扉を押し開く。扉はギギギと音を立て、異様な冷気が彼女の顔に当たる。
中に入ると、広いホールが広がっていた。天井は高く、壁には年代物の絵画が掛かっている。ホールの中央には、巨大なシャンデリアが吊るされていた。しかし、全てが薄暗い。カンナは懐中電灯を点け、辺りを照らしながらゆっくりと歩を進めた。
突然、廊下の奥からかすかな声が聞こえてきた。耳を澄ますと、それは何かを囁くような声だった。カンナの心臓は一瞬、早鐘のように打ち始めたが、すぐに冷静を取り戻した。彼女はその声の方向へ進む決意をした。
廊下を進むと、まもなくして一つの部屋にたどり着いた。部屋の扉は少し開いており、中から淡い光が漏れている。カンナはそっと扉を押し開けて中に入った。部屋の中には、古い書物が無造作に積み重ねられた机と、壁一面にかかる異国の地図があった。
「これが…不思議の館の秘密かしら?」
カンナは机に近づき、一冊の書物を手に取った。書物の表紙には、見たこともない文字が刻まれていた。中をめくると、ページの一部に微かな血痕があった。彼女は驚きのあまり、書物を手から滑らせてしまった。
その瞬間、部屋が暗転し、異様な冷気とともに無数の影が現れた。カンナは身を固くし、懐中電灯を影に向けて照らしたが、影は逃げることもなく、むしろ彼女に向かって近づいてくるように見えた。影は形を変え、次第に人間の姿を取り戻していった。
「誰…あなたたちは誰なの?」
カンナの声は震えていた。影たちは答えることなく、ただじっと彼女を見つめていた。そのうちの一つが口を開くと、不思議な言葉で囁き始めた。それは彼女がこれまで聞いたことのない言語だったが、不思議なことに意味が理解できた。
「私たちはこの館に囚われた魂。お前もここから出ることはできない。」
その言葉が響くと、カンナは突然足元の感覚を失った。壁や床が溶けるように変形し、彼女の身体は未知の力に引き寄せられるようにして落ちていった。次に目を覚ますと、彼女は真っ暗な部屋の床に横たわっていた。
「ここはどこ?」
暗闇の中で手探りしながら立ち上がろうとするが、足が不自由なように感じられた。手を伸ばすと、質感の異なる冷たいものに触れた。その感触はどうやら鉄のバーのようだ。
「私は…檻の中にいるの?」
その瞬間、カンナは恐怖に襲われた。声を出して助けを求めようとするが、声は全く出ない。それどころか、体が徐々に力を失っていくのを感じた。
突然、暗闇の中に一筋の光が差し込んできた。光の先に浮かび上がったのは、人影だった。その人影はカンナに近づき、無言でその目を覗き込んできた。目の奥には、彼女の知り得ない異世界の風景が広がっていた。
「ここから出る方法を教えて!」
心の中で叫ぶと、その人影は微かに微笑み、再び不思議な言葉を囁いた。しかし、その言葉は完全には理解できなかった。
次の瞬間、カンナの周りの空間が揺らぎ、再び彼女は意識を失った。
目が覚めると、あの古びた館のホールに戻っていた。何事もなかったかのように、すべては元通り。カンナは深く息を吸い込むと、その場から逃げるように飛び出した。
外に出ると、日は完全に暮れており、森は静まりかえっていた。彼女は無我夢中で村に戻り、家に駆け込んだ。村人たちは彼女の無事を見て胸をなでおろした。
「やっぱり、不思議の館には何かがいる…。」
彼女の言葉に、村人たちは頷いた。カンナはその夜、深い眠りについた。しかし、彼女の中にはあの不思議な囁き声がずっと鳴り響いていた。
そして、再び訪れることはなかったが、彼女の心には永遠にその記憶が刻まれていた。それが何であったのか、彼女にも分からなかった。ただ一つ確かなことは、あの館が本当に「不思議」な存在であるということだった。
不思議の館の伝説は、この村で永遠に語り継がれていくことだろう。そして、誰もがその謎に挑むことなく、その神秘のままに。