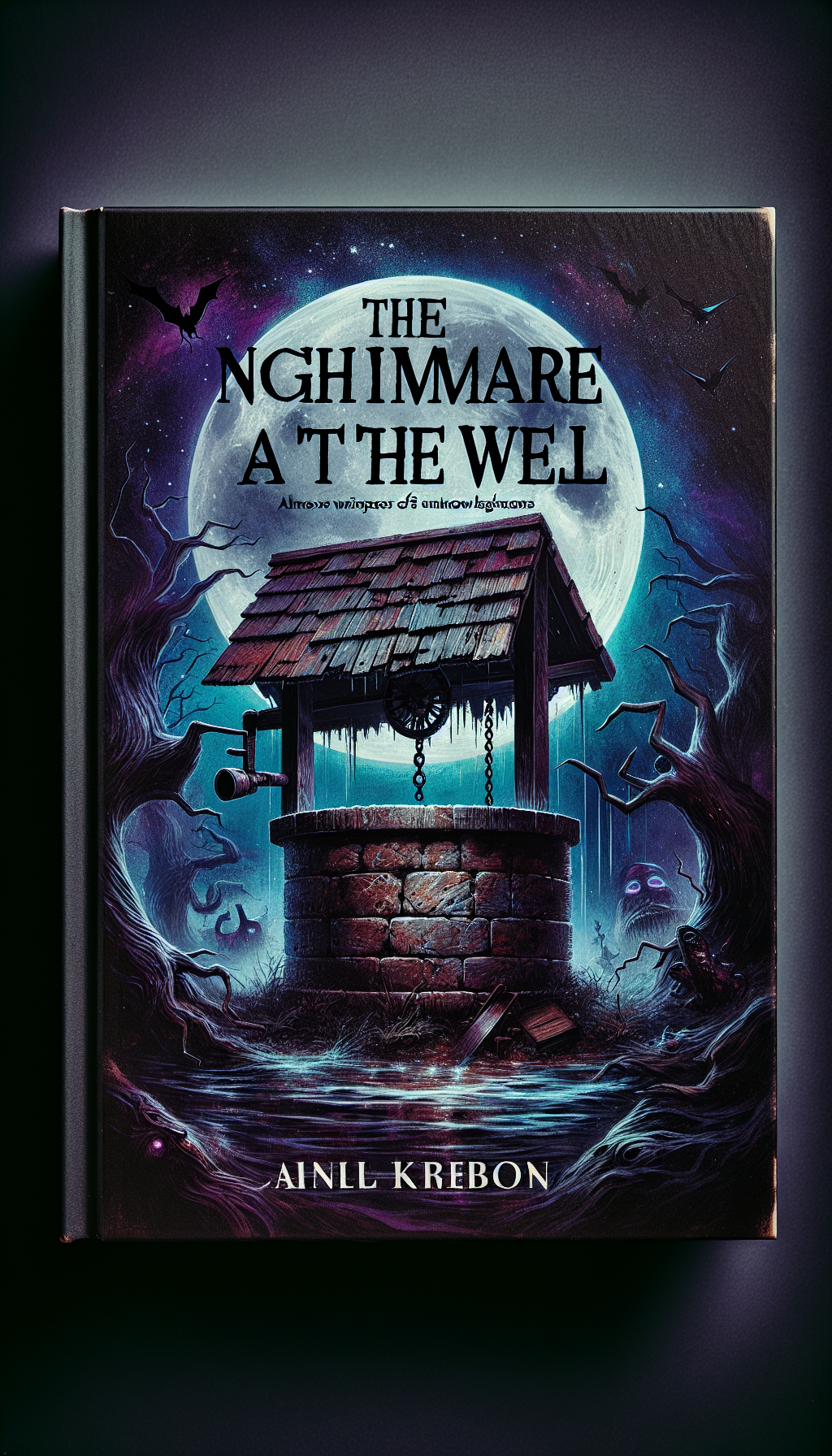呪われた静寂
夜の静寂が辺りを包み込む中、小さな村の一角に位置する古びた家があった。その家は誰も住んでおらず、村人たちからは「呪われた家」と呼ばれていた。数十年前、家の中で起きた悲劇的な出来事が語り継がれ、誰もその場所に近づこうとはしなかった。しかし、ある大胆な若者たち、タケシとユミはその家に興味を抱き、探検することに決めた。
彼らは夕暮れ時、その家の前に立ち尽くした。玄関の扉はぼろぼろで、やがて壊れかけた木が音を立てて彼らを迎え入れた。中に入ると、薄暗い廊下が彼らを迎え、埃にまみれた家具や剥がれかけた壁紙が過去の名残を感じさせた。タケシの怖れを隠しきれない声が響く。
「こんなところ、本当に入るのかよ?」
ユミは明るく微笑んだ。「何も起こらないよ。ちょっとだけ調べてみよう!」
二人は家の奥へ進んだ。そして、彼らはリビングルームに辿り着いた。そこには大きな古いソファと、壊れた額縁に飾られた家族の写真があった。写真をじっと見つめるタケシの目が、何かに引き寄せられるように感じられた。そこには、子供たちが笑顔を浮かべ、見知らぬ女性が佇んでいた。彼の心に不穏な感情が湧き上がる。
「これ、誰なんだろう?」タケシは写真を指差した。
「おそらくこの家の昔の住人じゃない?」ユミは好奇心に満ちた眼差しを向けた。
続いて、彼らは家の隅々を探査した。どこもかしこも無気味な雰囲気が漂っていたが、彼らはそれを楽しんでいるかのようだった。そんな中、ユミは地下室のドアを見つけた。「行ってみようよ!」
躊躇しつつも、タケシはユミに従った。地下室のドアを開けると、暗闇が広がっていた。ユミはスマートフォンのライトを照らし、階段を下り始めた。タケシも後に続き、心臓がドキドキするのを感じる。
地下室には古びたロッカーが並び、ワゴン車のエンジン音のような音が遠くから聞こえてくるようだった。彼らが一つのロッカーを開けると、中には何もなく、ただの空っぽの棚があった。しかし、次のロッカーを開けた瞬間、ユミが驚いた声をあげた。
「タケシ、見て!ここに日記がある!」
彼女が取り出したのは、昔の家族の生活が記された薄い本だった。ページをめくると、彼らは家庭の幸せな様子が記された日々を垣間見た。しかし、ページが進むにつれ、日記の内容は次第に暗くなっていった。親の不仲や、次第に家族が心を閉ざしていく様子が綴られていた。
「何かおかしいな…」タケシが呟く。
その時、ふとタケシの目に、その日記の最後の頁が飛び込んできた。そこには、「私は最後の夜を待っている」と書かれていた。その言葉が彼の心に不安を植え付ける。
「もしかして、この家で最後に何か怖いことが起きたんじゃ…?」タケシは手汗を感じて言った。
ユミがその言葉に心を痛めたと理解すると、急に地面が揺れるような感覚がした。二人は驚き、振り向くと、地下室のドアが一人でに閉まっているのが見えた。
何が起こったのか分からないまま、タケシはすぐにドアを開けようと試みた。しかし、ドアは固く閉ざされていた。「開けてくれ!」叫んだが、返事はない。すると突然、周囲に冷たい風が吹き、一気に異様な気配が漂い始めた。
恐怖に駆られ、二人は地下室の中を探し始めた。すると、背後から声が聞こえる。「私を戻して…」冷たい声が響く。その声は明らかに女性のもので、ユミを恐怖でじっと見つめる。
「ど、誰?!」タケシが言ったが、声はどんどん近づいてきた。
「私を、もどして…あなたたちには無理よ」
振り向くと、そこには写真の中の女性が立っていた。彼女の顔には悲しみが漂い、眼差しは恨めしさを宿していた。絶望的な状況に、タケシとユミは言葉を失った。
「あなたたちが私の家を訪れたから、私は戻れなくなった」女性の声が続く。「でも、あなたたちがここに留まることで、私の運命を変えることができるの」
タケシは恐怖で動けず、ユミは彼を振り向き、同じように怯えていた。なぜ彼女がこんな存在になってしまったのか。だがその説明を求める暇もなく、地下室は急速に薄暗くなり、冷たい手が彼らの背中に触れた。
その瞬間、タケシは気を失い、次に目を覚ましたときには、地下室には誰もいなかった。日記は床に、ページは風に舞っていた。運命の選択をすることもできず、彼の目の前にはただ、再び静寂が訪れていた。