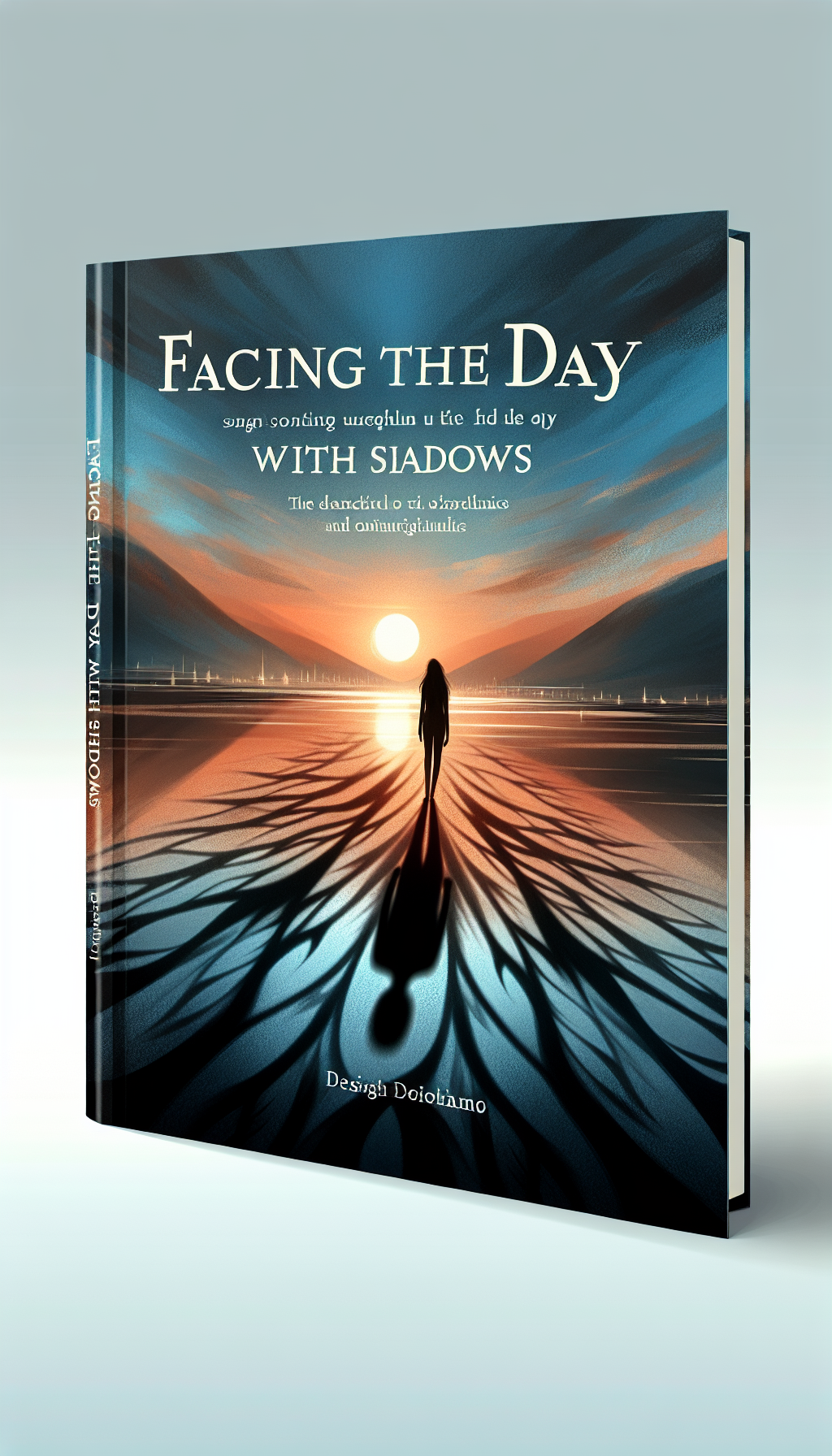静かな恐怖
ある雨の夜、東京の静かな住宅街で一つの悲劇が起きた。近所の高橋家が、夜の静寂を破るように警察のサイレン音に包まれた。高橋雅人(たかはしまさと)は、昼間から外出していた妻の怜子(れいこ)が帰宅しないことに不安を感じていた。彼はスマートフォンの画面を何度も見つめ、電話をかけても彼女に繋がらなかった。
高橋家がある住宅街は、年齢層が高く、子どもたちが遊ぶ姿も見られない静かな場所だった。ここでは物音ひとつしない夜が続いており、住民たちもお互いを知るような関係ではなかった。珍しいことに、隣の佐藤家の犬が鳴き声を上げていた。
警察が到着したのは深夜のことで、警官たちは高橋家の周りを囲み、捜査を開始した。雅人は心配になって、自ら調べ始めた。高橋家の近くには、数日前に引っ越してきたばかりの新しい住人、佐々木一家がいた。奇妙なことに、その家からは怜子の声が聞こえたような気がしてならなかった。しかし、雅人が勇気を振り絞ってドアをノックしても、そちらからの反応はなかった。
警察は情報を集め、周囲の住民から尋ねて回った。佐々木家のことを知っている者は少なく、また新しい住人の素性がわからないと言った。雅人はますます不安になり、怜子が行方不明になった理由に心を巡らせた。彼は、怜子がこの町に来た際に、隣人に挨拶をしている様子を思い出した。慎ましい印象を与え、どこか控えめな彼女は、近所付き合いにも積極的だった。
「うちの奥さんが戻ってこないんです……」雅人は警官に言った。警官は肩をすくめ、「もう少し時間を待ってみてください。心配しないで」と言ったが、雅人の心には不安が渦巻いていた。
一夜明け、雅人は自宅の周りを調べることにした。雨が上がり、空は曇っていた。しかし、そのどんよりした天気を吹き飛ばすかのように、雅人の心は焦燥感に満ちていた。道端に倒れたおさかなの死体や、さまざまなゴミが散乱している様子は、妙に現実感を帯びていた。
その時、近所の主婦が雅人に声をかけてきた。「高橋さん、奥さんのことはどうなりましたか?」主婦の表情に不安が映っていた。少し気を緩めた雅人は、尋ねられたことで、ひとつの切迫した情報を得ることができた。「佐々木さん、最近何か変なことを言ってたみたいです。聞いた話によれば……」
雅人はその言葉にびくりとした。佐々木家についての情報をもっと調べなければならなかった。彼はその晩、近所の住民に聞き込みをしながら、佐々木家へと向かった。
「おい、佐々木さん!」雅人はドアを叩いた。しかし、応答はなかった。雅人は思い切ってドアを開け、中に入った。家の中は薄暗く、静まり返っていた。冷たい空気が漂い、何か不穏な音がする。彼を引きつける何かがあった。
と、その時、雅人はある音に気付いた。地面から微かな水の滴る音が聞こえる。音のする方に目を向けると、階段の下に何か重い物があった。それは怜子の携帯電話だった。彼は息を呑んだ。携帯電話のバックドアの破れたシールや少し湿った状態は、何かが起きたことを示唆していた。
その瞬間、後ろから声が聞こえた。「あんた、何してるの?」振り返ると、佐々木が立っていた。驚きと恐怖が交錯し、雅人は思わず携帯を握りしめた。「怜子はどこにいるんだ!」雅人は叫んだ。
「彼女は……」佐々木は言葉を濁して、自分のスマートフォンを取り出し、何かをし始めた。「ここにいる必要はない。お前が来た理由は分かってる。さっさと帰れ。」その言葉はまるで怜子への脅迫のようだった。
雅人は恐怖心を押し殺し、真実を求めた。「怜子がどこにいるのか教えてくれ、お願いだ!」
その時、佐々木の表情が変わった。「彼女は……時々、ここに訪れていた。」彼の口から出た言葉で、雅人は心臓が止まるほどの恐怖を感じた。「なぜそんなことを……」
「彼女は私を必要としていた。お前に対する不満を私に打ち明けていたんだよ。」
雅人は混乱が広がる。怜子が何かを緊急に伝えようとしていたのか。彼は連絡をしてくれるよう頼み続けたが、佐々木は無言だった。その目に映った怜子の影が、まるで彼を見つめているような気がした。
その瞬間、雅人は決意する。佐々木が自分に隠していることがあるはずだ。彼は佐々木に必死に詰め寄った。そのとき、彼自身の恐怖を抱えつつ、怜子を守るための勇気が湧いてきた。
数分後、雅人は警察に通報した。彼の心に潜む不安と恐怖は、いずれ真実に辿り着く道となるはずだった。警察が駆けつけてから、雅人に向かって佐々木が呟いた言葉は、まさに彼を絶望へと導くものだった。
それは、「誰もが知らない真実だ。」という、不気味な響きを持つ言葉だった。
雅人の心の中で、その言葉が繰り返された。何が真実なのか。怜子はどこにいるのか。数日後、捜査は続き、佐々木は逮捕されたものの、怜子の行方は依然としてわからなかった。
高橋家の窓の外には、また雨が降り始めていた。雅人は静かに、怜子の帰りを待ち続けていた。彼の心には、恐怖と不安が渦巻き続けていた。