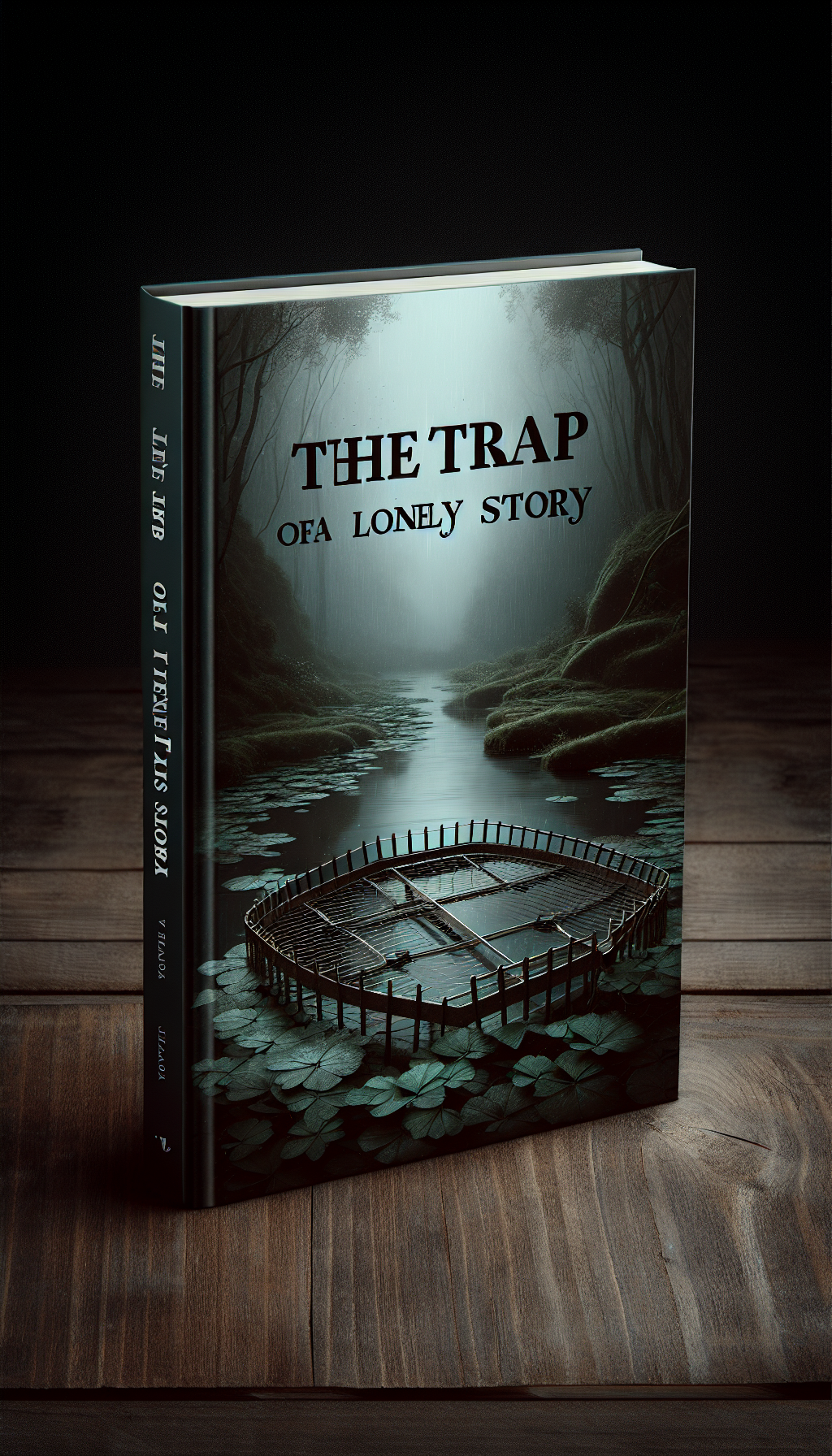影の助けを求めて
彼女の名前は由紀。秋の終わりが近づくある日のこと、彼女は友人たちと肝試しで町外れにある廃墟へ行くことになった。かつては学校だったその場所は、今ではすっかり忘れ去られ、草木に覆われていた。噂では、そこに通っていた生徒たちが失踪したという物語が存在しており、誰もが恐れをなして近づかない場所だった。
由紀たちが廃墟に到着すると、陽が沈みかけて薄暗くなり始めていた。友人たちは冗談を交わしながら中へと足を踏み入れる。だが、由紀はどこか不安を感じていた。この場所には何かが潜んでいるような気がしてならなかった。彼女は振り返るが、友人たちの楽しげな声が遠くから聞こえてくる。
廃墟の中は薄暗く、かすかな埃の香りが漂っていた。壁にはかつての生徒たちが描いた落書きが残っており、所々には錆びた机や椅子が散乱していた。由紀はその光景を見て、胸が締め付けられるような感覚に襲われた。友人たちが騒ぐ声を無視し、彼女は一人、二階部分に向かう階段を昇った。
階段を上る途中、彼女は急に背筋を冷たいものが走るのを感じた。気のせいだろうかと考えるも、心は不安に満ちていた。二階に辿り着くと、そこは一面に曇ったガラス窓が並んでおり、外の薄明かりがわずかに差し込んできた。部屋の中央には大きな黒板があり、その上には何やら不気味な文字がかすかに刻まれているようだった。
「助けて…」
それは、由紀の目に眩しく映った。無意識のうちに彼女は近づき、その文字をなぞった瞬間、ふと背後に冷たい風を感じた。振り返ると、開いていた窓が一瞬で閉じていた。その瞬間、由紀は心臓が高鳴るのを感じる。彼女は急いで友人たちのところへ戻ろうと階段を駆け下りた。しかし、段を踏み外してしまい、彼女は転んでしまった。
痛みを感じながらも、すぐに立ち上がると、彼女の周りには誰もいなかった。友人たちの声も聞こえない。焦りと恐れが募り、声を震わせて呼びかける。
「みんな!どこにいるの!」
だが、ただ静寂が応えるだけだった。由紀は一人、廃墟の中をさまよい始めた。暗闇の中で視界がぼやけ、壁に手をかけながら進む。突如、彼女の耳元で「助けて…」という声が響いた。由紀は驚いて振り返るが、誰もいない。ただの風の音だったのか、それとも。
廃墟を退出しようと必死になり、何度も階段を上ったり下りたりするが、外へ出る出口が見つからない。どこかで、冷ややかな笑い声や、耳をつんざくようなすすり泣きが混ざり合い、彼女の心を掻き乱す。
由紀はようやく一つの部屋にたどり着く。そこには古い机が並び、その上には写真が散乱していた。手に取ると、見知らぬ子どもたちの顔が映っていた。皆、どこか不安そうで、目が虚ろだ。彼女はその中の一人の顔に見覚えがあった。それは、失踪したという噂の子どもだった。
急に引き寄せられるように、彼女の背後に冷たい感触がした。振り返ることができず、ただ恐怖に震える由紀。彼女の心の中で何かが崩れ始め、ドアが激しく揺れた。しかし、何も見えず、ただ「助けて」の声が繰り返される。
ついに彼女は意を決して振り返る。すると、そこにはぼんやりとした影が立っていた。目は虚ろで、口は開きどこか苦しそうに見える。
「助けて…」
彼女の心が凍りつく。けれど、目の前の子どもの姿を見ているうちに、由紀はその目の奥に何か訴えているものを感じた。恐怖を押し殺して近づこうとすると、影はゆっくりと彼女に触れてきた。その瞬間、彼女はまるで引き裂かれるような感覚に襲われ、意識を失った。
目が覚めると、すっかり明るくなった廃墟の中にいた。一体どれだけの時間が経ったのか、周囲には一切の物音がなく、自分一人だけがそこに取り残されていることを理解する。急いで出口を探し、ようやく外へ出ることに成功した。
だが、外で待っているはずの友人たちはどこにも見当たらない。由紀の心の中には、あの子どもたちの声が響いていた。「助けて…」それは、彼女自身が廃墟に残された者たちの声だったのかもしれなかった。
以降、由紀は何度も廃墟のことを思い出そうとしたが、その記憶は次第に薄れていった。しかし、夜になると悪夢にうなされ、目が覚めると誰かの視線を感じるのだ。恐怖に駆られ、彼女はその瞬間を必死に生き延びるしかなかったが、その影は常に彼女の背後に潜み続けていた。