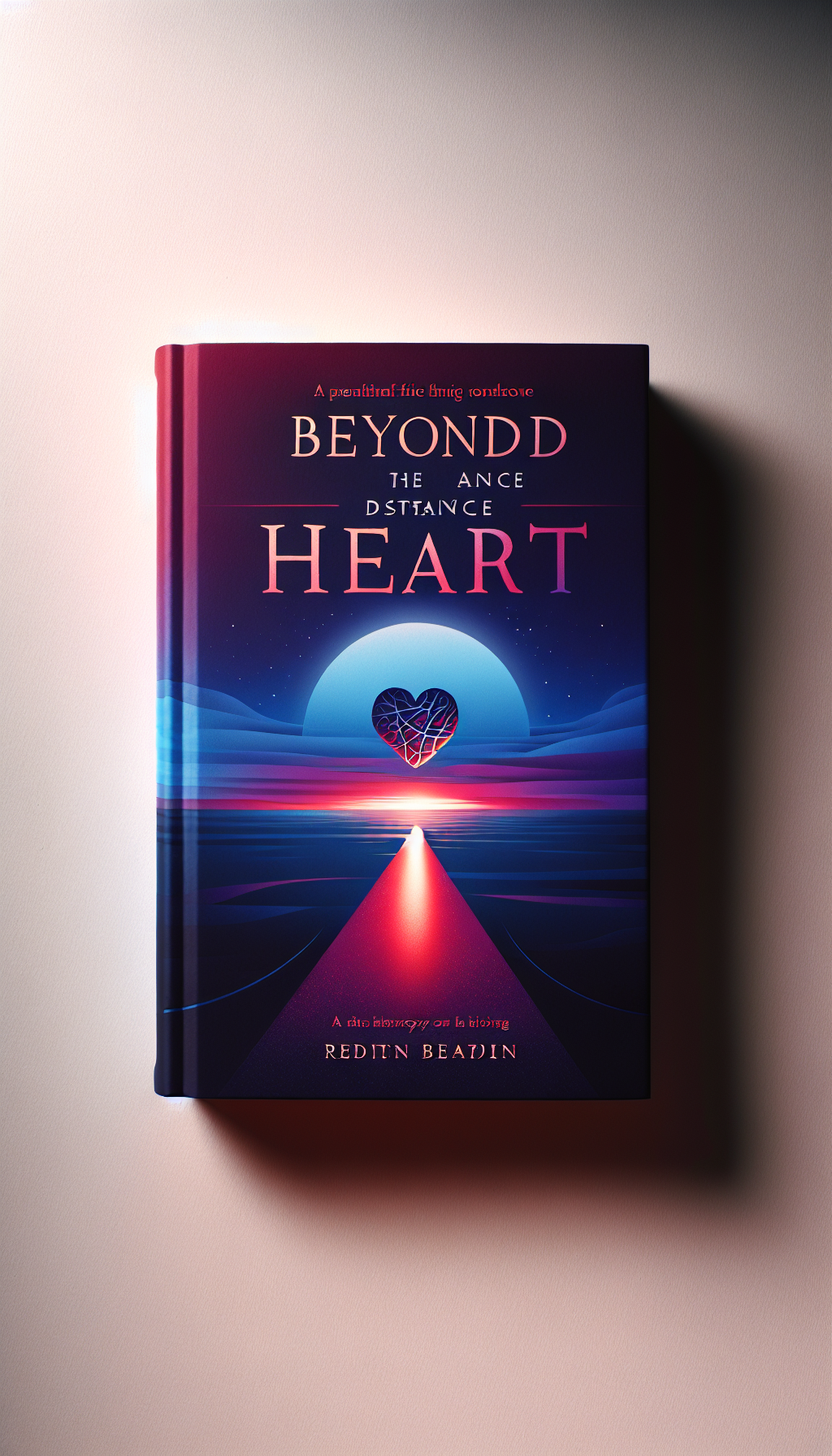心の内側の花
彼女の名前はあや。大学3年生の春、彼女は友達のマナと共に、毎日のようにキャンパスを歩き回っていた。あやは内気で、いつもマナの後ろをついて回るような存在だった。彼女は自分の気持ちを表現するのが苦手で、恋愛に関してもウブだった。
そんなある日、あやは偶然、同じクラスの圭介に出会った。彼はいつも明るくて、周囲から人気があった。あやは圭介の笑顔に少しドキドキした。しかし、圭介はいつもマナと楽しそうに話している姿を見ていたため、あやは彼に話しかける勇気が出なかった。
春が過ぎ、夏がやってきた。マナとあやはサークル活動を始めた。そこで、圭介も同じサークルに入っていることがわかる。夏祭りの準備をするために集まったとき、圭介があやに話しかけてきた。「あやさん、一緒にこういう小道具作らない?」彼の言葉に、あやは驚きつつも少し嬉しかった。
二人はすぐに意気投合し、毎日のようにサークルで顔を合わせるようになった。あやは圭介との時間が楽しくてしょうがなかった。彼の優しい声や温かな笑顔は、あやの心を少しずつ明るくしていった。しかし、同時にマナが圭介に好意を抱いているのではないかという不安が、あやの心の中で膨らんでいった。
ある日、サークルの帰り道、あやはマナと一緒に帰ることになった。「圭介っていいよね。あの雰囲気、なんだか掴みどころがない感じがして」とマナが言った。その言葉を聴いて、あやの心はさらに重くなった。マナは本気で圭介のことを好いているのだろう。そう思うと、あやはどうしても自分の気持ちを隠さなければならなくなった。
その後、夏祭りが近づき、サークルは準備に忙しくなった。あやは圭介のそばにいる時間が増える一方で、マナとの距離を取ることにした。彼女は自分の気持ちを守るために、マナに対しても不自然な笑顔を浮かべながら、心の内を隠していた。
祭りの当日、あやは圭介と一緒に屋台を手伝うことになった。待ちに待ったその日、二人は楽しそうに何度も笑い合いながら、作業を進めていた。しかし、その時マナが偶然通りかかった。彼女は二人の楽しそうな様子を見て、少し立ち尽くした後、どこか悲しげな表情を浮かべながらその場を去っていった。あやは心の中で「ごめん」と呟いた。
祭りが終わった後、あやは圭介に誘われて、二人で飲みに行くことになった。彼女の心には期待と不安が交錯していた。圭介はあやの目を真剣に見つめながら、「あやさんは本当に明るくて、みんなを引き込む力がある。だから、もっと自信を持ってほしい」と優しく言った。
その言葉はあやの心に響いたが、同時に彼女の内に秘めた感情も揺れ動いた。「圭介、私…」と口を開いたが、言葉が続かなかった。青い夜空の下、彼女は何かを告げようとしたが、結局声を上げることができなかった。
数日後、あやはマナと話をする機会を作った。心の中でずっと気になっていたことをやっと伝えた。「マナ、もしかして圭介のことが好きなの?」と尋ねると、マナは少し驚いた顔をしたが、すぐに柔らかな笑顔を浮かべた。「ううん、私達の友情の方が大切だから、あやに任せるよ」
その言葉を聞いた瞬間、あやは心の奥深くから安堵が広がった。友情を大切にしてくれるマナがいること、そして、自分が圭介に特別な感情を持っていることを少しずつ受け入れていられると思った。
その後、あやは圭介に自分の気持ちを伝える決意を固めた。秋の風が吹く中、あやは勇気を出して圭介に会いに行った。彼に向かって、彼女は自分の心の内を素直に語った。しばらく圭介は黙って聞いていたが、彼の表情は次第に明るくなり、「俺もあやさんのことが好きだった。こんなに早く言えたとは思わなかった」と笑顔を見せた。
あやは涙をこらえながら、彼の気持ちに応えて頷いた。この瞬間、彼女の心にあった不安はすべて消え去った。友達以上の関係への一歩を踏み出し、あやは新たな恋の始まりを感じた。そして、マナとの友情も大切にしながら、彼女はこれからの未来に希望を抱くのだった。