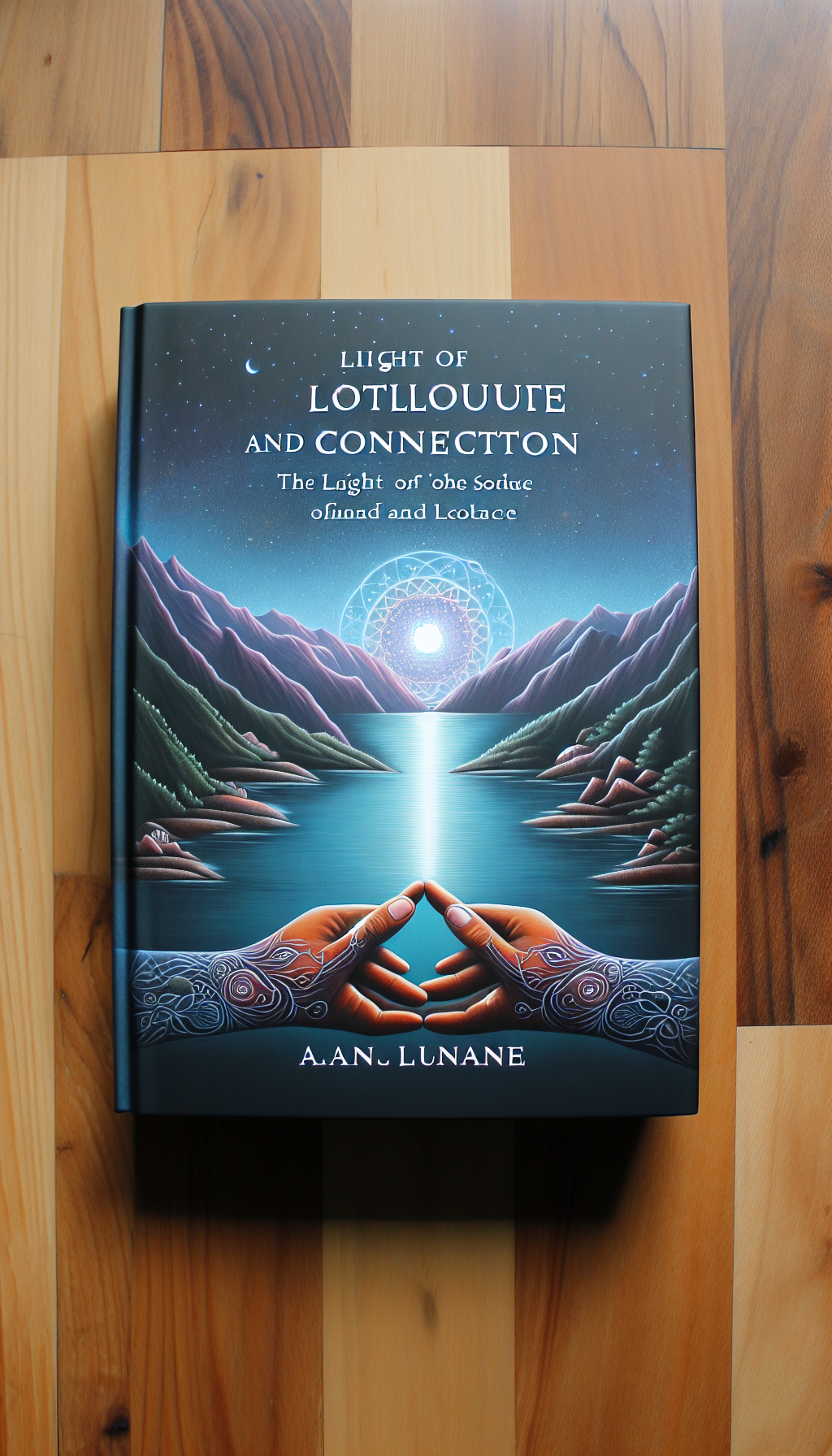夏の友情
中学校最後の夏休みは、まさに青春の象徴だった。その日、私はいつものメンバーと公園で待ち合わせをしていた。太陽が高く、砂で遊ぶ子供たちの笑い声が響く中、風が心地よく頬を撫でていた。
「さあ、今日もバスケしようぜ!」と元気に叫んだのは裕太だ。裕太はクラスのムードメーカーで、いつも明るくてみんなを引っ張っていた。私たちは毎日のようにバスケットボールコートに集まり、汗まみれになっては疲れ知らずでプレイしていた。
公園の一角にはショーコもいた。ショーコは私の隣の席の子で、実は密かに憧れていた。でも、裕太もショーコに興味があるみたいだった。そんな微妙な三角関係が、私たちの中に緊張感をもたらしていた。
その日は特別な日だった。夏の終わりが近づくにつれて、私たちの心には何となくの寂しさが広がっていた。中学生活もあとわずか。次のステージが待っていることはわかっていたが、今この瞬間を大事にしたかった。
試合が始まる前、裕太が突然言った。
「今日は最後にしようぜ、みんなで出し切ろう!」
その言葉に皆が頷いた。ボールが空中に放り投げられ、試合が始まった。裕太のシュートが鮮やかに決まり、ショーコが華麗なドリブルを見せた。私も全力で走り回り、ゴールを狙った。歓声と笑い声が響き、誰もがその瞬間を楽しんでいた。
一方、心の中では複雑な思いが渦巻いていた。青春の一コマが刻一刻と過ぎ去っていく中で、何かを伝えたいという思いが強くなっていった。試合終了後、皆で飲み物を買うために自動販売機に向かって歩いた。まるで日常の一部であったその風景も、その瞬間は特別に感じられた。
自動販売機の前で、裕太が突然振り向いてショーコに声をかけた。
「ショーコ、ずっと思ってたんだ。俺たち、中学が終わっても友達でいようぜ。この夏の思い出、絶対忘れないから。」
ショーコの顔が一瞬驚いたように見えたが、すぐに笑顔に変わった。
「うん、私も。同じ学校に行くわけじゃないけど、きっとまた会おうね。」
そのやり取りを見て、私の胸には少しの寂しさが残ったが、同時に友情の強さを感じた。青春の儚さと美しさが一瞬にして感じられるひとときだった。
夕方になると、私たちは公園を後にした。周囲がオレンジ色に染まり、太陽が沈む頃、ショーコが私に近づいて話しかけてきた。
「ねぇ、今日楽しかったね。ありがとう。」
思わず私はうなずいた。
「うん、いつも楽しかった。でも今日が特別だった。」
ショーコは笑って、手を振った。その笑顔が心に焼き付いた。
自宅に帰る途中、ふと一つの決意が私の中で固まった。この夏の思い出を大事に、未来に進もうと。青春の輝きは一瞬かもしれないが、その記憶は永遠に心に残るだろう。
それから数年経ち、私は裕太やショーコと再び会うことは少なくなった。しかし、あの夏の日の思い出は色あせることなく、私の心に活力を与え続けている。
中学校最後の夏休みの、あの一日の記憶。それが私にとっての青春の全てであり、未来に向かうための大切な礎となったのだ。