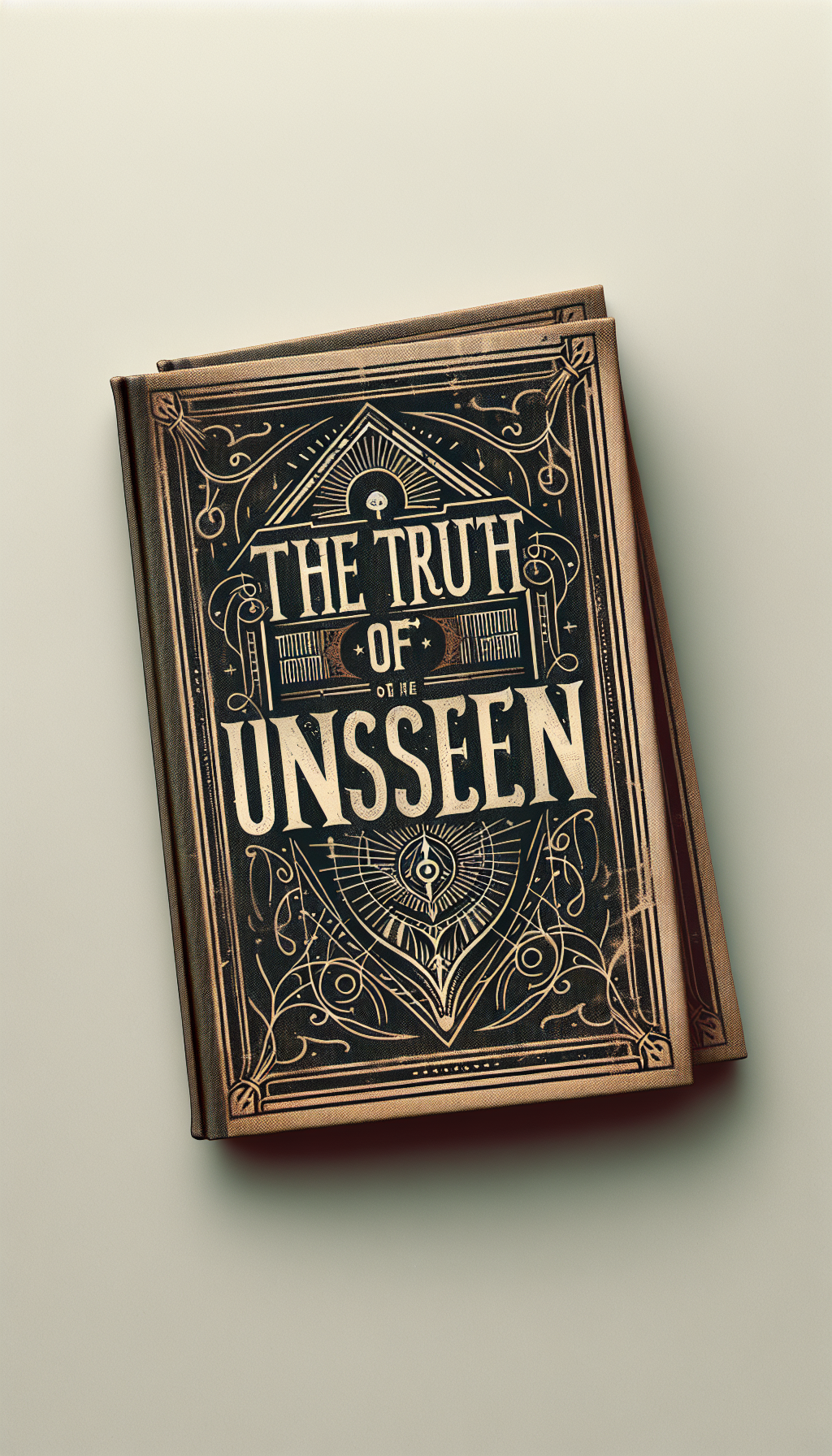闇の向かい部屋
夜の帳が下りると、町はいつもと違った雰囲気に包まれる。特に、古びたアパートの一室に住む佐藤は、その独特の緊張感に慣れていた。彼は一人暮らしで、普段は自宅で静かにインターネットを閲覧したり、本を読んだりして過ごしていたが、最近、不思議な出来事が立て続けに起こり始めた。
ある晩、彼はお気に入りの小説を読み終えて、時計を見た。午後十一時を過ぎている。ふと窓の外に目をやると、向かいのアパートの一室が明るく輝いていた。彼はその部屋を見たことがないが、個性的な明かりに引き寄せられ、しばらく窓の外を見つめていた。
その夜、夢の中で、彼は暗い廊下を歩いていた。壁には剥がれたペンキの跡や古びた写真が並んでおり、彼の心を不安で満たした。廊下の先に、同じ向かいのアパートの部屋があった。なぜか、その部屋の扉が開いていた。妙に引き寄せられるように、彼はその中へ足を踏み入れた。
目が覚めると、佐藤はその夢のことを鮮明に思い出していた。しかし、朝の光によって夢は現実のものと区別されてしまった。彼は日中、いつも通りの生活を送ったが、どこか心の底に不安感が残っていた。
数日後、佐藤は再び夜遅くまで起きていた。ふと、また向かいのアパートの窓を見た。今回も明るい光が漏れている。興味本位で観察していると、突然その窓がガタガタと揺れ、誰もいないように見えた。何かが違うと感じた彼は、思わず目を凝らした。
その瞬間、彼は近くの公園に住む老婦人の声が耳に入ってきた。「あの部屋はダメよ。そこに住む人は、みんなおかしくなってしまうから。」老婦人の言葉に、彼は興味を持った。知り合ったことはなかったが、気になって質問をした。
「どうしてですか?」と彼は尋ねる。老婦人は、かつてその部屋に住んでいた人々の奇妙な行動を語りだした。中には行方不明になる者さえいたという。彼女の話を聞くうちに、佐藤は少し気分が悪くなるのを感じた。
その日から、彼は向かいのアパートを意識するようになった。時間が経つにつれ、夢の中の廊下とその部屋に行くことが増えていった。夢の中では、いつも扉の前で立ち尽くしていた。しかし、ドアを開ける勇気が出なかった。
そしてある夜、夢の中で再びその廊下に立っていると、彼は不思議な声を聞いた。「入ってきて、待っているから。」思わず扉を開けると、真っ黒な部屋が目の前に広がっていた。中に入ると、異様な寒気がした。他の誰かがいる気配を感じた瞬間、心臓が早く打ち始めた。
次第に、彼の周りは濃い霧に包まれ、声が響き渡った。「私たちを助けて。」最初は耳も信じられなかったが、彼の顔の近くで囁くような声を聞き、全身が凍りついた。目の前に現れたのは、かつてその部屋に住んでいた人々の姿だった。彼らは無表情で、絶望的な目をしてこちらを見つめていた。
目が覚めた時、佐藤は息を切らしていた。一体何だったのか。彼は夢の中の声を思い出しながら、再び向かいのアパートを見た。明かりは消えていた。何かが起こったかのような静けさが、彼を取り巻いていた。
意を決して、佐藤は翌日、向かいのアパートを訪れることにした。ドアをノックすると、出てきたのは若い女性だった。彼女は無表情で立ち、まるで何かに取り憑かれているかのようだった。
「あなた、あの部屋に住んでいるの?」と彼は尋ねた。彼女は少しの間黙っていて、やがてこう答えた。「出て行った方がいい。ここの住人はみんな同じ運命を辿るから。」
その言葉に背筋が冷たくなった。彼は恐怖を感じながらも、その場を離れ、アパートから逃げ出した。自宅へ戻る途中、振り返ると、向かいのアパートの明かりは再び点灯していた。
そして、その夜、再び夢の中であの廊下に立っていた。今度は、他の住人たちが彼を待っていた。彼は思わず扉を開き、入ることを決意した。真っ暗な部屋に足を踏み入れると、彼の背後にドアが閉じる音がした。
周囲には薄気味悪い静寂が満ちていた。彼は数え切れないほどの目に見られながら、その暗闇に飲み込まれていく感覚を味わった。
町の人々はやがて、彼が姿を消したことに気付く。しかし、誰もその部屋に近づこうとはしない。不気味な噂が広まる中、向かいのアパートは静かにその姿を保ち続け、明かりが点いたままになるのだった。