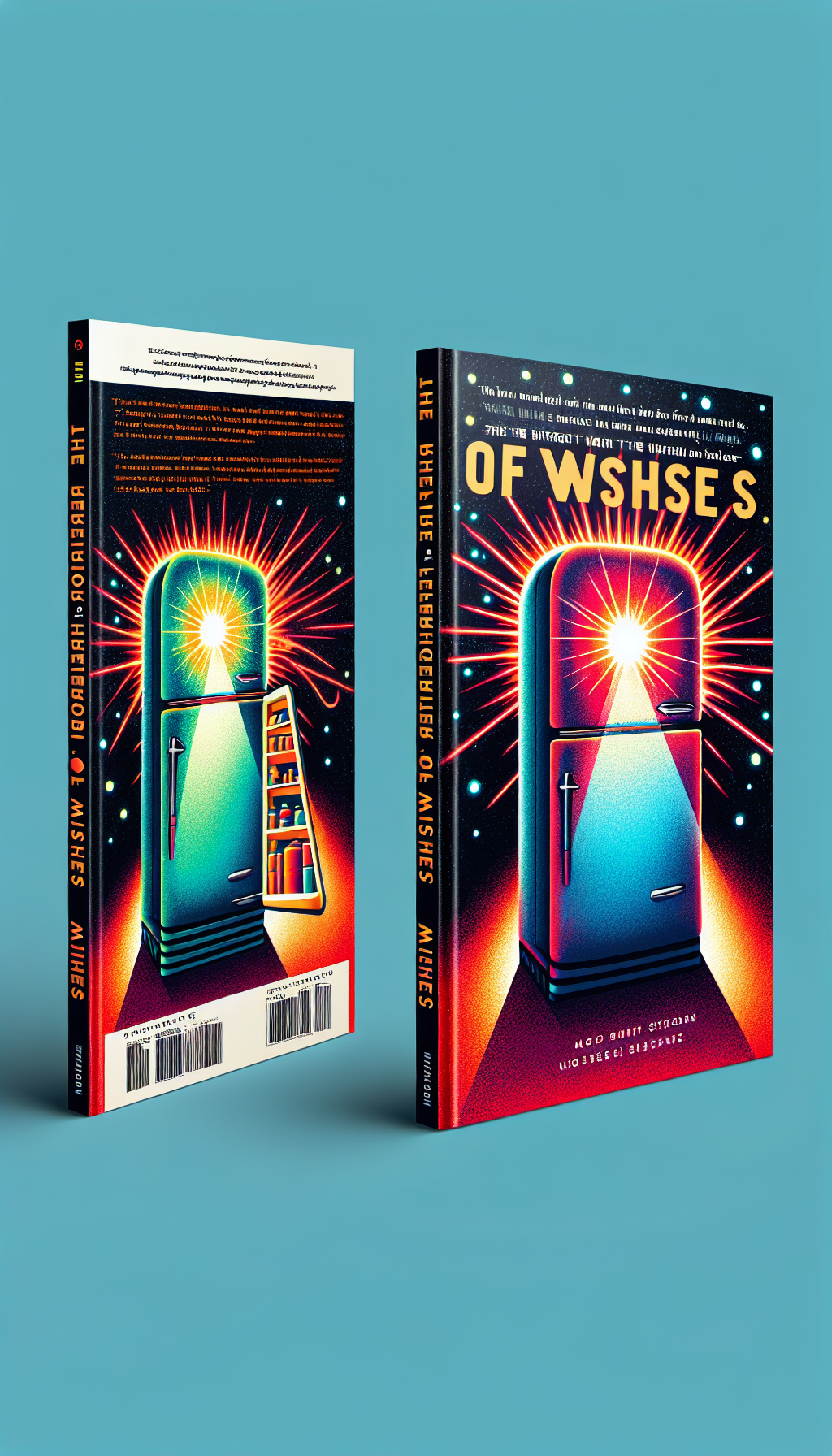消えぬ館の恐怖
夜の深まりと共に、霧が薄いベールのように村を包み込んでいた。しびれるような冷たさが空気中に漂い、人々は家の中に閉じこもり、その存在を感じるようであった。その村は古い伝説に彩られ、人々はしばしば語り合うが、それが現実のものだとは誰も信じていなかった。
しかし、その夜が特別なものであるとは誰も気づいていなかった。村の外れにある古びた屋敷には誰も住んでおらず、崩れかけた壁や振り子時計の音だけがその存在を告げていた。屋敷はその長い歴史を通じて、多くの不幸を生み出してきた場所として知られていた。
「お前たち、ここで何をしているんだ?」
若い声が霧の中から響いた。そこには三人の若者が立っており、一人は勇敢さというよりも無謀さから来る自信を持っていた。彼の名前は翔といい、この屋敷を懐中電灯の明かりで探検しようと友人たちを誘ったのだった。
「翔、本当にここに入るつもりか?」と友人の一人、善輔が不安げに尋ねた。もう一人の友人、舞美は黙っていたが、彼女の顔には恐怖の色が浮かんでいた。
「大丈夫だよ。こんな場所、ただの古い家だ」翔は笑い飛ばして言ったが、その目の奥には好奇心と一抹の不安が入り混じっていた。
三人は意を決して屋敷の中に足を踏み入れた。床は軋み、埃が舞い上がる中、彼らは一歩一歩進んだ。廊下は長く、静寂が鼓膜を圧倒する。壁には古い絵画や朽ちた鏡が掛かっていたが、それらは徐々に彼らの視界から消えていった。
「ここ本当に大丈夫なの?」舞美が小さな声で尋ねたが、翔は応えなかった。ただ前方の暗がりに目を向け続けていた。
突然、何かが動く音が聞こえてきた。翔と善輔は懐中電灯でその方向を照らしたが、何も見えなかった。ただ、重たい空気と冷たい風が彼らの背筋を凍らせただけだった。
しばらくすると、薄暗い廊下の奥から奇妙な音が聞こえてきた。それは泣き声のようであり、呻き声のようでもあった。三人はお互いの顔を見合わせ、恐怖が全身を駆け巡るのを感じた。
「もうやめよう、帰ろう」善輔が叫んだが、翔は頑固に首を振った。「ここまで来たんだ。確かめないと気が済まない」
音は徐々に近づいてきた。そして突然、古びたドアが彼らの前で勝手に開いた。中には暗闇が広がっており、何かがその奥で動いているのがわかった。その時、翔は何かに引き寄せられるようにその部屋に入り、舞美と善輔は恐怖に固まってしまった。
不意に、翔が叫び声を上げた。懐中電灯が床に落ち、回転しながら光が乱反射した。舞美と善輔は恐怖で凍りつき、目を見開いた状態で翔を見つめた。彼の顔は痛みに歪んでおり、何かが彼を襲っていた。
「助けて!逃げて!」彼は必死に叫んだが、その声は次第に弱まった。そして、影のような存在が彼を闇へと引きずり込んでいった。
舞美と善輔はその場から逃げ出した。全速力で屋敷の外へ駆け出し、霧の中へ消えた。彼らの頭の中にはただ一つの思いがあった――あの屋敷は何かが住む場所であり、それは人間が立ち入るべきではないということ。
村に戻った彼らは、他の住民たちにこの出来事を話したが、誰も信じなかった。しかし、翌朝になると状況は一変した。翔が姿を消した夜の霧が未だに村を包んでおり、その存在が何か不吉なことを伝えているようであった。
日が昇ることはなかった。霧は村全体を包むまま、二度と晴れることはなかった。その後、村人たちは次第に一人また一人と姿を消していき、最終的にその村は無人となった。
そして、あの屋敷は再び静寂に包まれ、霧の中に佇んでいた。その存在は忘れ去られることはなかったが、二度と人々の記憶に現れることはなかった。
ただ、その夜の恐怖だけが霧の中に残り、誰にも語られることなく消えゆく運命にあった。それは、恐怖の本質であり、決して消えることのない存在だったのだ。