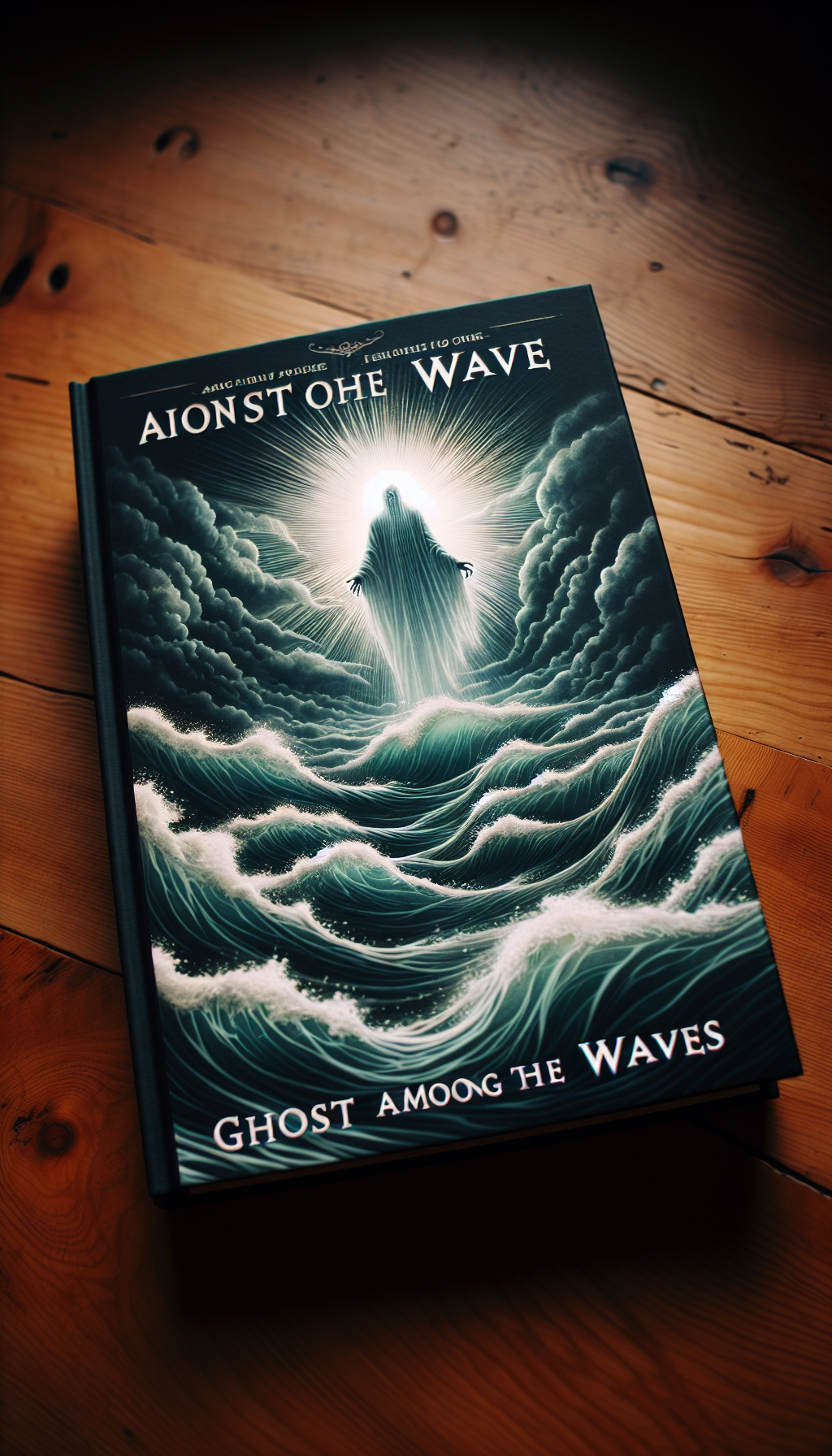黒い霊の追跡
小坂佳代は、古びた木製のドアを押し開け、不気味な廃病院の中へ足を踏み入れた。暗闇に包まれた廊下、破れた壁紙、こびりついたホコリの匂い——すべてが彼女の心に恐怖を呼び起こす。彼女がこの場所に来たのは、失踪した弟の拓也を探すためだった。最後に目撃されたのは、この病院の近くだったという情報を手に入れ、やむを得ずここにやってきたのだ。
佳代は懐中電灯のスイッチを入れ、薄暗い廊下をゆっくりと進んでいく。一歩一歩、歩を進めるごとに、彼女の心臓は激しく鼓動を打ちつけた。壁にかけられた古い鏡に映る自分の姿が揺れ、まるで誰かがこちらを見ているような錯覚に陥る。
突然、彼女の耳元でかすかな囁き声が聞こえた。「助けて……」誰かの声、いや、何かの声なのか。佳代は立ち止まり、振り返る。しかし、背後には何もない。彼女は震える手で懐中電灯を持ち直し、再び歩き始めた。
廊下の奥には、重厚な鉄の扉があった。その上には「精神科隔離病棟」と刻まれている。佳代は心の中で覚悟を決め、その扉を開ける。開いた瞬間、冷たい風が彼女の顔に触れ、まるで何かが警告しているかのように感じた。
扉の向こうには、さらに暗く冷たい部屋が連なっていた。壁には古い病歴カルテが散乱し、床には錆びついた車椅子が倒れている。佳代は懐中電灯を慎重に動かしながら、施設の奥へ奥へと進んでいった。その時、一つの部屋から突然物音がする。
彼女は息を呑み、そっとその部屋に向かった。ドアを開けると、薄暗い部屋の中には一人の少年がいた。拓也だった。彼は冷たい床に座り込み、震えながら何かをブツブツと呟いていた。佳代は駆け寄り、弟を抱きしめた。
「拓也、大丈夫?何があったの?」
拓也は震える手で佳代の腕を握り、視線を彷徨わせながら呟く。「ここには……何かがいる……助けて……」
佳代は弟の言葉に戸惑いつつも、彼を立ち上がらせようとしたその瞬間、部屋の隅から黒い影がゆっくりと立ち上がるのが見えた。その影は人間の形をしていたが、目も口もなく、ただ黒い霧のような存在だった。
佳代は恐怖に凍りつき、その場から逃げ出したい気持ちに駆られたが、弟の手をしっかりと握り、共に立ち向かう決意をした。影は徐々に近づいてきた。佳代は拓也を背後に隠し、懐中電灯を強く握りしめた。
「誰なんですか?何のためにこんなことをしているの?」佳代は震えながらも叫んだ。しかし、影は無言のまま彼女たちに近づいてきた。次の瞬間、影の中から鋭い手が伸び、佳代に襲いかかった。
その瞬間、彼女の頭の中である記憶が鮮明に蘇った。昔、母親が語っていた古い伝説。この廃病院には、かつて人々を恐怖に陥れるために魂を奪う霊が住んでいるという話。佳代はそれがただの迷信だと思っていたが、今目の前に現れているものは、その伝説の黒い霊そのものだった。
佳代は何とか振り払おうと努力したが、霊の力は恐ろしく強く、彼女の体は徐々に力を失っていった。その時、彼女の足元にあった小さな祈りの石が目に入った。母親が最後に渡してくれたこの石が、唯一の希望だった。
佳代は全力で石を掴み、その力を信じて黒い霊に向かって投げつけた。すると、霊は激しく揺れ、次第に形を失っていった。そして、最後には完全に消え去った。
佳代は息をつき、拓也を抱きしめた。弟も震えながらも、ようやく笑顔を見せることができた。「ありがとう、姉ちゃん」
二人は手を取り合い、廃病院を後にした。外の世界に出ると、朝日が昇り、全てが明るく照らされていた。佳代は深く息を吸い込み、この恐怖の体験が二度と訪れないように祈った。
彼女たちが無事に家に戻った後、この廃病院は完全に封鎖された。そして、この地に存在した恐怖の記憶は、彼女たちの心の中だけに残った。二人は決して忘れないだろう、自分たちを襲った黒い霊の恐ろしさを。
それでも、彼らは生き延びた。そして、恐怖に打ち勝ったその強さを、いつまでも忘れることはなかった。