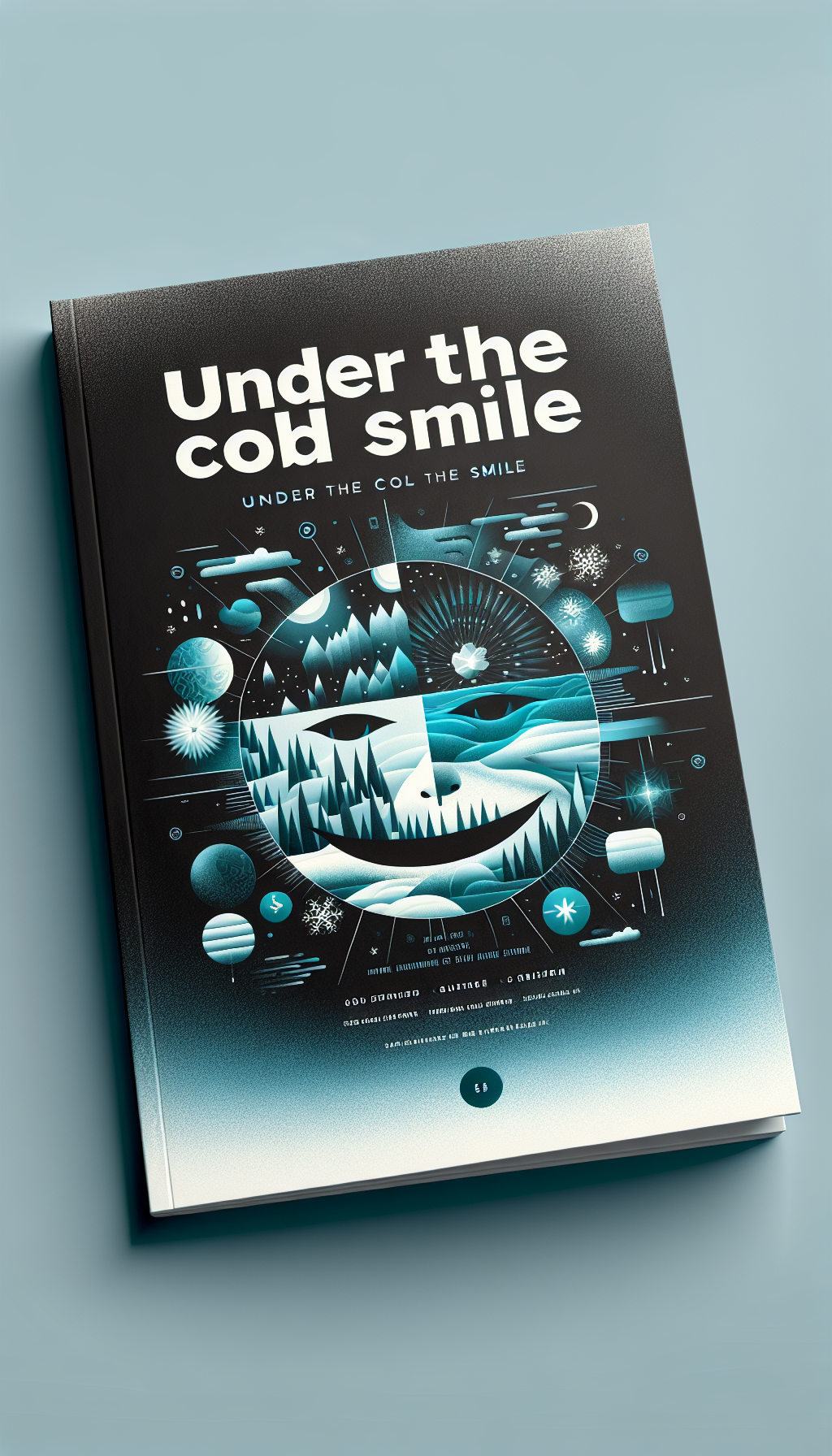霧の中の囁き
冷たい霧が立ち込める晩秋のある夕暮れ、町外れに佇む古びた洋館に一人の少年が足を踏み入れた。彼の名は翔太。彼は友人たちから聞いた噂を探るため、密かにこの洋館を訪れたのだった。町で語られるこの場所の恐怖の物語は、夜になると霊が現れるというものだったが、翔太は単なる迷信だと考えていた。
洋館のドアを開けた瞬間、冷たい風が彼を迎え、そして不気味な静寂が広がった。彼は持参した懐中電灯を点け、薄明かりの中を歩き始めた。古い床板がきしむ音が怖れを煽るが、彼はその音に慣れようと努めた。壁にはかつての家族の肖像画が掛かっており、彼らの冷たい視線が翔太を見つめ返してくるようだった。
洋館の奥へ進むにつれ、徐々に不気味さが増していった。特に目に留まったのは、壁に沿って横たわる古びた鏡だった。鏡の表面は曇り、まるで何かを隠しているかのようだった。好奇心から翔太はその鏡に近づいた。懐中電灯の光が当たると、一瞬だけ反射の中に誰かの顔が映ったように感じたが、すぐにその映像は消えた。
翔太は自分の錯覚だと思いつつも、心のどこかに不安を感じ始めた。その時、かすかなひそひそ声が彼の耳に届いた。恐る恐る声の方へ振り向くと、そこには誰もいなかった。しかし、声は確かに彼を呼んでいた。「翔太…」その声は甘美でありながら、どこか不気味だった。
好奇心と恐怖の狭間で揺れ動く翔太は、声の元へ向かうことに決めた。声に導かれるまま、彼は洋館の地下へ続く階段を見つけた。暗い階段を下るにつれて、冷や汗が背中を伝う。地下に足を踏み入れると、薄暗い空間が広がっており、かすかな光が古びた燭台から漏れていた。
その光の先には、中央に小さな祭壇があった。その上には、古い日記と黒い御影石が置かれている。翔太は恐る恐る日記を手に取り、ページをめくった。そこには、この洋館にまつわる恐ろしい歴史が記されていた。数十年前、ここで一族が惨劇に巻き込まれ、今もなお彼らの霊がこの場所に留まっているというのだ。さらに、「外に出てはいけない。彼らが来る」と警告する文が続いていた。
翔太は心臓が高鳴り、焦りが込み上げてきた。暗闇の中、彼を監視している気配を感じ、急に後ろを振り返った。やはり、誰もいない。しかし、今度は背筋が凍るような寒気が彼を襲った。地下室の空間が彼を包み込み、徐々に視界がぼやけてきた。
その瞬間、地下室の壁から影が伸びてきた。翔太は動けなかった。背後から耳障りな声が響く。「翔太、おいで…」それはさっき聞いた声であり、しかし今度はもっと近くに感じられた。恐怖を抱えながらも彼は階段を駆け上がり、逃げようとしたが、重たい扉は頑なに閉ざされ、全く開かなかった。まるで何かが彼をここに留めようとしているかのようだった。
「ここから出さない…」その声が再び響く。翔太は涙を流し、薄暗い地下室の中で必死に脱出を試みたが、次第に力が抜けていく。しかし、絶望の中でふと思いついた。彼は懐中電灯を壁に叩きつけ、光を発生させた。その光が影を一瞬消し去り、彼はその隙を利用してドアを押し開けた。
外に出た時、霧が晴れ、星が輝いていた。振り返ると、洋館は静かにそこに佇んでいたが、彼の心の中には確かな恐怖が刻まれた。翔太は二度とあの場所には戻らないと誓い、心臓の鼓動を胸に抱えながら、町の明かりへと向かった。
その後、友人たちに彼の体験を語ろうとしたが、どうしても言葉にすることができなかった。彼の脳裏には常に、あのささやき声が響いていたからだ。「翔太、おいで…」その声は今もなお、彼を呼び続けているのだった。