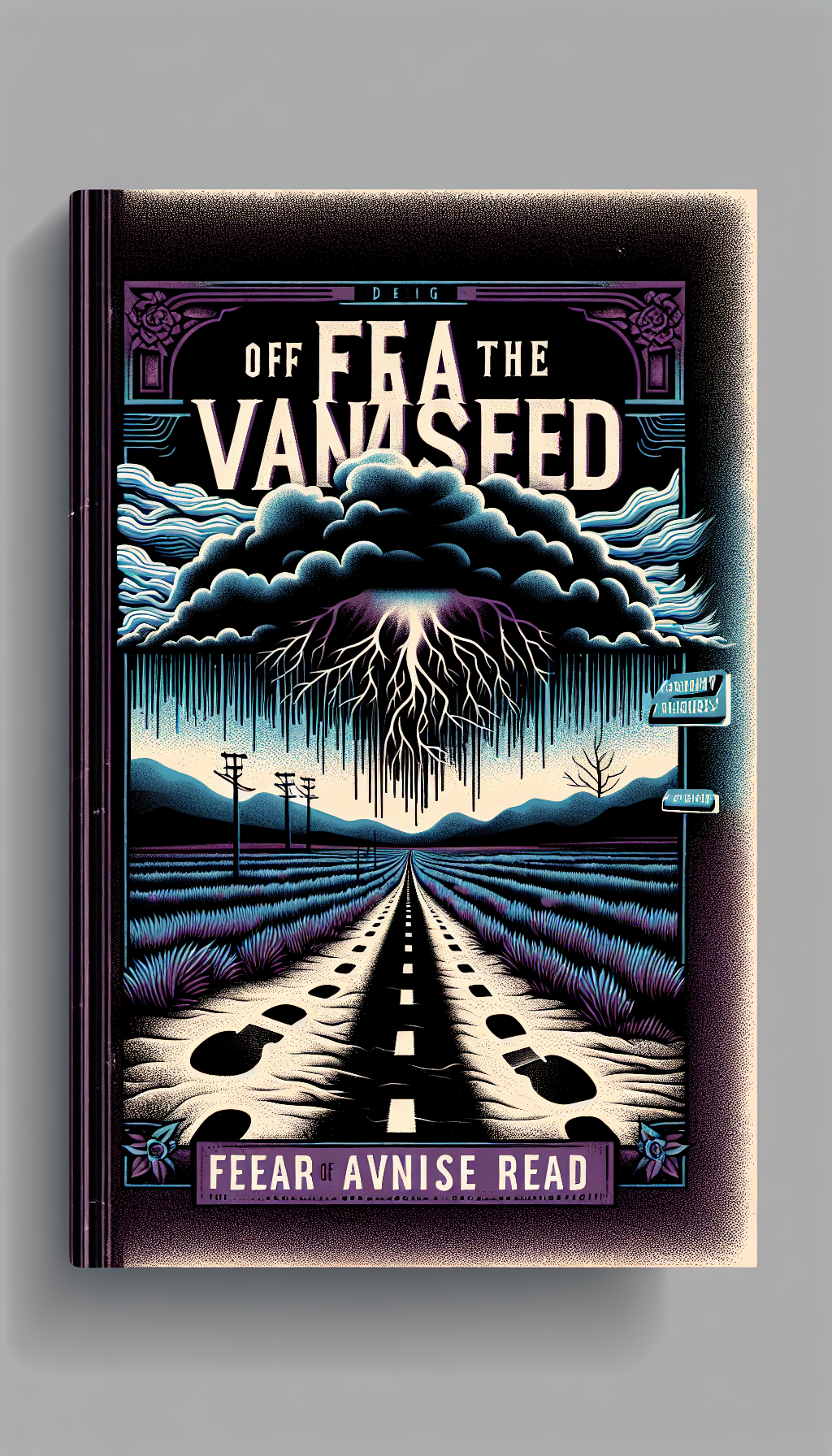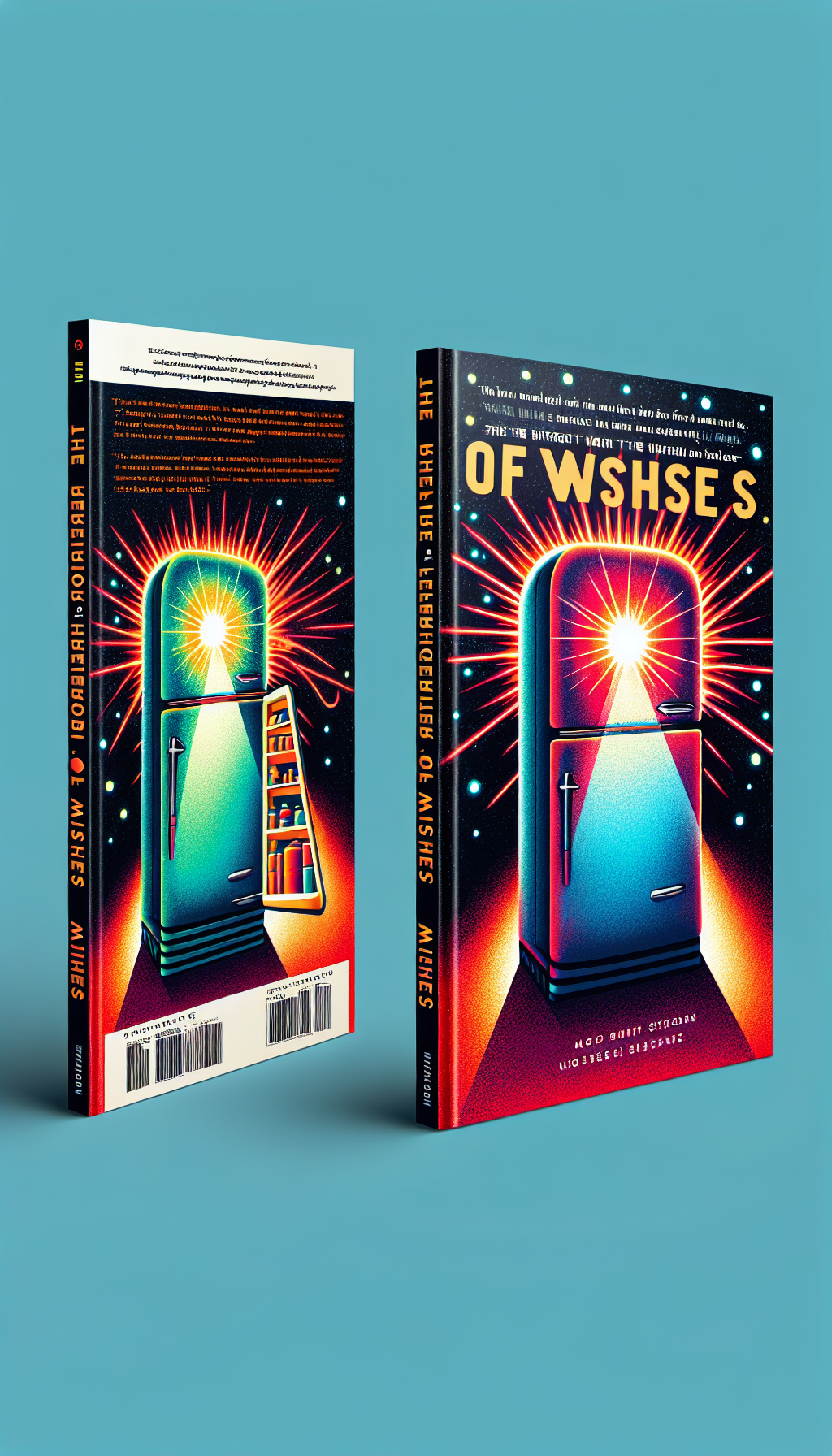鏡の中の囚われ
薄暗い夜、雨が静かに降り注ぐ中、小さな村の片隅に佇む古びた家があった。その家は長い間誰も住んでおらず、村人たちはその存在を避けるようにしていた。しかし、好奇心旺盛な少年、健太はその家に侵入することを決意する。友人たちに「お前は怖がりだ」と笑われ、彼はその言葉を覆すため、勇気を振り絞るのだった。
家の扉は錆びていて、開くのに大きな力が必要だった。ぎしぎしと音を立てながら扉が開くと、ほこりで覆われた空気が鼻をついた。中はまるで時間が止まったかのような静寂で、薄暗い廊下が続いていた。壁には古い写真が掛けられており、ひび割れた帆布がその人物たちを見つめ返してくる。
健太は一歩ずつ前に進む。その時、背後からかすかな音が聞こえた。風が通り抜けただけだと思い込んでいたが、彼の心臓は高鳴り始めた。廊下の先には小さなドアが見え、そこだけが何故か微かに光っている。好奇心に駆られ、彼はそのドアへ向かう。
ドアを開けると、小さな部屋が現れた。部屋の中央には古い鏡があり、その周りには金色の装飾が施されていた。鏡は埃で曇っていたが、健太は自分の姿を映すため、手で拭き取った。すると、鏡の中に映ったのは彼自身ではなく、全く見知らぬ少女だった。彼女は淡い青いドレスを着ており、目は悲しげな表情を浮かべている。
「助けて…」少女が小さな声で呟いた。健太は驚き、思わず後退った。少女の顔は何か訴えかけているようで、彼は何とか声を絞り出した。「君は誰?」
「ここから出して…ずっと閉じ込められているの…」少女の声は次第にか細くなり、健太の心に不安が広がった。彼はその場から逃げ出したい衝動に駆られたが、何故か足が動かない。目を逸らすことができず、彼女の悲しげな瞳に引き込まれるようだった。
「…お願い、助けて…」その言葉は、まるで彼を呪縛するかのように響いた。健太は思わず鏡に近づき、少女の手を取ろうとした。その瞬間、冷たい感触が腕を包み込む。彼は恐怖に身を震わせた。少女の表情は一瞬にして変わり、恐れに満ちた顔になった。
「逃げて…!」口を開いた彼女の声は響き、部屋の空気がひどく冷たく感じた。健太は我に返り、急いで部屋を飛び出した。廊下を駆け抜け、扉の外へと辿り着く。しかし、彼が出た先には、まるで何もなかったかのような静寂が広がっていた。もはや村の灯りも見えず、彼は迷い込んだことを後悔した。
不安でいっぱいになり、振り返ると、あの少女の姿が鏡の中で消えかけているのが見えた。彼女の口元がささやくように動いている。しかし、何を言っているのかはわからない。ただ無情な静寂が彼を包み込み、周囲の温度がさらに下がっていく。
自宅へ戻る途中、彼の目には涙が溜まった。この村に帰ることなどできないのではないかと不安がよぎる。家族の声、友人たちの笑い声、全てが孤独に消え去ったように感じた。彼は急いで家に戻り、すぐに家族にその体験を話そうとしたが、言葉が出てこない。どれだけ説明しても、誰も彼の言葉を信じないだろう。鏡の中の少女のことを話したところで、彼自身の精神状態を疑われるのが関の山だ。
翌日、村人たちは家の周りを掃除し始めた。あるおばあさんが、その家には何十年も前に失踪した少女の話があると言った。村に伝わるそんな話を思い出し、健太の心には深い恐怖が根付いた。彼が見た少女は、もしかしたら不幸にもその家に囚われた亡霊ではないか。しかし、彼はその答えを知る余裕すらなかった。
日が経つにつれ、彼は徐々にその体験を忘れようとしたが、時折夢の中に少女が現れ、「助けて」と訴えかけてくる。彼はその夢から逃げられず、恐怖に駆られたまま村での生活を続けた。周囲の陰湿な視線にも敏感になり、時折村の集まりにも参加しなくなった。
それでも、彼の心の中にはあの少女の悲しみが消えずに残り続けた。結局、彼はその小さな村を後にしなければならなかった。新しい土地で彼は再出発しようと決めたが、向こうの世界でもあの少女の声が耳に響いていた。恐怖と悲しみが交錯する彼の人生が、再び彼を呼び寄せることを。