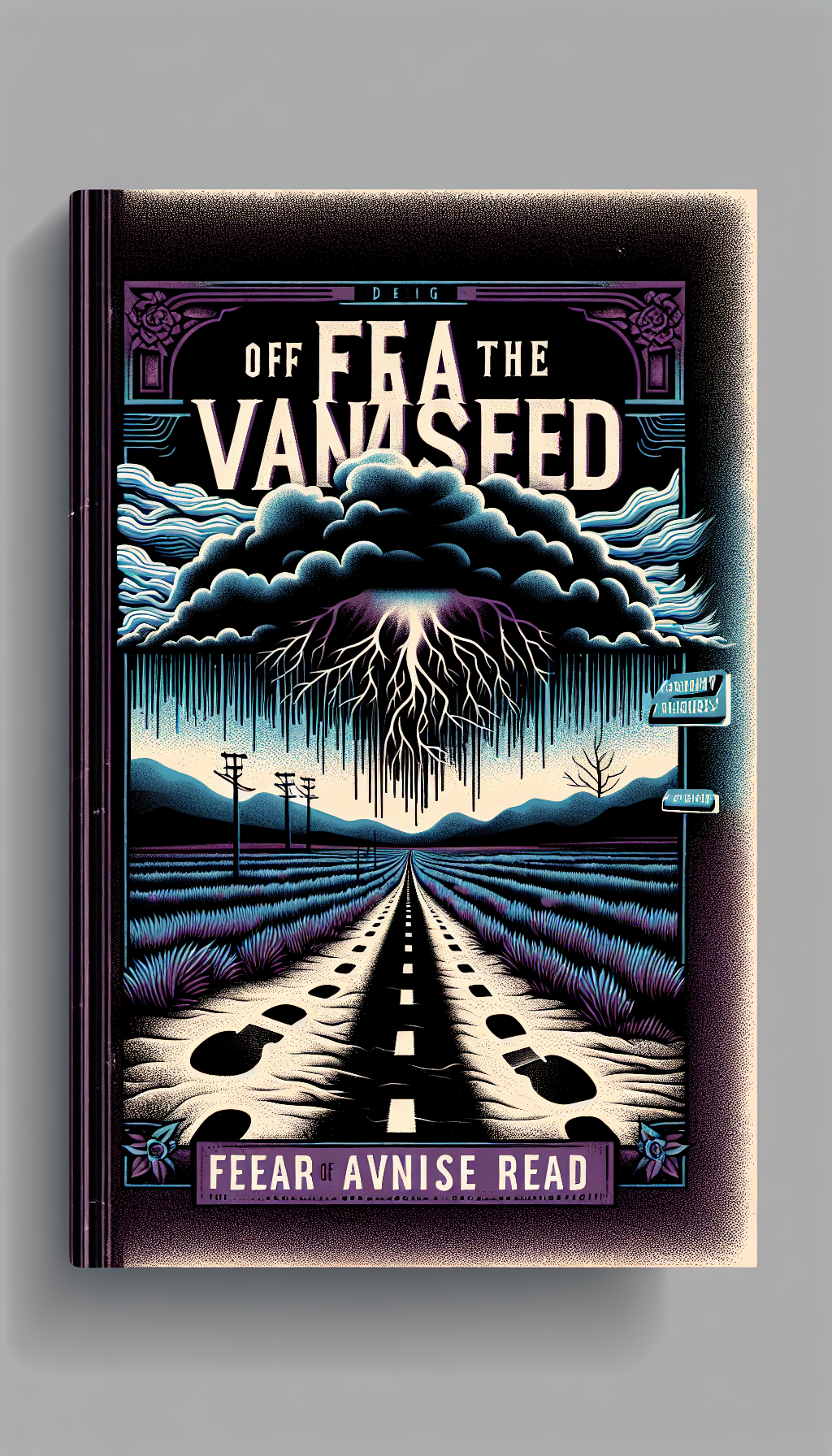影に追われて
夜が深まり、町外れの古びたアパートに一人の青年、拓哉が住んでいた。拓哉は作家志望で、ホラー小説を書くことに情熱を注いでいたが、なかなかアイデアが浮かばずにいた。そんなある晩、彼は近所の廃屋から奇妙な音を聞いた。カンカンと叩く音と、微かに聞こえる女性の泣き声。興味を惹かれた拓哉は、その音の正体を確かめるため、廃屋へと足を運んだ。
廃屋は、かつてここに住んでいた女性が謎の失踪を遂げたという噂が絶えない場所だった。入るなり、彼は胸がザワザワとするのを感じたが、一歩ずつ進むうちに、不安よりも好奇心が勝り、彼は奥へと進んでいった。そこには、かび臭い空気とともに、ひび割れた壁が待っていた。
家の中は荒れ果てており、家具も散乱していたが、ふと目に留まったのは床に落ちていた古びた日記だった。ページをめくると、その女性の思い出や苦悩が綴られており、彼女の過去に深く引き込まれていく。特に興味を引いたのが、彼女が恐れていた夢の中の存在についての記述だった。それは、自分をずっと観察しているような、影のような存在だった。
拓哉は、この女性の恐怖を小説の題材にしようと考え、日記を持ち帰ることにした。帰宅する途中、道端で彼の足元に何かが光った。拾い上げると、それは小さな銀色の鍵だった。彼はその鍵に運命を感じ、再び廃屋へ戻ることを決意した。
次の日、彼は再び廃屋へ足を運び、鍵が何を開けるのかを探し始めた。すると、日記に記されていた部屋を見つけ、その部屋のドアに鍵穴があることに気づいた。ドキドキしながら鍵を差し込み、回すと、軋む音を立ててドアが開いた。中に入ると、驚くべきことに、壁のすべてに女性の描いた絵が飾られていた。それは、彼女が夢の中で見た影の存在を描いたものだった。
拓哉はその絵に魅了され、筆を走らせ、この新たなインスピレーションで小説を書き始めた。しかし、物語が進むにつれ、彼は日記の中に記されていた「影」の存在を感じるようになった。特に夜になると、その影に見られているかのような不安感に襲われ、彼の創作は次第に狂気じみていった。
ある晩、拓哉は眠りに落ちると、夢の中で女性とその影に出会った。影は彼に向かって手を伸ばし、何かを訴えるように囁いた。目が覚めたとき、彼は冷や汗をかいていたが、その囁きが耳に残り、創作意欲はますます高まった。
その後、短期間で小説は完成し、彼はそれを出版社に送った。しかし、すぐに編集者から連絡があり、内容があまりにも恐ろしいため、出版は見送られたと告げられた。拓哉は愕然とし、呆然としてしまった。
数日後、彼は再び廃屋を訪れた。暗闇に包まれた部屋の中で、彼は日記をもう一度読み返し、影に関する最後の記述を見つけた。「私は彼を観察している。彼に近づくたびに、彼は自分の影を消すことができない」と書かれていた。拓哉は背筋が凍る思いをし、その場から逃げ出した。
しかし、影は拓哉の逃げ道を塞ぐかのように、彼の後ろにまとわりついていた。帰宅する道すがら、彼の心の中で不安と恐怖が渦巻き、影が自分に何かを無理矢理させようとしているという思念が強まった。彼は自分が書いた小説の恐怖がリアルになっているのではないかと考えるようになり、自身が恐れていた影の存在が彼の創作から生まれたものではないかと疑念が深まった。
拓哉はすべてを放り出し、逃げるように別の町に移り住んだ。しかし、どこに行っても、その影は彼を追いかけ続けた。彼の後ろには常にその怖ろしい存在があった。結局、拓哉は創作の恐怖から逃げられず、彼の人生そのものがホラー小説の一部となってしまったのだ。
廃屋は誰も近づかない場所となり、時間が経つごとにその存在は記憶から消え去っていった。拓哉の名前もやがて忘れ去られ、彼が書いた小説のことも誰も覚えてはいなかった。しかし、影だけは降り続く雨のように、どこかで生き続けているのだろう。彼を追い詰めたその存在は、今や彼の物語の中で永遠に続いているのかもしれない。