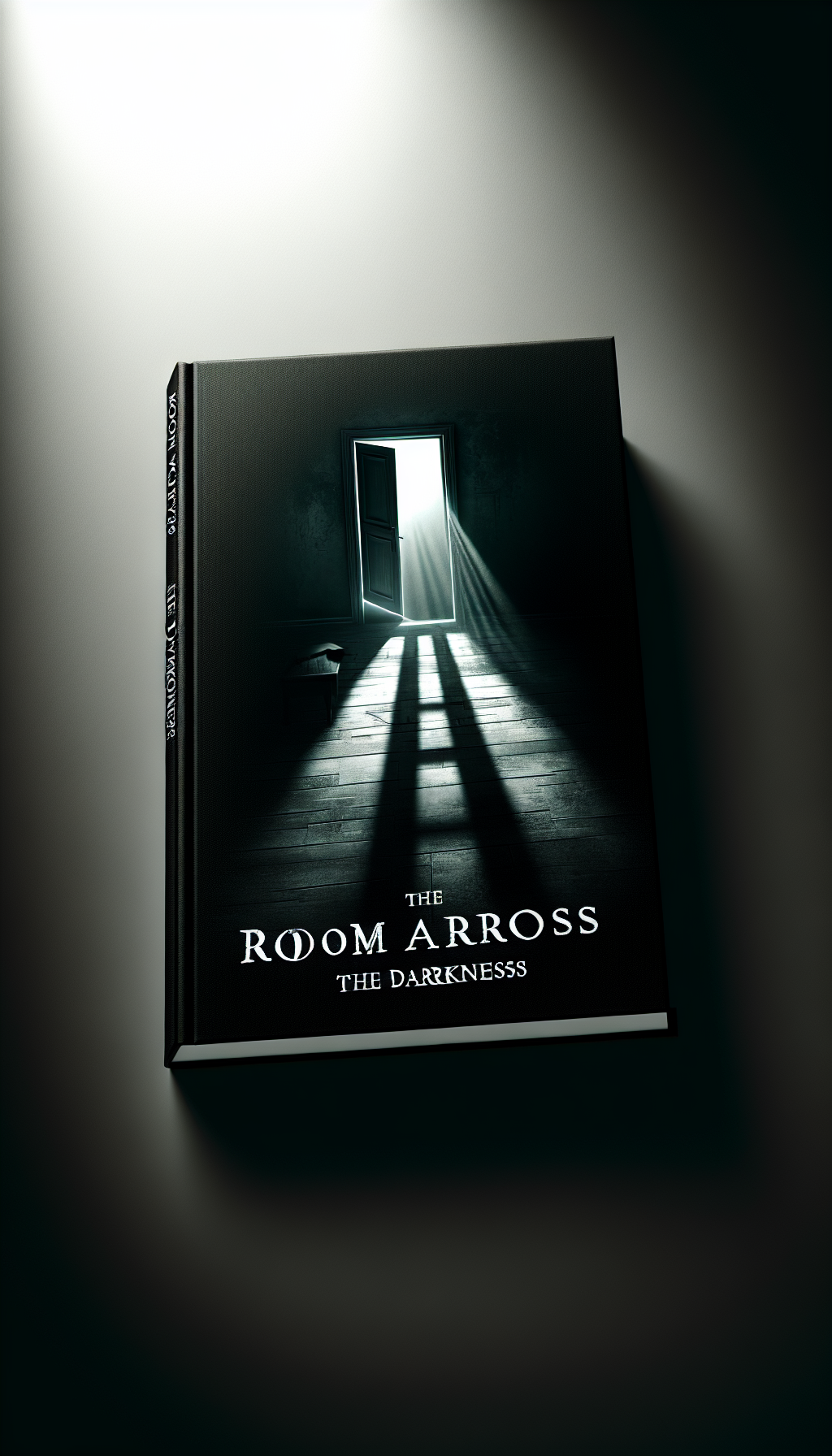闇に寄り添う心
彼女の名前は真紀。どこにでもいる普通の高校生だが、彼女の心の奥には、他者を理解することができない暗い闇が潜んでいた。真紀にとって、感情というものは他人の表面的な表情や行動を真似るための手段であった。彼女は母親の死をきっかけに、家族からの愛情の温かさを感じたことがなかったため、他人の痛みや喜びを理解しようとすることはなかった。
ある日、放課後の帰り道、真紀はひとりの少年を見かけた。彼の名前は健太。彼は、いつもひとりで公園のベンチに座り、本を読んでいた。真紀は、彼が醸し出す独特の雰囲気に惹かれ、徐々に彼の存在を意識するようになった。しかし、周囲の人々が語る健太の評判は良くなく、変わり者として知られていた。興味を持った真紀は、彼にアプローチを試みることにした。
「ねぇ、何を読んでるの?」と真紀が声をかけると、健太は驚いたように顔を上げた。一瞬、彼の瞳には警戒心が宿ったが、すぐにその表情は柔らかくなった。彼女の笑顔には、真実を感じさせるものがあったからだ。
「推理小説だよ。君も読むの?」と健太は、少し照れながらも答えた。話が進むにつれて、真紀は彼がただの変わり者ではなく、非常に知的で面白い人物だと知ることができた。彼の言葉には、確かな洞察力があった。
数週間後、二人はすっかり親しくなり、真紀はいつしか健太を特別な存在として意識するようになった。しかし、彼に対する愛情は、彼女の中にある暗い衝動を刺激するものだった。真紀は、満たされない心の穴を埋めるために、ついに健太についてのリサーチを始める。
彼女は、健太が夜中に教室に忍び込み、独りで何かをする姿を目撃する。興味本位で彼の後を追った真紀は、彼がクラスメートたちの私物を破壊する姿を目の当たりにした。彼は、何かに取り憑かれたような表情で、無心に作業を続けていた。その瞬間、真紀の心の中に暗い興味が芽生え始めた。健太の内面に潜む狂気を知りたいと思ったのだ。
翌日、真紀は彼を呼び出した。「昨日、あなたが教室にいたのを見たの。何をしていたの?」健太は一瞬驚いた様子だったが、すぐに微笑みを浮かべた。「ただの遊びさ」。その言葉には、どこか不気味な響きがあった。
その後、真紀は健太の背後にいることの快楽を感じ、彼の闇の一端に触れていく。彼の中に宿るサイコパス的な側面は、次第に彼女を引き寄せ、彼女自身の中にも暗い衝動が芽生えてきた。彼女は自分の心が変わり始めていることに気が付かなかった。
ある晩、真紀は決意した。健太と一緒に、誰もいない学校のアトリエに侵入することにした。彼女は彼に提案し、一緒にアトリエの作品を見学することになった。そこで待っていたのは、淡々とした彼のもう一つの顔だった。真紀は、その冷徹な一面を目の当たりにし、自分もその一部になりたいという漠然とした欲望を抱くようになった。
アトリエには古い人体の模型があった。健太はその模型を指さし、「君もこれに興味があると思うよ」と言った。彼の目は燃えるような興奮に満ちていた。真紀はその冷たい目に呑み込まれ、興味と恐怖が同時に駆け巡った。彼女はついに健太が隠していた真実に触れようとしていた。
数日後、真紀は健太を正式に誘い出し、新たな計画を立てることにした。彼女は、二人で一緒に町の外れにある古い廃屋に向かうことを提案した。彼らは内部を探索し、恐怖に満ちた静寂に包まれる。そこで、二人はかつての住人の遺品を見ることになる。
突如、健太の目が光り輝き、不気味な笑みを浮かべた。「何か面白いことができそうだ」。彼の言葉とともに、彼は一冊の古びたノートを見つけ出した。そのノートには、過去の凶悪犯罪の詳細が書き記されていた。彼の目は狂気の輝きで満ち、真紀はその瞬間に彼に完全に惹きつけられた。
その夜、真紀は健太と共に狂ったように過去の犯罪に感化され、彼女の心に宿った恐ろしい興味に従い、恐ろしい行動に出ることを決意した。彼女は、健太と共にその暗い夢を叶えるパートナーとなることを選んだ。
真紀の中にあった最後の良心は消え去り、彼女は完全に健太に心を奪われてしまった。彼女は彼に寄り添い、共に闇の淵に向かっていく。二人は、サイコパス的な絆によって結ばれたのだ。
置き去りにされた人々、破壊された心、失われた命、そして、彼女たち自身の運命がどうなるのか、誰もわからなかった。しかし、真紀と健太の心中には、確かな冷たさだけが残るのだった。