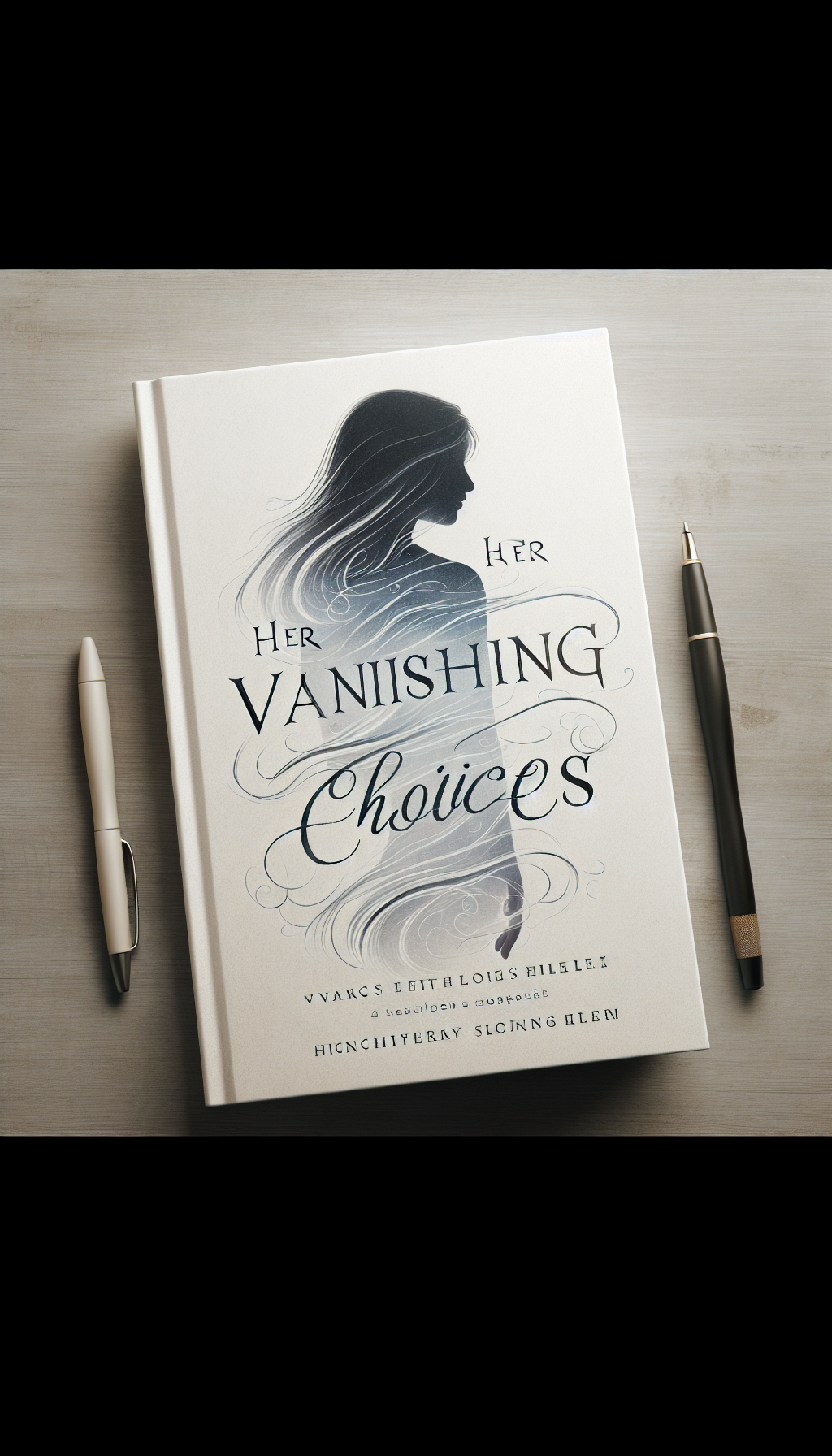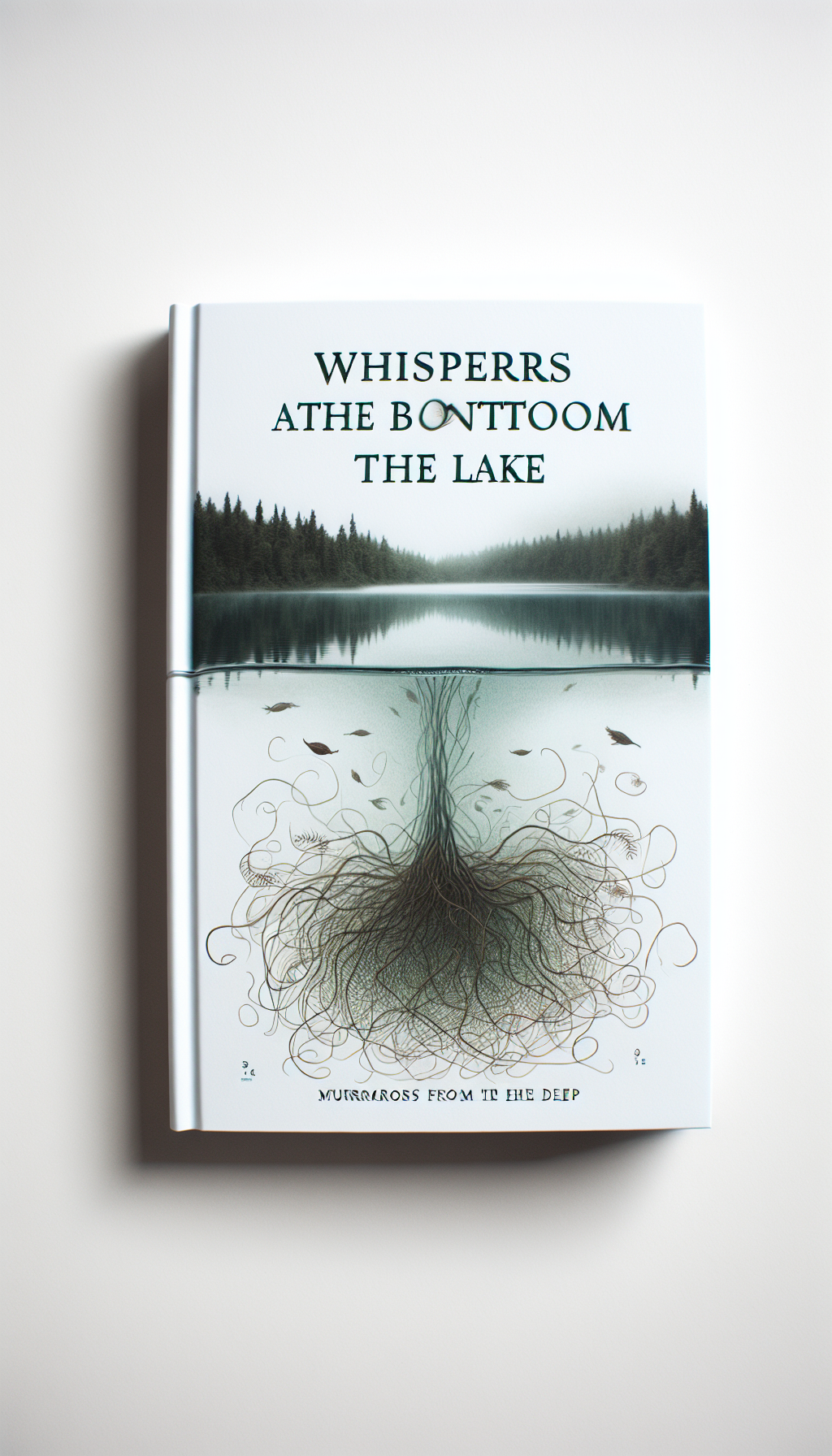霧中の恐怖
仕事の帰り道、真紀は霧に包まれた街を歩いていた。冷たい風が彼女の頬を撫で、薄暗い路地に入ると、心に不安がよぎる。最近、神奈川の街で連続失踪事件が発生していた。この夜も、あの事件が頭から離れなかった。
彼女は急ぎ足で先を急いだ。いつも経由する道を通るのは怖かった。だが、何かに引き寄せられるように、ふと目に入った小さなカフェの明かりが、彼女をその場に留めた。心が引かれた理由は分からないが、何か特別なものに触れたような感覚があった。
カフェに入ると、薄暗い店内には数人の客が静かに過ごしていた。真紀はカウンターに座り、温かいコーヒーを頼む。店内の雰囲気は落ち着いていて、彼女の緊張も少し和らいだ。しかし、ふと視線を感じた。カウンターの隅にいる男性が、真紀をじっと見つめていた。
彼女は気にしないようにしたが、その視線は不気味だった。気になる思いを抱えたまま、彼女はコーヒーを飲んで少し考えを整理した。最近のニュースでの失踪事件のことが頭を離れなかった。この男性が犯人だと決めつけるつもりはないが、直感的に何かが違うと感じた。
コーヒーを飲み終えた真紀は、いったん席を立ちトイレに向かう。その途中、掘りごたつのような席に座っている女性が手を差し出し、低い声で囁いた。「気を付けて。あの男、危ないわ。」
真紀は驚き、振り返った。その女性は目を細めて彼女に目を合わせながら、顎を引いてカウンターの方を指差した。すると、視線で示された男性は、真紀と目が合った。彼は口元に笑みを浮かべているようだった。どこか不気味なその笑顔に、真紀の心臓が高鳴った。
トイレを出ると、真紀は急いでカフェを出ることにした。ただの偶然かもしれないが、不安が積もっていた。カフェの出口に向かうと、背後で扉の音が聞こえた。振り向くと、男性が後ろに立っていた。
「君も仕事帰り?」彼は優しい声で話しかけてきた。真紀はジェットコースターのような心臓の鼓動を感じ、表情を硬直させた。「ええ、たまたま寄っただけです。」
彼は微笑みながら近づいてきた。「ここは落ち着く場所だよね。みんなの話を聞いていると面白いことがたくさんある。」
その言葉に、真紀は恐怖を感じた。失踪事件の犯人が次の獲物を狙っているのだろうか。心の中で叫びたい思いを抑え、彼女は後ずさりした。「すみませんが、私はもう帰ります。」
男性の表情が一瞬、驚愕に変わった。それから、ゆっくりとした動作で手を伸ばした。「君、耐えられないだろう?一緒に話そうよ。」
その瞬間、真紀の本能が警告を発した。彼女は全力で逃げだした。夜の街を横切り、次の路地に飛び込む。恐怖に駆られながらも、振り返る余裕はなかった。
心臓は激しく鼓動し、脚は疲労で満ちていた。何度も振り返りながら、彼女は真実を知る必要があった。彼女の心の奥底にある不安は、彼女を追い詰めるように感じた。その根源を突き止めなければならない。
路地を抜け、繁華街に出ると、真紀はほっとした。ひと気のある場所に戻ると安心感が広がる。しかし、ふとした瞬間、彼女の背後から声が聞こえた。「真紀さん、どこに行ってたの?」
彼女は振り返り、驚愕した。彼女の親友、彩がいた。しかし、彼女の顔は普段の明るさとは違っていた。目がうつろで、まるで何かに取り憑かれているかのようだ。
「彩…?」
その瞬間、真紀は何かを感じ取った。彩の背後にあの男性が立っている。彼は完全に無防備な状態で微笑み、真紀をじっと見つめている。真紀の心は氷のように冷たくなった。彩がその男に従っているのか。
「真紀、彼と話してみなよ。彼の話は素晴らしいから。」彩の声は、まるで何かに操られているようだった。
真紀は恐怖を抑え、ゆっくりと後退りしながら言った。「彩、あの男から離れて!」しかし、彩はまるで彼女の声が耳に入らないかのように、無表情で微笑んでいた。
何が起こっているのか理解できない。真紀は逃げようと振り返った。だけど、足がもつれて地面に倒れ込んだ。すぐ背後にはあの男性が迫っていたのだ。そして、目が合った瞬間、彼は「もう遅いよ」と低く囁いた。
真紀は恐怖に襲われ、視界が暗くなり始めた。記憶の中だけで響く親友の笑い声と、冷たい空気の中で彼女はその場に倒れた。惨劇はすでに始まっていたのだ。どの時点で真実が狂っていったのだろうか。彼女はただ、逃れられない運命に翻弄されるだけだった。